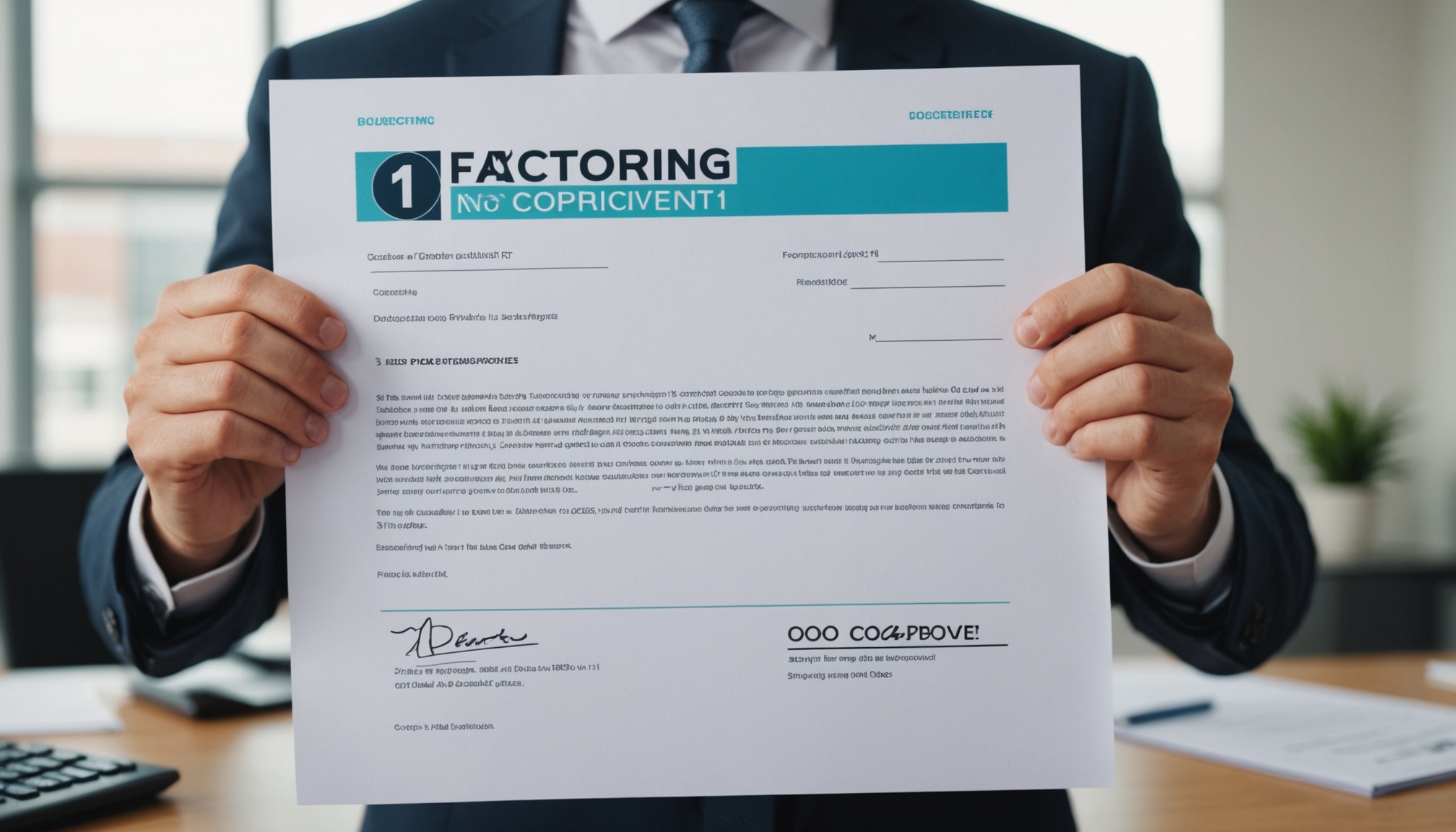2024.12.25
中小企業が知っておくべき金融支援の基礎知識~決算書の重要性と債務者区分の実態~
金融支援を受ける際、最初に求められるのが「決算書」の提出です。
特に中小企業においては、決算書が融資審査の7割以上を占める重要な要素となっています。
さらに、金融機関は決算書をもとに企業を「債務者区分」に分類し、その結果が支援の可否に直結するケースも多々あります。
本記事では、金融支援における決算書の重要性や債務者区分の概要、中小企業特有の審査方法について解説します。
また、緊急支援と通常支援の違いにも触れながら、企業が金融支援を受けるための準備やポイントについてお伝えします。
金融支援をスムーズに進めたい方、これから融資を検討している方は、ぜひご一読ください。

金融支援と決算書の重要性
決算書が審査に与える影響
金融支援を申請する際には、必ず決算書の提出が求められます。
審査担当者は、貸借対照表や損益計算書、税務申告書を含む一式の書類を確認し、その内容で支援の可否を判断します。
特に中小企業の場合、金融支援審査の7割以上が決算書の内容で決まります。
一方で都市銀行などでは、その割合がさらに高くなり、9割程度と言われています。
提出された決算書の内容が適切でない場合、金融支援を受けることが難しくなるため、慎重な準備が必要です。
決算書に必要な書類
以下の書類は、金融支援審査において一般的に提出が求められるものです。
【主な決算書類】
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
・税務申告書一式(勘定科目内訳明細、固定資産台帳など)
これらを正確に準備し、内容に不足や誤りがないようにすることが重要です。
債務者区分とその役割

債務者区分の概要
金融機関は提出された決算書をもとに、企業を「債務者区分」に分類します。
債務者区分には以下のような分類があり、企業の業況に応じて評価されます。
【債務者区分の分類】
1. 正常先
2. 要注意先
3. 要管理先
4. 破綻懸念先
5. 実質破綻先
6. 破綻先
この分類は、企業の財務状態を示す重要な指標となり、特に「正常先」や「要注意先」に分類されることが金融支援の前提条件となります。
金融支援への影響
企業が「破綻懸念先」や「実質破綻先」に分類されると、金融支援の取得が難しくなります。
特に債務超過の状態で支援を申請する場合、その影響はさらに顕著です。
金融機関は債務者区分に応じた対応を取り、融資方針を決定します。
現行の債務者区分の運用<h3>
2019年に金融検査マニュアルが廃止されたにも関わらず、債務者区分の考え方は現在でも実務で利用されています。
各金融機関は独自の基準を導入していますが、債務者区分の枠組みは依然として重要な判断材料として用いられています。
中小企業と大企業の決算書の違い
大企業の監査と中小企業の税務申告
大企業の決算書は、監査法人による詳細な監査を受け、「無限定適性意見」という適正性の保証を得ます。
一方、中小企業の場合、税務申告が主目的であり、監査が行われないため、内容の信頼性に差があります。
中小企業決算書の評価方法<h3>
中小企業の決算書は、そのまま信用されることが少なく、審査担当者により「資産の減額修正」や「費用の増額修正」が行われます。
この結果、債務超過と評価されるケースも多いため、慎重な準備が必要です。
金融支援を受けるための準備

審査の下方修正を回避する方法
下方修正を避けるためには、決算書にコメントを添付することが有効です。
例えば、売上債権が多い場合には、その理由を季節要因などで具体的に説明することで、誤解を防げます。
適切な財務戦略の実施
金融支援を受けるためには、計画的な財務戦略が不可欠です。財務内容を適切に管理し、金融機関の基準に適合する状態を維持することが重要です。
緊急支援と通常支援の違い
緊急支援メニューの特徴
コロナ禍では、多くの緊急支援メニューが提供されました。
これらは債務者区分に関係なく利用可能であり、赤字や債務超過の企業でも申請できるものが多く含まれます。
情報収集と活用方法
緊急支援の情報は、日本政策金融公庫や取引金融機関から発信されます。常に情報収集を行い、適切なタイミングで活用することが重要です。
まとめ
本記事では、金融支援を受けるための決算書の重要性や、債務者区分の影響、中小企業と大企業の決算書の違い、さらに緊急支援と通常支援の特徴について解説しました。
これらを正しく理解し、準備を行うことで、金融支援を円滑に受ける可能性を高めることができます。
しかし、金融支援の申請や適切な財務戦略の実施には専門的な知識が必要であり、独力での判断が難しいと感じられる企業様も多いのではないでしょうか。
そんな企業様をサポートするのがHTファイナンスです。
HTファイナンスでは、豊富な経験と専門知識を活かして、企業ごとの状況に応じた最適な資金調達方法をご提案いたします。
安定した経営環境の構築に向けた支援を行い、事業成長のお手伝いをさせていただきます。
法人企業向けの融資サポートで30年の実績を持つHTファイナンスに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。