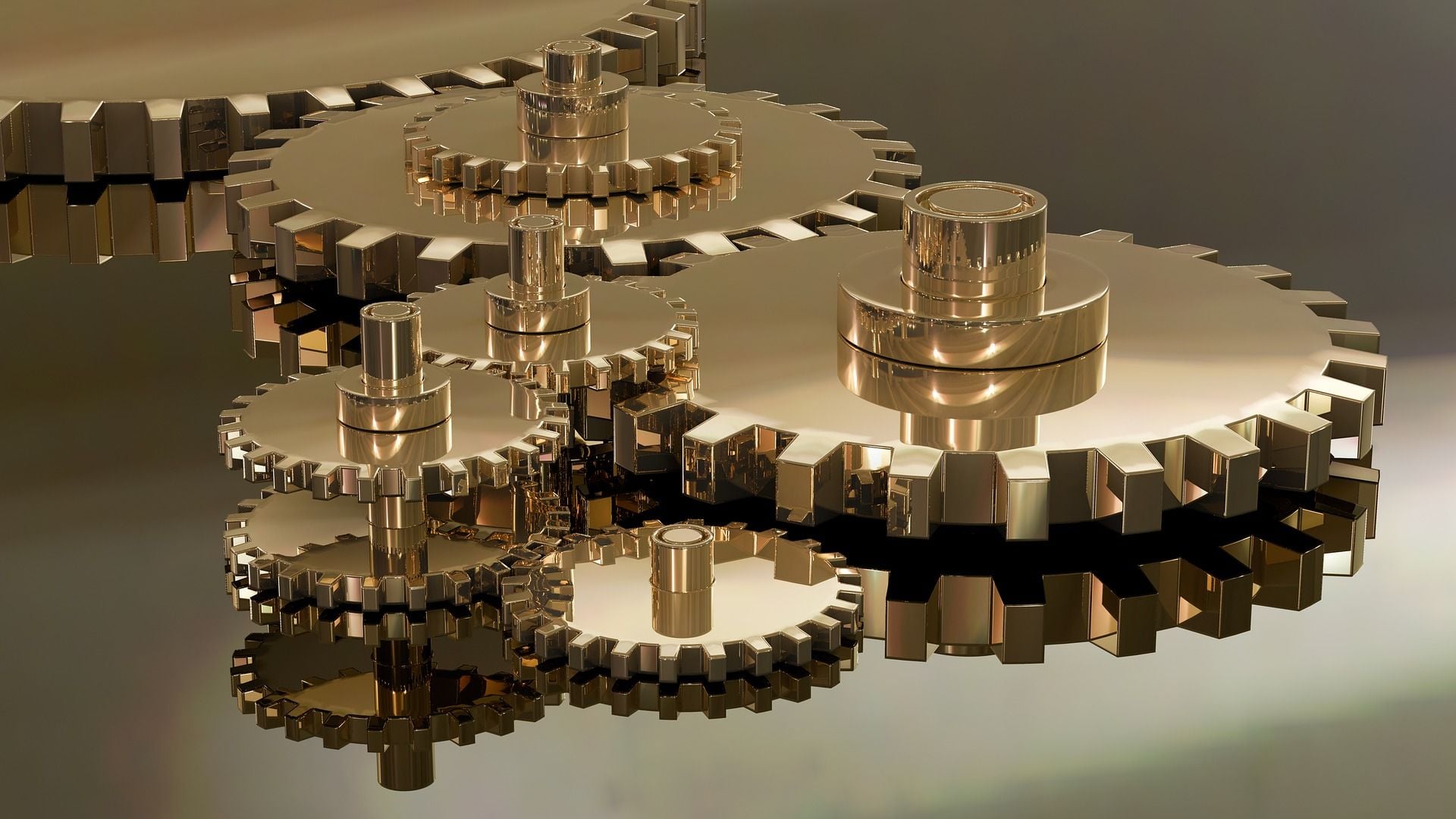2025.05.31
売掛金の増減が資金繰りに与える影響とは?
売掛金の増減は、企業のキャッシュフローに直結するポイントです。製品やサービスを販売した対価として計上される売掛金は、回収タイミングが遅れると迅速な資金調達が必要になるケースも出てきます。本記事では、売掛金が増減した際に経営者がどのようなリスクやメリットを認識し、どのような管理や資金繰り対策を行うべきかを解説します。
中小企業をはじめ、多くの企業は事業の運転資金をスムーズに回すために資金調達手法を検討します。例えば、銀行融資や補助金、ファクタリングなどのさまざまな手段がある中で、売掛金を管理することはキャッシュフローの土台を安定させる上で非常に重要です。なぜなら、売掛金の増減が貸借対照表や損益計算書に表れるだけでなく、日々の経営判断にも影響を及ぼすからです。
特に売掛金が拡大している企業においては、一時的に手元資金が減少することで新しい投資や仕入れが滞る可能性があります。こうした場合、資金調達を効率的に進めるためにも、売掛金の回収サイクルを短縮する工夫や与信管理を徹底することが求められます。本記事を読み進めることで、事例を含めた効果的な管理方法や、期末時点の数字をどのように読み解くべきかを理解していただけるでしょう。
売掛金の増減と資金繰りの関係とは
企業が商品やサービスを提供した後に発生する売掛金は、回収のタイミングによって資金繰りの良し悪しを大きく左右します。
売掛金は一度に多額の現金収入を見込めるものの、取引先との支払い条件によっては回収が先延ばしになることがあります。たとえば、60日後や90日後の支払いを取り決めている場合には、当面の運転資金が不足しがちになります。こうした状況では、即時の資金調達を図るために追加の融資を受けたり、他の資金繰り対策を講じたりする必要性が高まるのです。
一方で、売掛金は長期的な視点で見ると企業の信用力を示す指標にもなり得ます。売上高が拡大している企業であれば売掛金も同時に増加しやすく、取引先の多様化によって今後の売上も期待できます。ただし、増加分が適切に回収されなければ、最終的にキャッシュフローが滞り倒産や支払い不能のリスクが高まるため注意が必要です。
近年では、売掛金が回収できずに経営破綻にまで追い込まれる事例も散見されます。こうしたケースを未然に防ぐには、企業が日頃から売掛金管理の重要性を認識し、適切な回収サイクルの設定や資金調達計画を立てることが欠かせません。ファクタリングなどを上手く活用すると、日々の資金繰りを安定させる上で効果的です。
売掛金が増加した場合
売掛金は、売掛先から代金の支払いを受ける権利です。取引先に商品やサービスを販売した後に発生します。
売掛金増加の原因は、いくつか考えられます代表的な原因は以下の通りです。
- 売上が増えた
- 売上は横ばいだが、取引先が売掛金の支払いに遅れた
- 売上は横ばいだが、取引先との契約変更によって回収サイトが長期化した
売上の増加に比例して売掛金が増加する流れは分かりやすいでしょう。しかし、売上が横ばいでも売掛金が増加することがあるため、注意が必要です。
売掛金は、売上に伴って発生します。売上を得るまでには様々な経費を支払っているため、売上が増加すれば経費も増加し、資金繰りへの負担が大きくなります。
売上が横ばいの場合、経費の負担も変わりません。しかし、売上の回収が遅れることによって売掛金が増加すると、お金が入ってくる動き(売上回収)が鈍く、お金が出ていく動き(経費支払)が変わらないのですから、資金繰りが悪化します。
売掛金が減少した場合
売掛金減少の影響は、売掛金増加の逆を考えると分かります。簡単にみていきましょう。
売掛金減少は、以下のような原因によって起こります。
- 売上が減少した
- 売上が変わらず、取引先との契約変更によって回収サイトが短縮した
売上が減少すれば、売掛金も減少します。取引先との契約変更による回収サイト短縮も効果的です。
売上が増加した場合、回収サイトを短く設定しても、現金回収でない限り売掛金の増加は避けられません。ただし、取引先全体での平均回収サイトが短くなれば、資金繰りには良い影響が期待できます。
売上が変わらずに売掛金が減少することは、売上がスピーディに回収できていることを意味します。お金が入ってくる動き(売上回収)が早くなり、お金が出ていく動き(経費支払)が変わらなければ、資金繰りはラクになります。
売掛金で資金繰りが悪化した実際の事例
大口の取引先が突然支払いを遅延させたことで、売掛金の回収ができず資金ショートを起こした例があります。特に中小企業においては取引先の信頼度や与信管理を怠ると、他の顧客からの売掛金で補えず倒産の危機に直面するリスクが高まります。こうしたケースを防ぐには、早めの資金調達や与信管理の徹底を行い、複数の取引先と安定した関係を築くことが重要です。
期首→期末の増減で考える
売掛金は期首と期末の金額を比較することで、キャッシュフローの推移と資金繰りの変動をよりわかりやすく把握できます。
企業は会計期間内に発生する売掛金を継続的に管理し、期末に向けての上昇や下降の要因を分析する必要があります。期首から期末にかけて売掛金がどの程度増減したかを把握することで、回収力や営業活動の状況を視覚化でき、資金繰りや新たな資金調達方法を検討する判断材料になります。
また、売上拡大を目指す企業ほど、売掛金も大きくなる傾向があります。新規顧客の獲得に特化した戦略では、期末時点で売掛金が増加していることがよくあります。この状況が続く場合は、与信管理を強化しながらファクタリングを活用するなど、現金化を促進し経営を安定させるための手段を柔軟に取り入れることが推奨されます。
逆に、期末時点で売掛金が大幅に減少している場合は、売上が鈍化している可能性を疑う必要があります。もちろん、スムーズな回収が進んだ結果とも考えられますが、今後の利益確保に向けてどのような施策を打つかを検討することも重要です。事業の方向性や新しい資金調達方法を見直す機会として、売掛金の変動状況を冷静に判断しましょう。
基本的には、
- 売掛金が増加すれば資金繰りが悪くなる
- 売掛金が減少すれば資金繰りが良くなる
ということは間違いありません。この事実は、売上が変わらない状態で、期首と期末の売掛金が増減するケースを考えるとよく分かります。
売上高が1,000万円のA社を例に、売掛金の増減と資金繰りの関係をみていきましょう。
1期目:現金で全額回収
A社は、一般消費者向けに飲食店を経営する会社です。
シミュレーションの1期目の時点では、A社は期中の売上を全て現金で回収していました。クレジットカード決済を導入しておらず、来店したお客さんは必ず現金で支払う仕組みです。
| 期中の売上高 1,000万円 |
期中の現金回収額 1,000万円 |
全額を現金で回収するのですから、期中の売上高と期中の現金回収額は一致します。期首の売掛金残高はゼロ、期末の売掛金残高もゼロで増減はなく、資金繰りへの影響もありません。
創業初期などでまだ取引先が限定されている場合、全ての売上を現金で回収できるケースがあります。これは資金繰りが非常に楽な状態と言えますが、受注拡大を図るためには掛取引が増えてくることも多いです。将来的に売掛金が増加する可能性があるため、次のステップに備えて資金調達の選択肢も視野に入れておくと安心です。
2期目:期末に売掛金が発生
2期目から、A社は来店客へのクレジットカード決済を導入し、代金後払いのデリバリーサービスも始めました。新型コロナウイルス感染症の影響により来店客が激減し、従来の仕組みでは売上激減がほぼ確実であったためです。
このため、1期目は全額現金回収であったものが、2期目以降は来店・現金払いのお客さんは現金回収、来店・クレジット払いのお客さんとデリバリーのお客さんは売掛金によって回収することとなりました。
幸いにもデリバリーサービスが大盛況となり、売上高1,000万円を維持できたのですが、一方で売掛金が増加しました。
| 期中の売上高 1,000万円 |
期中の現金回収額 700万円 |
| 期末の売掛金残高 300万円 |
その結果、期中の売上高は1,000万円で変わりませんが、そのうち回収できた現金は700万円に止まり、期末時点で未回収の売掛金が300万円残りました。期首の時点ではゼロだった売掛金残高が、期末時点では300万円に増加したのです。
全額現金回収で1,000万円を回収していたときは、経費などを1,000万円から支払うことができました。これに対し、2期目は700万円しか回収できず、資金繰りに使える資金も300万円減っています。
事業が軌道に乗り始めると、掛取引の増加にともなって売掛金が少しずつ発生し始めます。期末に売掛金が存在するということは、来期の入金を見込む一方で、当面の手元資金不足を感じる場面が出てくるかもしれません。そのため、必要に応じて融資やファクタリングなどの資金調達を検討し、資金繰りの乱れを未然に防ぐことが大切です。
3期目:期末の売掛金が増えた
3期目は、2期目の売掛金残高300万円を引き継いでスタートします。期中の売上高は変わらず1,000万円です。
3期目の結果は以下の通りです。
| 期首の売掛金残高 300万円 |
期中の現金回収額 900万円 |
| 期中の売上高 1,000万円 |
|
| 期末の売掛金残高 400万円 |
期中の現金回収額は900万円でした。2期目の現金回収額よりも200万円増えており、資金繰りが改善したようにみえるかもしれません。しかし、3期目も資金繰りは悪化しています。
期末の売掛金残高が400万円で、2期目の期末より100万円増えていることに注目してください。
期首の売掛金300万円は2期目に発生したものであり、3期目の早いうちに全額回収できるはずです。また、2期目同様、売上高1,000万円のうち700万円を回収できるならば、3期目の期中現金回収額は1,000万円になるはずです。その場合、期末の売掛金残高は300万円となり、期首からの増減はゼロ、資金繰りへの影響もゼロとなります。
しかし、最終的な期末の売掛金残高は100万円増加の400万円でした。事実、A社では3期目もデリバリーサービスの売上が伸び、売掛金が増加していたのです。この100万円の分だけ、資金繰りは悪化しています。
取引先や受注が増え、売上が拡大している企業では、期末時点で売掛金も大幅に増える傾向があります。これは事業成長の証とも言えますが、その反面、まとまった資金が手元に入るまでに時間がかかるリスクを伴います。与信管理をしっかりと行い、万が一の回収トラブルに備えて複数の資金調達ルートを確保しておくと、資金繰りの安定につながります。
4期目:期末の売掛金が減った
このままでは資金繰りが苦しくなる一方です。A社は資金繰り改善のために、売掛金を減らすように取り組みました。
店内サービスを充実させることで、デリバリーサービスの利用客に来店を促したり、来店時の支払いの際、現金払いで使える割引券を発行したりすることにより、現金回収を増やすようにしたのです。
その結果、4期目は以下の結果となりました。
| 期首の売掛金残高 400万円 |
期中の現金回収額 1,300万円 |
| 期中の売上高 1,000万円 |
|
| 期末の売掛金残高 100万円 |
期首の売掛金400万円をしっかり回収し、期中の売上高1,000万円のうち現金回収額を900万円に伸ばしたのです。期中の現金回収額は1,300万円、期末の売掛金残高は100万円となりました。
期首から期末にかけて、売掛金残高は300万円も減少しています。これにより、資金繰りも改善されます。
もちろん、全額現金回収していた1期目に比べると、売掛金残高100万円の分だけ資金繰りは悪化しています。しかし、元々A社は売上悪化を防ぐためにクレジット決済やデリバリーサービスを始めたのです。この取り組みがなければ売上が激減し、経営そのものが危なかったかもしれません。
このように考えると、売上高1,000万円を維持し、なおかつ売掛金100万円分の資金繰り悪化に止めた結果は悪くないといえるでしょう。
期末において売掛金が減少するということは、スムーズな回収が行われている可能性が高い状態です。手元資金が増加することで、仕入れや設備投資など新たな行動を起こしやすくなります。一方で、売掛金の減少が売上低迷を映すものでないかを確認し、必要に応じて当初の営業戦略や資金調達計画を見直すことも重要です。
売掛金管理のポイント
売掛金管理においては、与信管理と早期回収の仕組みづくりが不可欠です。定期的に取引先の信用状況を見直し、支払いが遅れがちな企業については条件変更や担保の設定などの対応を検討します。また、ファクタリングを活用して売掛金を早期に現金化することで、資金調達をスピーディに進められる点も見逃せません。
よくある質問
売掛金と資金繰りに関しては、「売掛金が多いほど会社は好調なのか」「回収サイトの延長にはどう対応すべきか」など、さまざまな疑問が寄せられます。まず、売掛金が多いからといって必ず好調とは限らないため、あくまでも回収可能性や支払条件を考慮することが必要です。さらに、回収サイトが延びた場合には、銀行融資や補助金の活用、あるいは早期入金割引制度の導入などで資金負担を分散させる戦略も有効です。
まとめ
売掛金の管理は資金繰りの安定と企業の成長を支える重要な要素です。
売掛金が増加する際には売上拡大の裏付けとなる一方、手元資金が不足するリスクを早期に察知し、適切な資金調達策を検討しておく必要があります。逆に、売掛金が減少傾向にある場合は、キャッシュフローが良好でも売上が落ち込んでいないかを冷静に分析すべきです。こうした取り組みを常に実践することで、企業は急な資金需要の発生時にも柔軟に対応できる体質を作り上げることができます。
期首から期末にかけての売掛金の推移を正しく把握し、早めに現金化を図る仕組みや与信管理を固めることが、安定した経営基盤を築く鍵となります。これらを怠ると、せっかくの成長機会を逃してしまうだけでなく、倒産リスクを高めるおそれもあります。売掛金の変動を常に確認し、必要に応じて資金調達を併用しながら経営を進めていくことが重要です。
もし売掛金の管理や資金調達関係で不安を抱えている場合は、専門家に相談することも選択肢の一つです。客観的な視点から最適な方法を提案してもらうことで、経営者が抱える悩みを解消しやすくなるでしょう。こうした外部の知見を積極的に導入することで、自社のビジネスをより強固なものにしていく道筋が開けます。
支援実績12,000社以上!ヒューマントラストの資金調達トータルサポート
ヒューマントラストでは、売掛金管理から融資の紹介、補助金・助成金の活用アドバイスなど、多角的に企業をサポートするサービスを提供しています。 ファクタリングやビジネスローン、銀行融資の調達支援などをワンストップでご提供しており、最短即日での現金化や融資にも対応しています。 とくに、売掛先へ通知しない2社間ファクタリングは、最短15分ほどで資金をご用意できるため、急な経営ニーズにも柔軟に対応可能です。 必要書類も最小限に抑え、オンラインやお電話でのお手続きを中心に進められますので、遠方にお住まいの方やお忙しい経営者の方でも気軽にご利用いただけます。 まずは専門スタッフが状況を丁寧にヒアリングし、それぞれに最適なプランをご提案いたしますので、資金繰りにお困りの際はぜひヒューマントラストまでご相談ください。