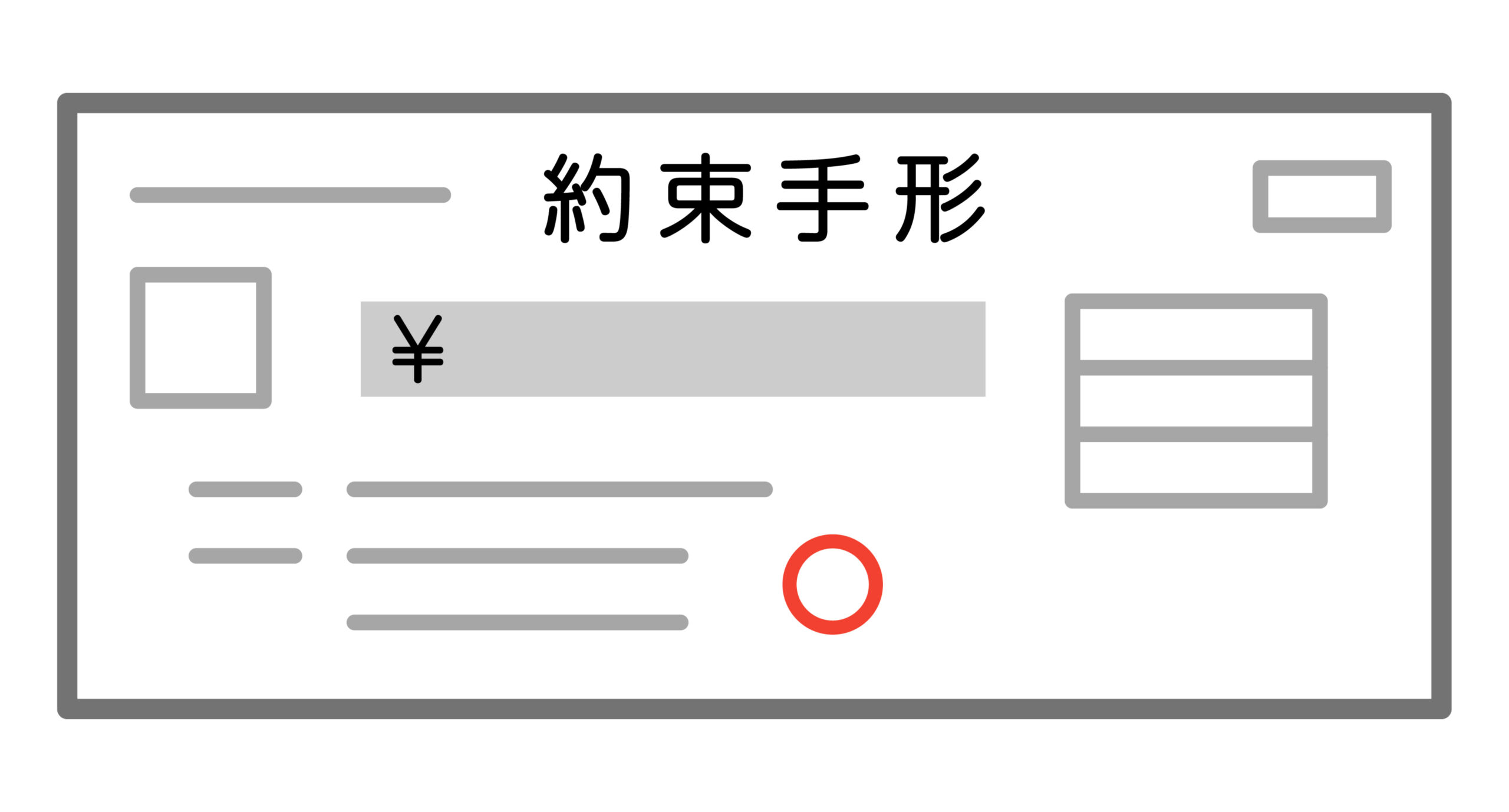2025.01.22
予実管理とは?効果的な運用のコツを解説
事業計画を立てても、思うように売上が伸びず、資金繰りに苦労されている経営者の方は多いのではないでしょうか。事業を軌道に乗せるには、計画と実績の差異を定期的に把握・分析し、迅速に対策を打つことが重要です。
この記事では、予実管理とは何か、その目的と効果的な運用方法について解説します。予実管理を適切に行うことで、経営状況が可視化され、スピーディーな経営判断が可能となります。また、組織全体で目標達成に向けて取り組む体制づくりにも役立つでしょう。
予実管理とは
予実管理とは、予算と実績を比較・分析し、その差異を管理することで経営目標の達成度合いを把握する管理会計業務のことをいいます。「予算実績管理」とも呼ばれ、経営における意思決定や業績評価に欠かせない手法の一つといえるでしょう。
予実管理を行うことで、計画と実際の業績とのズレを早期に発見し、必要な改善策を講じることができます。これにより、経営資源の効果的な配分や、目標達成に向けた軌道修正が可能となるのです。
予実管理の目的
予実管理の主な目的は、以下の3点にまとめられます。
- 経営状態の可視化:予算と実績の比較を通じて、現在の経営状況を明確に把握できます。
- 早期の課題発見:予算との乖離が生じている部分を特定し、速やかに対策を講じることができます。
- 経営判断の迅速化:リアルタイムでの情報把握により、適切なタイミングで経営判断を下せます。
これらの目的を達成するためには、適切な予算設定と、定期的かつ継続的な予実管理の実施が不可欠となります。
予実管理の対象となる予算
予実管理の対象となる主な予算は、以下の4種類に分類されます。
- 売上予算:商品やサービスの販売目標を設定するための予算
- 利益予算:売上から原価と経費を差し引いた、目標とする利益を設定する予算
- 経費予算:人件費や販売費など、事業運営に必要なコストの見積もり
- 原価予算:製品やサービスの製造に要する原価の見積もり
これらの予算は、部門別や事業別に細分化され、それぞれの責任者が管理・統制を行います。予実管理では、これら各予算の実績値と計画値の差異を分析し、必要な改善策を講じていくことが重要です。
予実管理が必要とされる背景
近年、企業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、予実管理の重要性はますます高まっています。特に、以下のような背景が予実管理を必要とする要因として挙げられます。
- 経済のグローバル化による競争の激化
- テクノロジーの急速な進歩とビジネスモデルの変化
- 顧客ニーズの多様化と製品ライフサイクルの短命化
- 経営の透明性や説明責任に対する社会的要請の高まり
このような事業環境下では、経営状況を正確に把握し、スピーディーな意思決定を行うことが求められます。予実管理は、そのための有効な手段の一つであり、企業が持続的な成長を実現する上で欠かせない経営管理手法といえるのです。
予実管理の実施プロセス
予実管理を効果的に実施するためには、適切なプロセスを踏むことがポイントになります。ここでは、予実管理の実施プロセスについて解説します。
予算の設定方法
予実管理の第一歩は、適切な予算を設定することです。予算設定の際は、まず全社的な経営目標を明確にし、それを各部門の目標に落とし込んでいきます。
各部門の予算は、売上予算、利益予算、経費予算、原価予算などに分類されます。これらの予算は、過去の実績データや市場動向を踏まえて、現実的かつ達成可能な目標値を設定することが重要です。
実績データの収集と記録
予算が設定されたら、次は実際の業績データを収集し、記録していきます。売上高、経費、利益などの主要な財務指標について、定期的に実績値を集計し、予算との比較を行います。
実績データの収集頻度は、週次または月次での実施が望ましいでしょう。これにより、リアルタイムでの業績状況の把握が可能となり、迅速な意思決定につなげることができます。
予実差異の分析方法
予算と実績の差異が明らかになったら、その原因を詳細に分析します。差異が生じた要因を特定し、それが一時的なものなのか、構造的な問題なのかを見極めることが重要です。
分析の際は、重要度の高い差異に注力し、優先順位をつけて対応していくことが効果的です。また、必要に応じて予算の修正を検討することも大切です。
分析結果を踏まえた改善策の立案と実行
差異分析の結果を受けて、課題解決のための具体的な改善策を立案します。改善策は、実行可能で効果が期待できるものを選定し、実施計画を策定します。
立案した改善策は、速やかに実行に移すことが重要です。改善策の進捗状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて軌道修正を行いながら、目標達成に向けて取り組んでいきます。
PDCAサイクルの重要性
予実管理を持続的に行うためには、PDCAサイクルを確立することが不可欠です。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のプロセスを継続的に循環させることで、業務の効率化と目標達成を実現します。
PDCAサイクルを回すことで、組織全体の目標意識が高まり、継続的な改善活動が促進されます。これにより、経営効率の向上と目標達成率のアップが期待できるでしょう。
予実管理を行うことによるメリット
予実管理は、企業経営における重要な管理手法として広く活用されています。予算と実績を定期的に比較・分析することで、経営状況の可視化や迅速な意思決定が可能となり、組織全体の業績向上に大きく貢献します。本稿では、予実管理を導入・運用することによって得られる4つの主要なメリットについて、具体的な効果とともに解説していきます。
経営状況の可視化
予実管理を導入することで、企業の経営状況を正確に把握することができます。
まず、予算と実績の差異を定期的に比較・分析することで、計画通りに事業が進捗しているのかを確認できます。予算と実績の乖離が大きい場合は、その原因を突き止め、早期に対策を講じることが可能になります。
また、部門別の予算管理を行うことで、どの部門の業績が芳しくないのかが一目瞭然となります。問題のある部門を特定し、集中的に改善策を実施することで、企業全体のパフォーマンス向上につなげられるでしょう。
経営判断の迅速化
予実管理のもう一つの大きな効果が、経営判断のスピードアップです。
予算と実績を比較することで、目標達成に向けた進捗状況をリアルタイムで確認できます。計画と実際の数字に大きな乖離がある場合は、すぐさま経営陣に報告し、対策を検討・実行に移すことができるのです。
機敏な経営判断を下すためには、正確なデータに基づく冷静な分析が不可欠です。予実管理を適切に運用することで、スピーディーかつ的確な意思決定が可能となります。
部門間コミュニケーションの活性化
予実管理の導入は、部門間のコミュニケーション促進にも一役買います。
予算策定の段階から、各部門の担当者が集まって議論を交わすことになります。目標達成に向けて部門の垣根を越えた建設的な意見交換が行われ、社内の一体感が醸成されていくのです。
また、予算と実績の差異が生じた際も、関連部門が連携して原因究明と対策立案に当たります。問題解決のために部門の枠組みを超えて協力し合う経験は、組織力の強化につながるでしょう。
予実管理を成功させるためのポイント
予実管理を円滑に進め、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントに注意を払う必要があります。
ここでは、予実管理を成功に導くための4つの鍵となる要素について解説していきましょう。
適切な予算設定
予実管理の出発点となるのが、適切な予算設定です。会社の経営目標や事業計画に基づき、現実的かつ達成可能な目標値を設定することが求められます。
予算設定の際は、過去の実績データを参考にしつつ、市場動向や経済環境の変化も考慮に入れることが重要でしょう。また、部門ごとの予算を詳細に設定し、全社的な目標との整合性を図ることも欠かせません。
迅速な実績把握と差異分析
予算と実績の乖離を早期に発見し、その原因を突き止めることは、予実管理の核心部分といえます。実績データを迅速かつ正確に収集・集計する仕組みを整えることが肝要です。
差異が生じた場合は、その要因を詳細に分析し、改善策を講じる必要があります。特に、売上高や利益率など、経営に直結する指標の変動には十分な注意を払いましょう。
全社的な取り組み体制の構築
予実管理を効果的に機能させるためには、経営層から現場の従業員に至るまで、組織全体で取り組む体制を構築することが不可欠です。
トップのリーダーシップの下、各部門の責任者が主体的に予実管理に関与し、PDCAサイクルを回していく必要があります。定期的な会議や報告会を通じて、情報共有と課題解決を図ることも重要でしょう。
予実管理を支援するシステムの活用
昨今では、予実管理業務を支援する様々なITツールが登場しています。表計算ソフトによる管理から脱却し、専用のシステムを導入することで、作業の効率化と精度向上が期待できます。
クラウド型のシステムを活用すれば、リアルタイムでのデータ共有も可能です。経営判断の迅速化や、部門間連携の強化にもつながるでしょう。適切なシステム選定と運用体制の整備が、予実管理の成否を左右するといっても過言ではありません。DXの導入による予実管理の即時化、効率化も検討するとよいと言えるでしょう。
予実管理の課題
予実管理は企業経営に欠かせない手法ですが、実施する上でいくつかの課題があります。ここでは、予実管理を行う際に直面しやすい主要な課題について取り上げます。
予算設定の難しさ
予実管理の第一歩は、適切な予算設定です。しかし、現実的かつ達成可能な予算を設定するのは容易ではありません。
予算設定の難しさの理由は、将来の不確実性が高いことにあります。市場動向や経済状況の変化を正確に予測することは困難であり、予算設定時には一定の仮定に基づかざるを得ません。また、過去のデータを基にした予測は、環境変化に対応しきれない可能性があります。
加えて、予算設定には各部門の協力が不可欠ですが、部門間の調整が難航するケースもあります。売上目標と費用予算のバランスを取ることが難しく、現実的な予算設定に時間がかかってしまうのです。
実績データ収集の手間
予実管理を行うには、予算と実績を比較するための正確なデータ収集が欠かせません。ところが、実績データの収集・集計には多大な手間がかかります。
特に、複数の部門やシステムに散在するデータを統合するのは容易ではありません。手作業でのデータ収集は、ミスが生じるリスクも高く、時間もかかってしまいます。また、データの粒度や定義があいまいだと、部門間で食い違いが生じ、正確な実績把握ができなくなります。
さらに、リアルタイムでのデータ収集が難しいため、タイムリーな予実管理ができないという問題もあります。月次や四半期ごとの実績把握では、機敏な経営判断に繋げることが難しくなってしまうのです。
形骸化に陥るリスク
予実管理を導入しても、運用が形骸化してしまうリスクがあります。当初は適切に運用されていても、時間の経過とともに形式的なものになってしまうことがあるのです。
その原因の1つは、予実差異の分析が表面的になることです。単に数字の差異を確認するだけでは不十分で、差異が生じた要因を掘り下げて分析する必要があります。しかし、踏み込んだ分析には時間と労力がかかるため、省略されがちなのです。
また、予実管理の結果を改善に活かせていないケースもあります。課題が明らかになっても、具体的な対策が打ち出せなかったり、対策が実行されなかったりすることがあるのです。PDCAサイクルが回らないと、予実管理は有名無実化してしまいます。
まとめ
本記事では、予実管理の概要から具体的な運用方法までを解説してきました。予実管理は、予算と実績の差異を定期的に把握・分析し、経営目標達成に向けた進捗状況を管理する重要な手法といえます。
適切な予算設定と実績データの収集、そして差異要因の深掘りが予実管理の鍵となります。PDCAサイクルを回しながら、組織全体で改善に取り組むことが求められるでしょう。
予実管理の定着には課題も多いですが、システム活用などの工夫により克服は可能です。今後ますます不確実性が高まるビジネス環境では、予実管理によるスピーディーな経営判断が欠かせません。
中小企業の皆様におかれましては、ぜひ予実管理の重要性をご認識いただき、自社の体制構築に役立てていただければと思います。経営目標の着実な達成に向け、予実管理を有効に活用していきましょう。
最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン
急な受注や支払いが重なって、早急な資金調達が必要になったときに便利なのがビジネスローンです。
HTファイナンスでは、スピードと柔軟性を重視した独自の審査体制を整え、より早く経営者の皆様へ資金をご提供できるよう努めています。
必要書類もシンプルなので、準備に時間をかけることなくお申し込みいただけます。
また、オンラインやお電話でのやり取りを中心に契約まで進められるので、来店の手間を軽減できるのもポイントです。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずは一度HTファイナンスの借入枠診断をお試しください。