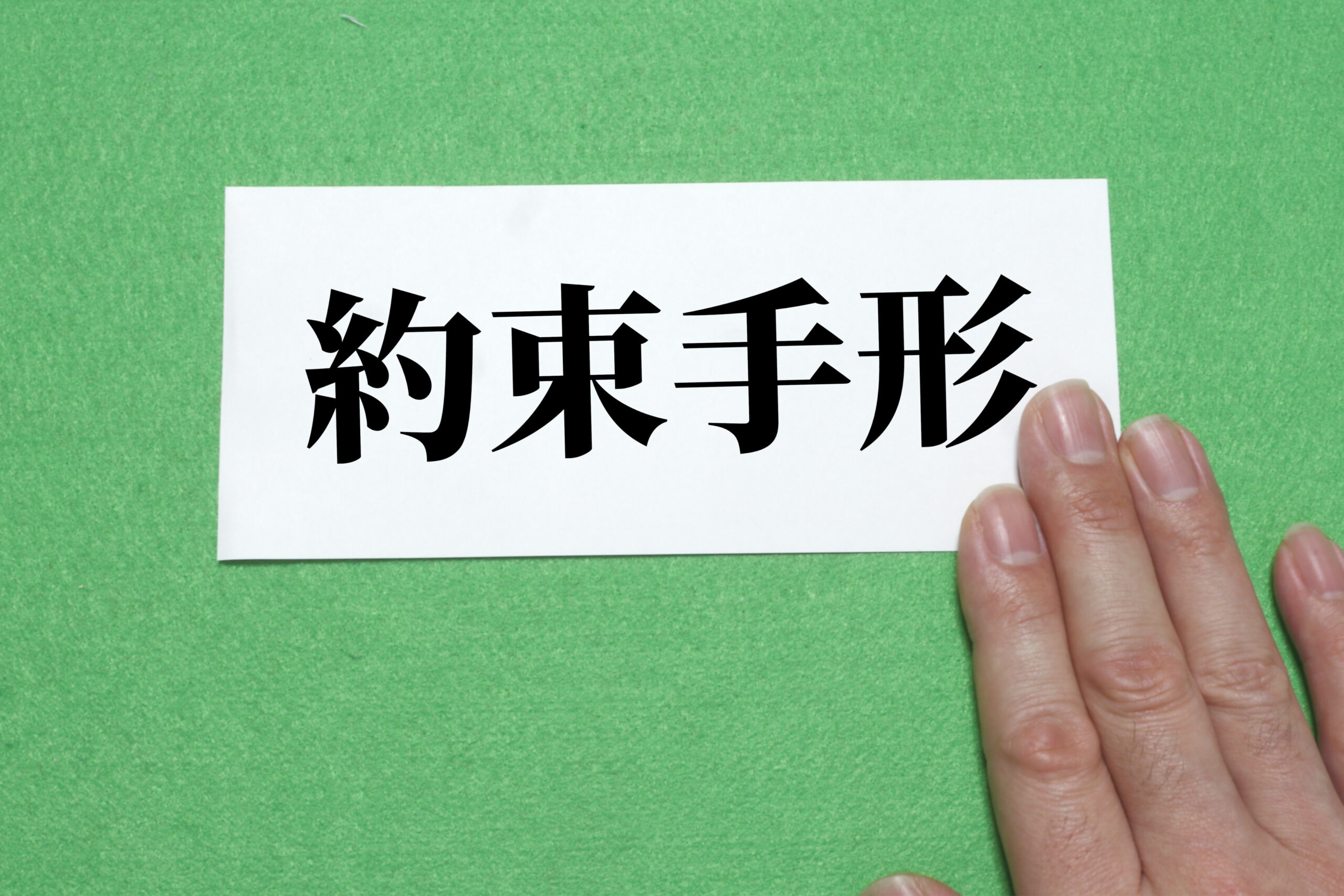2025.01.22
約束手形の基本とは?役割と使い方を解説
企業間取引では、現金決済以外の支払手段の活用が重要ですが、中でも約束手形の役割は大きいといえます。約束手形を上手に利用することで、取引先との信用関係を築きつつ、資金繰りの柔軟性を高められるからです。しかし、約束手形の仕組みや注意点を正しく理解していないと、不渡りなどのトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
この記事では、約束手形の基本的な意味合いから、具体的な利用方法、他の支払手段との比較、会計処理や法改正の動向まで、実務に役立つ情報を幅広く解説します。
約束手形とは
約束手形は、企業間取引における重要な決済手段の一つです。ここでは、約束手形とは何か、そして約束手形の役割について説明していきましょう。
約束手形の役割
約束手形とは、将来の確実な支払いを約束する証書のことをいいます。振出人(支払いを約束する側)が、受取人(支払いを受ける側)に対して、指定された支払期日に一定金額を支払うことを約束する法的な書類です。
約束手形の主な役割は、企業間の信用取引を円滑に行うことにあります。売掛金の回収や買掛金の支払いに利用されることで、現金決済の必要性を減らし、資金繰りの効率化に貢献します。また、手形の裏書譲渡によって、債権の流動性を高めることもできます。
約束手形の基本的な仕組み
約束手形の取引には、以下のような基本的な流れがあります。
- 振出人が当座預金口座を開設する
- 振出人が手形用紙に必要事項を記入し、受取人に交付する
- 受取人が手形を保有、または銀行にて割り引く(必要に応じて現金化する)
- 受取人が支払期日が近づいた段階で取立依頼を取引銀行に行う
- 取引銀行からの取り立てにより手形交換所で手形の処理が行われる
- 最終的な資金決済が完了する
この一連の流れにおいて、振出人と受取人の間で手形が授受され、支払期日に確実な決済が行われる仕組みになっています。手形の必要条件として、当座預金口座の開設と収入印紙の貼付が求められます。
約束手形の法的位置づけ
約束手形は、手形法によって規定された有価証券の一種です。法的な効力を持ち、支払いの確実性を担保する重要な書類として扱われています。
約束手形の不渡り(支払い不能)が発生した場合、振出人は銀行取引停止処分を受けるなど、厳しい法的制裁の対象となります。半年以内に2回の不渡りが発生すると、金融取引に大きな制限が課せられるリスクがあります。
約束手形取引の関係者
約束手形の取引には、主に以下の関係者が存在します。
- 振出人:手形の支払いを約束する側の企業や個人
- 受取人:手形の支払いを受ける側の企業や個人
- 取引銀行:当座預金口座の開設や手形の取立てを行う金融機関
- 手形交換所:手形の交換や決済を行う機関
これらの関係者が連携することで、約束手形による決済が円滑に行われています。特に、取引銀行は手形取引のインフラを提供する重要な役割を担っているといえます。
約束手形と他の支払手段との比較
約束手形は、企業間取引において重要な役割を果たしてきた支払手段の一つです。ここでは、約束手形の主要な特徴を解説し、他の支払手段との比較を通じて、その性質をより深く理解していきましょう。
約束手形と小切手の違い
約束手形と小切手の大きな違いは、現金化のタイミングにあります。約束手形は支払期日以降に現金化されるのに対し、小切手は受け取った時点で即時に現金化が可能です。
つまり、約束手形は将来の支払いを約束するものであり、小切手は即時の支払いを指示するものといえます。この違いを理解することで、取引の性質に応じて適切な支払手段を選択できるでしょう。先日付小切手が約束手形に代用される場合がありますが、小切手
は先日付であっても一覧払(即時支払)になりますので、期日支払の効果はありません。
約束手形と為替手形の違い
約束手形と為替手形の違いは、取引関係者の数にあります。約束手形が振出人と受取人の二者間で取り交わされるのに対し、為替手形は振出人、受取人、支払人の三者間で取り交わされます。
為替手形では、振出人が支払人に対して受取人への支払いを指図するという構造になっています。
約束手形の利用方法と手続き
約束手形は企業間取引での支払い手段として広く利用されてきました。ここでは約束手形の基本的な仕組みや手続きについて、振出から決済までの流れを解説します。
約束手形の基本的な利用方法
約束手形は、将来の確実な支払いを約束する証書です。振出人が受取人に対して、指定された支払期日に一定金額を支払うことを約束するものといえます。
約束手形を利用するには、まず当座預金口座を開設する必要があります。次に、手形用紙に必要事項を記入し、収入印紙を貼付して受取人に交付します。支払期日は最大で120日先まで設定可能ですが、政府要請では60日以内とされています。中小企業庁では手形の支払期日を最大60日とする方針を
打ち出しており、2024年11月以降、60日を超える約束手形発行による一括支払いは、行政
指導の対象になりました。
受取人は、支払期日までに振出人から入金を受けることで、約束手形の債権を確実なものにします。支払期日が到来したら、取引銀行に取立依頼を行い、手形交換所での処理を経て最終的な資金決済が行われます。
約束手形の振出と受取の手続き
約束手形の振出と受取には、一定の手続きが必要となります。まずは、振出人と受取人がそれぞれ当座預金口座を開設しておく必要があります。
振出人は、手形用紙に必要事項を記入し、収入印紙を貼付します。必要事項には、受取人名、支払金額、支払期日、振出日などが含まれます。記入と印紙貼付が完了したら、受取人に手形を交付します。
受取人は、交付された手形を受け取ったら、内容を確認します。手形の記載事項に不備がないか、印紙が適切に貼付されているかなどを確認することが重要です。問題がなければ、手形を受け取り、支払期日までに振出人から入金を受けるのを待ちます。
約束手形の裏書譲渡と割引
約束手形は、裏書譲渡によって第三者への支払いに利用することができます。受取人が手形の裏面に署名することで、手形の権利を別の者に譲渡するのです。
また、約束手形は割引によって支払期日前に現金化することも可能です。手形割引とは、金融機関が受取人から手形を買い取り、支払期日までの利息を差し引いた金額を受取人に支払うことをいいます。受取人は早期に資金を得ることができ、金融機関は利息収入を得ることができます。
ただし、裏書譲渡や割引を行う場合は、手形の信用力や振出人の支払能力などを十分に検討する必要があります。不渡りリスクを適切に管理することが求められるでしょう。
約束手形の取立と決済の流れ
約束手形の支払期日が到来したら、受取人は取立依頼を行います。通常は受取人の取引銀行に手形を持ち込み、取立を依頼します。
銀行は手形交換所に持ち込まれた手形の処理を行います。手形交換所では、持ち込まれた手形と支払銀行からの情報を照合し、不渡りがないかを確認します。問題がなければ、受取人の口座に支払金額が入金され、振出人の口座から引き落とされます。
こうして、約束手形の取立と決済の一連の流れが完了します。振出人と受取人の間で確実な支払いが実行されたことになります。手形取引の重要性を理解し、適切な手続きを踏むことが求められるでしょう。
約束手形のメリットとリスク
約束手形は、取引先との信用取引を円滑に進める上で欠かせない支払手段の一つです。ここでは、約束手形を利用することのメリットとリスクについて詳しく見ていきましょう。
約束手形を利用するメリット
約束手形を利用することで、取引先との信用関係を構築し、円滑な取引を行うことができます。手形という形で支払いを約束することで、取引先からの信頼を得ることにつながるでしょう。
また、約束手形は支払期日まで一定の猶予期間があるため、資金繰りの調整がしやすいというメリットがあります。手元資金が不足している場合でも、支払期日までに資金を準備することで、取引を継続することが可能です。
さらに、約束手形は裏書譲渡や手形割引といった方法で、支払期日前に現金化することもできます。これにより、資金調達の選択肢が広がり、柔軟な資金運用が可能になります。
約束手形を利用するリスク
一方で、約束手形の利用にはリスクも存在します。最大のリスクは、手形の不渡りが発生することです。振出人の資金不足などにより、支払期日までに支払いができない場合、手形は不渡りとなります。
不渡りが発生すると、振出人は銀行取引停止処分を受け、金融取引に制限がかかるなど、事業活動に大きな影響を及ぼします。また、不渡りが連続して発生した場合、信用失墜につながり、取引先との関係悪化を招く可能性があります。
また、約束手形の利用には、収入印紙の貼付や手形用紙の作成など、一定のコストがかかります。手形の管理や会計処理にも手間がかかるため、事務負担の増加というデメリットがあります。
約束手形に関する重要事項
ここでは、約束手形の会計処理や法改正、電子化への移行など、約束手形を用いるにあたって知っておくべき事柄について解説します。
約束手形の会計処理
約束手形の会計処理は、受取時と振出時で異なります。それぞれの仕訳方法について説明しましょう。
約束手形を受け取った際の仕訳は、以下のようになります。
| 借方 | 受取手形 |
|---|---|
| 貸方 | 売掛金 |
一方、約束手形を振り出す際の仕訳は次のようになります。
| 借方 | 買掛金 |
|---|---|
| 貸方 | 支払手形 |
このように、約束手形の受取と振出では、仕訳の勘定科目が異なることがポイントです。適切な会計処理を行うためには、取引内容を正確に把握し、仕訳を行う必要があるでしょう。
約束手形に関する法改正
2020年6月、政府は約束手形の利用廃止に向けた方針を打ち出しました。具体的には、2026年までに約束手形の利用を原則廃止するという目標が設定されています。
この方針の背景には、約束手形の利用に伴う課題が挙げられます。例えば、手形の不渡りリスクや、手形管理に伴う事務負担などです。電子決済の普及により、より効率的な資金決済手段への移行が求められているともいえるでしょう。
ただし、約束手形の利用は根強く残っているのが実情です。2021年時点でも、1日あたり約14万枚、金額にして約4,852億円の約束手形が取引されています。法改正や政府方針の影響を受けつつも、当面は約束手形の利用が継続されると見込まれます。
約束手形の電子化の展望
約束手形の電子化とは、紙の手形を電子的なデータに置き換えることを指します。電子手形の導入により、以下のようなメリットが期待できます。
- 印紙税の節約
- 手形管理の効率化
- 不渡りリスクの低減
- 決済のスピードアップ
現在、一部の金融機関で電子手形のサービスが提供されています。しかし、普及率はまだ低く、紙の手形が主流となっているのが実情です。
政府は、2026年までの約束手形廃止の方針と合わせて、電子手形の普及を促進する方針を示しています。今後、法整備や企業の意識改革が進めば、電子手形の利用が加速していくことが予想されます。ただし、電子化への移行には一定の時間を要するため、当面は紙の手形と電子手形が併存していく見通しです。
まとめ
本記事では、約束手形の基本的な意味や仕組みから、具体的な利用方法、会計処理、法改正の動向まで幅広く解説してきました。約束手形は将来の確実な支払いを約束する重要な証書であり、取引先との信用関係の構築に役立ちます。
約束手形のメリットを活かし、円滑な企業間取引の実現につなげていただければと思います。