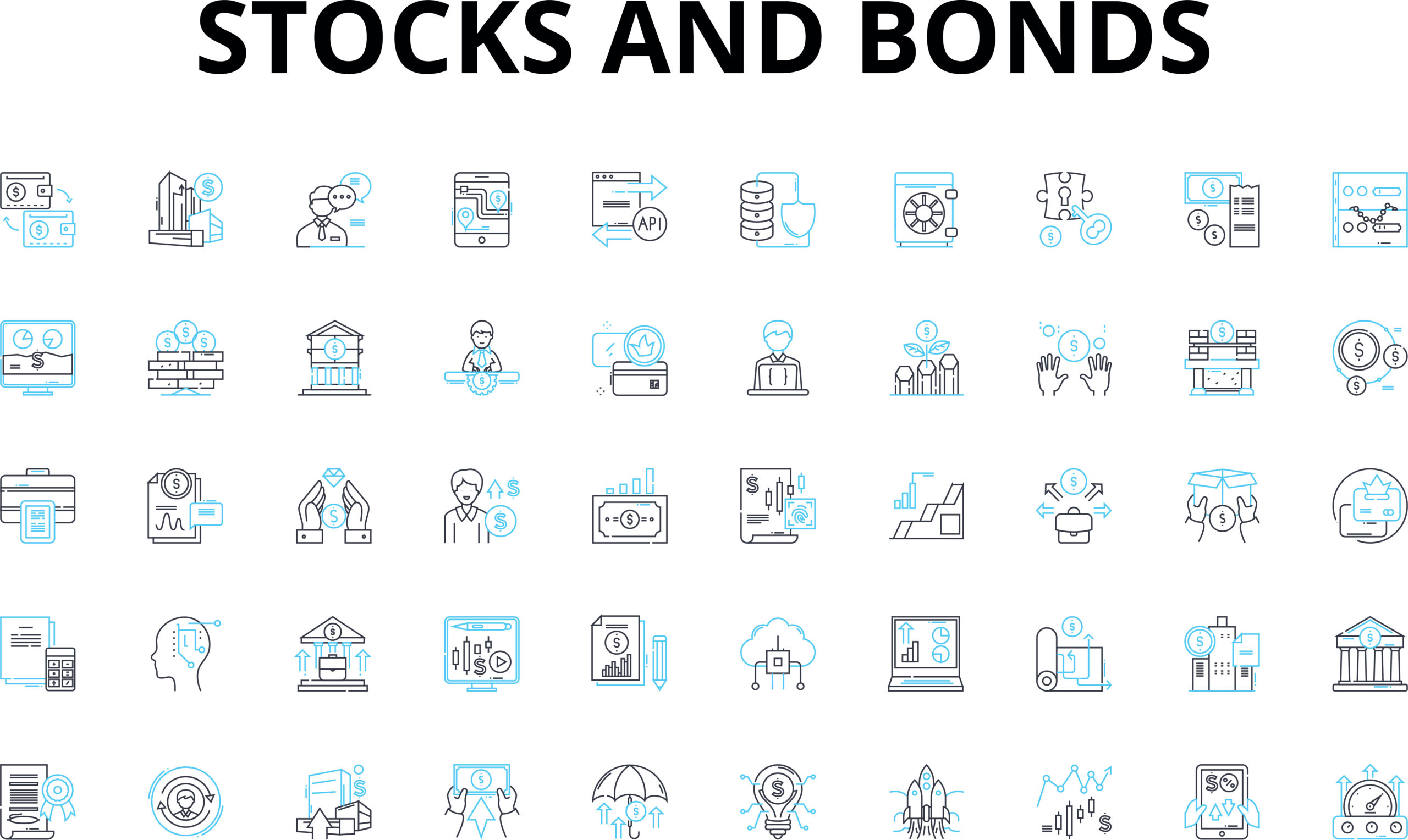2025.01.29
営業利益と経常利益の違い!経営指標の基本を解説
営業利益と経常利益は企業の収益性を示す重要な指標ですが、その違いを正しく理解している経営者は多くありません。本業の儲けを表す営業利益と、それに営業外損益を加味した経常利益では、企業の財務状況の見え方が大きく変わります。この記事では、営業利益と経常利益の違いから、それぞれの利益が企業経営において果たす役割までを詳しく解説します。
営業利益と経常利益の違い
企業の財務状況を把握するうえで大切になる営業利益と経常利益のそれぞれの利益の定義と計算方法、そして両者の違いについて解説します。
営業利益とは
営業利益とは、企業の本業での事業活動から得られる利益のことをいいます。具体的には、売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を差し引いた金額が営業利益となります。
計算式は以下の通りです。
営業利益 = 売上高 – (売上原価 + 販売費及び一般管理費)
経常利益とは
一方、経常利益は、営業利益に営業外損益を加減した利益のことを指します。営業外損益には、受取利息や支払利息、為替差損益などが含まれます。
経常利益の計算式は次の通りです。
経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 – 営業外費用
経常利益は、企業の総合的な収益力を表す指標と考えられています。本業以外の活動も含めた企業全体の儲けを示しているといえるでしょう。
営業利益と経常利益が示す企業の収益性
企業の収益性を評価する上で、営業利益と経常利益は重要な指標です。この2つの利益の示す内容を理解することで、企業の本業の収益力や総合的な収益力を正しく分析することができます。
営業利益から見る本業の収益力
営業利益は、企業の本業における収益力を示す指標です。
営業利益の推移を確認することで、企業の本業の収益力が向上しているのか、低下しているのかを判断できます。また、売上総利益率(粗利)と比較することで、販売費及び一般管理費(販管費)の適正性を評価することもできるでしょう。
経常利益から見る総合的な収益力
経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いて算出されます。つまり、経常利益は企業の総合的な収益力を示す指標といえます。
経常利益の水準や推移を分析することで、企業の財務体質の健全性を評価できます。また、売上高経常利益率を計算し、同業他社と比較することで、企業の収益力の相対的な位置づけを把握することもできるでしょう。
営業利益と経常利益の差額
営業利益と経常利益の差額は、営業外損益の影響を表しています。この差額が大きい場合、企業の収益力が営業外の要因に大きく左右されていることを意味します。
営業外損益には、金融収支に関わるものが多く含まれています。例えば、受取利息や受取配当金などは営業外収益に、支払利息や社債利息などは営業外費用に計上されます。
また、為替差損益のように、外貨建ての取引に伴って発生する損益も営業外損益に含まれるのが一般的です。
営業外損益の内訳を詳しく分析することで、企業の収益構造の特徴や潜在的なリスクを把握することができるでしょう。例えば、為替差損が多額に発生している場合は、為替リスクへの対策が必要である可能性があります。
営業利益と経常利益を利用した分析
営業利益と経常利益は、企業の収益性を評価する上で重要な指標です。ここでは、営業利益と経常利益を利用した経営状況の分析方法について解説していきましょう。
営業利益と経常利益の比較
営業利益と経常利益の差額を計算することで、利益の安定性を評価できます。両者の差が小さい企業は、営業外損益の影響が少なく、安定的な利益を確保しているといえるでしょう。
一方、差額が大きい場合は、営業外損益の内容を詳しく見る必要があります。例えば、為替差損や支払利息などの営業外費用が大きい場合、為替レートや金利変動の影響を受けやすく、利益が不安定になるリスクがあります。
営業外損益の内訳
経常利益は、営業利益に営業外損益を加減して算出されますので、営業外損益は、本業以外の活動から生じる収益や費用で、企業の財務体質を反映しています。
営業外損益の内訳を分析することで、企業の財務リスクや収益源の多様性を評価することができます。例えば、営業外収益の中で受取利息や配当金の割合が高い場合は、投資活動が活発であることが分かります。一方、営業外費用の中で支払利息の割合が高い場合は、借入金への依存度が高いことを示唆しています。
営業利益と売上総利益の比較
営業利益と売上総利益は、密接に関連しています。売上総利益は、売上高から売上原価を差し引いた値で、企業の基本的な収益力を表します。一方、営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた値で、本業での収益性を示します。
すなわち、両者を比較することで、販売費及び一般管理費の効率性を評価することができます。売上総利益率が高いにもかかわらず、営業利益率が低い場合は、販売費及び一般管理費の削減が必要である可能性があります。
販売費及び一般管理費の評価
販売費及び一般管理費は、営業利益に直接影響を与える重要な費用項目です。この費用の適正性を評価するには、以下の点に着目する必要があります。
- 売上高に対する販売費及び一般管理費の比率(販管費率)
- 各費用項目の前期比較や予算との乖離
- 同業他社との比較
これらの分析を通じて、不必要な支出や効率化の余地がないか確認することが重要です。
特別損益の影響の排除
特別損益は、臨時的かつ多額の収益や費用で、経常的な企業活動とは異なる性質を持っています。例えば、固定資産売却損益や災害損失などが該当します。
特別損益は、一時的な要因であるため、経常的な収益力を評価する際には、特別損益の影響を排除して分析しましょう。特別損益を含めたままでは、企業の本来の収益性を正確に把握することができません。
営業利益と経常利益の経営への活用
営業利益と経常利益は、企業の経営状態を示す重要な指標です。これらの指標は、事業の収益性や効率性を評価するために活用され、経営改善にも役立てることが可能です。
事業計画策定における利益目標
事業計画を立てる際、営業利益と経常利益を目標の一つとして設定することができます。事業の成長や拡大を図るためには、まず本業での収益性を高めることが大切です。
営業利益の目標を設定することで、売上高と費用のバランスを考慮しながら、事業の方向性を定めることができます。また、経常利益の目標を設けることで、営業外の要因も含めた総合的な収益力の向上を目指すことができるでしょう。
投資判断や経営資源配分の意思決定
企業が新たな事業に進出したり、設備投資を行ったりする際には、慎重な判断が求められます。営業利益や経常利益は、そうした意思決定の重要な指標となります。
投資案件の収益性を予測する際、営業利益をベースにした指標である総資本営業利益率などを用いることで、投資効率を評価できます。また、経常利益の予測値を見ることで、投資に伴う資金調達コストの影響も考慮に入れることができるでしょう。
部門別収益管理とコスト管理
企業内の各部門の業績を評価する際にも、営業利益と経常利益は重要な役割を果たします。部門ごとの売上高と費用を把握し、営業利益を算出することで、各部門の収益性を比較・分析できます。(管理会計)
また、部門別の営業利益の目標を設定し、実績との差異を分析することで、コスト管理の適正性を評価することもできます。経常利益を部門別に把握することで、営業外損益の影響も含めた部門業績の評価が可能となるでしょう。
予算実績管理と業績評価
営業利益と経常利益は、予算管理においても重要な指標です。期初に立てた予算と実際の業績を比較することで、事業の進捗状況を把握し、必要な改善策を講じることができます。
また、営業利益率や経常利益率を同業他社と比較することで、自社の業績の相対的な位置づけを理解することもできます。こうした業績評価を通じて、企業の強みと弱みを分析し、事業戦略の立案や見直しにつなげていくことが可能となるでしょう。
同業他社に対する優位性の認識
自社の営業利益率や経常利益率を同業他社と比較することで、自社の強みや弱みを把握することができます。利益率が高ければ、競合他社に対する優位性があると判断できるでしょう。
ただし、単純な数値比較だけでなく、各社の事業規模や事業内容の違いも考慮する必要があります。自社と類似した事業モデルを持つ企業と比較することで、より的確な強み・弱みの分析が可能になります。
まとめ
本記事では、営業利益と経常利益の基本的な違いから、それぞれの利益が企業経営に果たす役割までを解説してきました。営業利益は本業の収益力を、経常利益は企業全体の収益力を示す重要な指標です。
営業利益と経常利益を正しく理解し、有効に活用することが、企業の収益力強化と持続的成長につながります。ぜひ、両指標を活用して経営の改善へと役立てましょう。