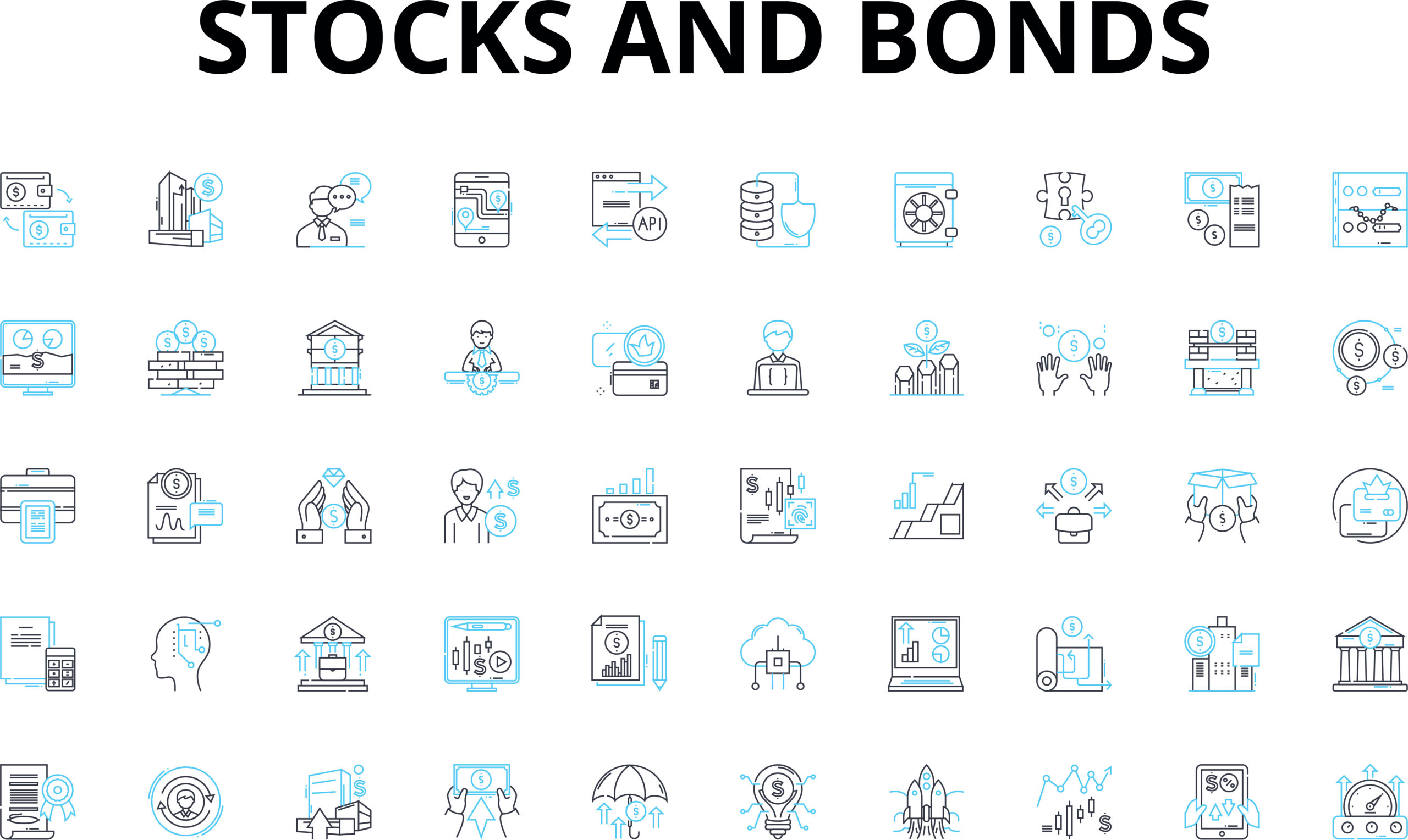2025.01.31
役員貸付金とは?利用する際のデメリットや管理方法まで解説
中小企業の経営者の方は、事業運営に必要な資金を工面するのに頭を悩ませているのではないでしょうか。銀行融資の審査が通らず、資金繰りに窮している中で、役員貸付金という選択肢に目を向ける方も多いかもしれません。しかし、役員貸付金には様々なリスクが潜んでいることをご存知でしょうか。
この記事では、役員貸付金の基本的な仕組みやメリット・注意点について解説し、さらに適切な管理方法や解消のための方策も紹介します。
役員貸付金とは
役員貸付金とは、会社から役員に対して行われる資金の貸付のことをいいます。会社と役員は別の法人格を有しているため、会社から役員への資金の貸付は、あくまでも会社と役員という別法人間での金銭の貸借関係となります。ここでは、役員貸付金の基本的な特徴について解説します。
会計上の位置づけ
役員貸付金は、会社の貸借対照表上、資産の部に計上されます。これは、役員に貸し付けた資金は、いずれ返済されるべきものであり、会社にとっての債権であるためです。
ただし、役員貸付金の回収が見込まれない場合には、貸倒引当金を計上するなどの会計処理が必要となります。回収不能となった場合には、最終的に損失処理を行うことになるでしょう。
役員貸付金の法的要件
役員貸付金には、法律上の要件があります。会社法上、役員に対する金銭の貸付けを行う場合には、原則として市場金利以上の利率で利息を収受する必要があります。無利息や低利での貸付は、役員に対する利益供与とみなされ、違法となる可能性があります。
また、税務上も、役員貸付金には適正な利率での利息計上が求められます。利息収受を行わない場合、役員に対する利益供与として、課税関係が発生する可能性があります。
役員貸付金が発生する要因
役員貸付金が発生する要因は様々ですが、主には、役員個人からの借入要請や、経営者による会社資金の私的流用などがあげられます。また、役員報酬の前払いや、経費精算の際の領収書紛失なども、役員貸付金の発生する原因となり得ます。
特に、オーナー企業や同族会社においては、個人と法人の資金区分があいまいになりがちで、役員貸付金が発生しやすい傾向にあります。内部統制の不備や、株主総会での適切な手続きを経ない資金移動も、役員貸付金を生む温床となるでしょう。
役員貸付金の注意点
役員貸付金の額が少ない場合には、深刻な影響が出る可能性は低いと言えます。しかしながら、役員が清算を先延ばしにして貸付金の残高が膨張すると、主に以下のリスクが生じるでしょう。
会社の手元資金の減少
役員貸付金の最も大きな注意点は、会社の手元資金が減少することです。役員への貸付を行うということは、その分だけ会社の運転資金や投資資金が減ってしまうことを意味します。
特に、中小企業においては資金繰りが厳しいケースが多いため、役員貸付金によって手元資金が減少することは、事業運営に大きな影響を与えかねません。資金が不足すれば、仕入れや設備投資、人件費の支払いなどに支障をきたし、ひいては事業の継続が困難になる可能性もあるでしょう。
また、手元資金が減少することで、急な資金需要に対応できなくなるリスクも高まります。取引先からの突然の注文増加や、自然災害などの緊急事態に備えるためにも、会社は一定の手元資金を確保しておく必要があるのです。
融資審査における不利な評価
金融機関からの融資を受ける際、役員貸付金の存在は大きなマイナス要因となります。融資審査では、会社の財務内容だけでなく、ガバナンス体制が健全であるかも重視されるからです。
さらに役員貸付金の存在は、会社と役員の資金の区分が曖昧であることを示唆しています。このような状況は、会社の内部管理体制の不備を疑わせる材料となり、融資審査における評価を大きく下げる要因となります。
金融機関からすれば、会社の資金が役員に私的に使われているのではないかと、疑いたくなるのです。融資の可否判断だけでなく、金利面でも不利になる可能性が高いでしょう。
社会的信用の低下
役員貸付金の問題は、金融機関からの評価低下だけにとどまりません。取引先や顧客、投資家など、会社を取り巻くステークホルダーからの信頼を失うリスクもはらんでいます。
社会的信用の低下は、ビジネスにも大きな影響を及ぼします。取引先との関係悪化や、顧客離れを招くおそれがあるのです。また、SNSなどを通じて問題が拡散すれば、ブランドイメージの低下は避けられません。結果として、会社の業績不振や株価下落につながるリスクは小さくないでしょう。
加えて、資本市場からの資金調達も困難になります。役員貸付金の存在は投資家の警戒心を招き、社債の発行や増資などによる資金調達のハードルを大きく上げる要因となるのです。
役員貸付金の解消方法
役員貸付金は、会社の財務状況に大きな影響を与える重要な項目ですので、膨れ上がる前に解消するようにしましょう。
すぐ解消するための方法
役員貸付金を即時解消するには、いくつかの方法があります。
まず、役員借入金との相殺が考えられます。役員が会社に対して借入金がある場合、役員貸付金とを相殺することで、両者の債権債務関係を解消することができるでしょう。
次に、役員からの現金回収も有効な手段の一つです。役員に対して貸付金の返済を求め、現金で回収することで、貸付金残高を減らすことが可能です。
また、個人資産の法人への売却も選択肢として挙げられます。役員が所有する不動産や有価証券などを会社に売却し、その代金を貸付金の返済に充てるのです。ただこの方法では、資産の評価額や税務上の取扱いに注意が必要となります。
長期的に解消する方法
即時解消が難しい場合は、長期的な視点で役員貸付金の解消を図ることになります。
役員退職金との相殺は、将来的な債権回収の手段として有効です。役員の退職時に、退職金と貸付金を相殺することで、債権を回収することができます。ただし、退職金の額が貸付金残高を下回る場合は、完全な回収とはなりません。
役員報酬からの返済も考えられるでしょう。毎月の役員報酬から一定額を天引きし、貸付金の返済に充てる方法です。返済期間が長期にわたるため、役員の生活への影響を最小限に抑えられるというメリットがあります。
役員貸付金を扱う際の法律上の注意点
役員貸付金は、会社と役員個人との間の金銭のやり取りであるため、法的・税務的な側面からの慎重な検討が求められます。ここでは、役員貸付金に関連する主要な法的・税務的な考慮事項について解説していきます。
税務上の取り扱い
役員貸付金は、会社の資産として貸借対照表に計上されますが、税務上は適正な利率での利息計上が義務付けられています。会社が役員に対して貸付を行う際は、法定利率以上の利息を設定し、期間に応じて適切に利息を計上する必要があります。
この利息計上を怠ると、税務調査において指摘を受けるリスクがあり、利息相当分が役員賞与として扱われ、法人税と所得税の課税対象となりかねません。
未回収時の役員賞与認定
役員貸付金が長期間にわたって未回収の状態が続くと、税務当局からは役員に対する賞与とみなされ、損金不算入となるリスクがあります。この「役員賞与認定」を避けるためには、適切な返済計画を策定し、確実に回収を進めることが重要です。
万一、返済が滞る場合には、合理的な理由を示す証憑を保存しておくとともに、税理士等の専門家に相談し、適切な対応方針を決定することをおすすめします。
債権放棄時の課税
会社が役員貸付金を債権放棄した場合、その放棄額は会社にとって損失となりますが、一定の要件を満たさない限り、税務上は損金として認められません。逆に、役員側では債務免除益として課税対象となります。
このように、安易な債権放棄は会社と役員の双方に税務上の負担を強いる結果となりかねません。債権放棄を検討する際は、事前に税理士等の専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが大切です。
相続財産としての扱い
役員が死亡した場合、役員貸付金は相続財産の一部として扱われ、相続税の課税対象となります。相続人は、被相続人である役員の債務を引き継ぐことになるため、円滑な相続手続きのためにも、生前から役員貸付金の適切な管理と返済が求められます。
また、相続の際に役員貸付金の精算が行われる場合は、相続税の申告において適切に処理する必要があります。相続財産の評価や申告手続きについては、税理士等の専門家と連携しながら進めましょう。
役員貸付金の適切な管理方法
注意点の大きい役員貸付金は、できるだけ少額に抑えることが大切になります。そのためには、適切な管理体制を整えることが必要でしょう。
内部統制の強化
役員貸付金の濫用が起こらないようにするにはまず、個人と法人の資金を明確に区分する仕組み作りが重要となります。
また、役員貸付金に関する文書の管理体制を構築し、定期的なモニタリングを実施することで、不適切な貸付けを未然に防ぐことができるでしょう。こうした内部統制の強化により、会社の財務の健全性を保つことが可能になります。
返済計画を遵守させる
役員貸付金を適切に管理するためには、いくつかの方法が有効です。まず、役員との間で金銭消費貸借契約を締結し、貸付条件を明確にしておくことが重要でしょう。
次に、役員貸付金の返済計画を策定し、計画的な回収を図ることが必要です。定期的な残高確認を行うことで、貸付金の状況を正確に把握し、必要に応じて適切な対応を取ることができます。
発生時の即時記録
役員貸付金が発生した際には、なるべくすぐに記録を残しましょう。貸付けの理由や金額、返済予定日などを明確に記録し、適切な利息計算と計上を行うことが求められます。
発生時に適切な処理を行うことで、不要なトラブルを回避することができるでしょう。
定期的な清算
役員貸付金の管理において、定期的な残高確認と清算は欠かせません。月次や四半期ごとに貸付金の残高を確認し、返済状況をチェックすることが重要です。
返済が滞っている場合には、早期に役員との協議を行い、解決策を探ることが必要でしょう。役員貸付金の長期化は、会社の財務状態に悪影響を及ぼす可能性があるため、適切なタイミングで清算しましょう。
まとめ
本記事では、役員貸付金の注意点、適切な管理の仕方や解消方法までを詳しく解説してきました。役員貸付金を利用することは、会社の手元資金の減少や税務上のリスクなど、様々な注意点が存在します。
役員貸付金の問題に直面している経営者の方は、リスクを最小限に抑えつつ、確実に解消を図っていくことが求められます。自社の状況に合った対応を取り、役員貸付金を適切に管理・解消していきましょう。