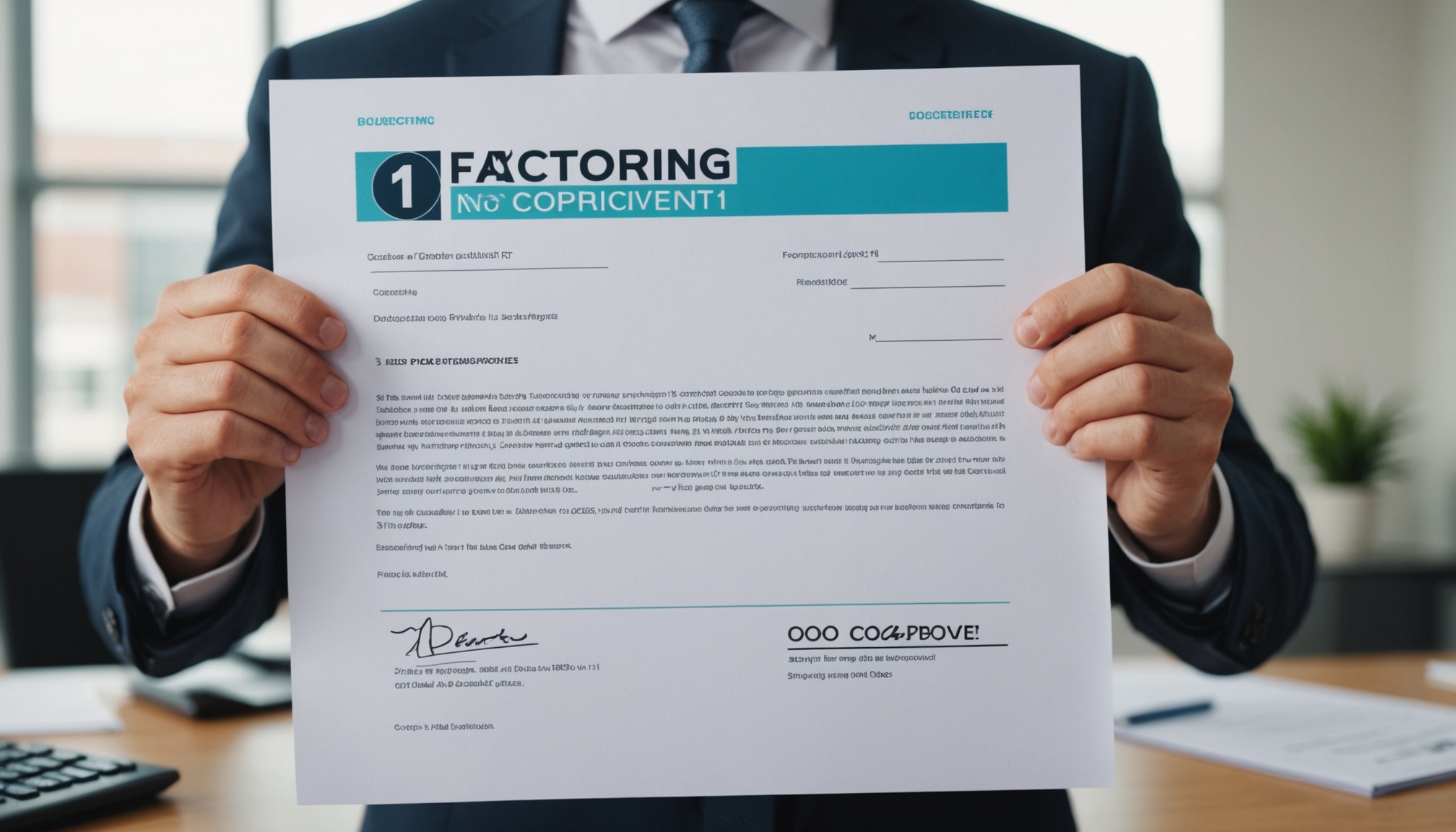2025.01.29
年末調整と確定申告の違いとは?それぞれの特徴を解説
年末調整と確定申告は、どちらも所得税の精算手続きという点では共通していますが、手続きの方法や対象者が異なります。年末調整は会社員の多くが経験する手続きですが、実は年末調整後でも確定申告が必要となるケースがいくつかあります。
この記事では、年末調整と確定申告の基本的な違いを解説した上で、年末調整後に確定申告が必要になる具体的なケースを見ていきます。医療費控除や住宅ローン控除など、確定申告でしか受けられない控除もあわせて紹介します。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、どちらも所得税の計算・納付に関する重要な手続きです。しかし、その対象者や手続き方法には大きな違いがあります。
ここでは、年末調整と確定申告の基本的な違いについて、概要や対象者、手続き期間、手続き方法の面から解説していきます。
年末調整とは
年末調整とは、会社が従業員(給与所得者)に代わって行う所得税の精算手続きです。1年間で支払った所得税の過不足を調整し、過払い分は従業員に返還、不足分は徴収します。
年末調整の対象者は、主に会社員、アルバイト、パートタイム労働者など、給与収入が2,000万円以下の人です。複数の会社から給与を受けている場合でも、合計額が2,000万円以下であれば年末調整の対象となります。
確定申告とは
確定申告は、個人が自ら1年間の所得税額を計算し、申告・納付する手続きです。事業所得や不動産所得、一定額以上の給与所得など、様々な所得が対象となります。
確定申告が必要な主な対象者は、個人事業主、フリーランス、副業で一定以上の所得がある会社員などです。年末調整後でも、給与所得以外の所得が20万円を超える場合や、2ヶ所以上から給与を受けていて年末調整を受けていない給与が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
手続き期間の違い
年末調整の手続き期間は、原則として毎年12月に会社が定める期間です。従業員は、この期間内に必要書類を会社に提出します。
一方、確定申告の手続き期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。ただし、土日祝日の関係で多少前後することがあります。確定申告は、この期間内に税務署や市区町村役場に申告書を提出するか、国税庁のe-Taxを利用してオンラインで申告します。
手続き方法の違い
年末調整の手続きは、従業員が会社に必要書類を提出するだけで完了します。必要書類には、扶養控除等申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書などがあります。会社がこれらの書類をもとに所得税額を計算し、精算します。
確定申告の手続きは、納税者本人が行います。申告書に必要事項を記入し、収入や控除の根拠となる書類を添付して提出します。医療費控除や寄附金控除など、年末調整では適用できない控除を受けることができるのが確定申告の大きな特徴です。
年末調整後でも確定申告が必要なケース
年末調整は、会社員の多くが経験する一年に一度の重要な手続きです。給与所得者の所得税を精算するためのものですが、実は年末調整を済ませた後でも、確定申告が必要なケースがいくつかあることをご存知でしょうか。
ここでは、年末調整後に確定申告が必要となる代表的なケースを見ていきましょう。
給与所得以外の所得が一定額を超える場合
会社員の方でも、給与以外に副業などで収入を得ている場合は注意が必要です。給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要となります。
例えば、不動産収入や株式の配当金、個人事業の収入などが該当します。これらの所得が20万円を超えた場合、確定申告をして正しく税金を納める必要があるのです。
2ヶ所以上から給与を受けている場合
複数の会社から給与を受けている場合も、確定申告が必要になることがあります。
もし、年末調整を受けていない給与が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。複数の会社で働いている方は、年末調整の対象となっていない給与にも注意を払う必要があります。
年間給与収入が2,000万円を超える場合
年間の給与収入が2,000万円を超える高額所得者の場合、年末調整の対象外となります。この場合は、確定申告を行って所得税を納める必要があります。
高額所得者の方は、年末調整に頼らず、自ら税金の計算と申告を行う必要があるのです。
年末調整では申告できない控除を受ける場合
医療費控除や寄附金控除など、年末調整では申告できない控除を受ける場合も、確定申告が必要となります。
例えば、多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税が還付される可能性があります。控除を最大限に活用するためにも、確定申告は重要な手続きといえるでしょう。
確定申告で受けられる主な控除
確定申告を適切に行うことで、様々な控除を適当して税負担を軽減できる可能性があります。ここでは、確定申告で受けられる主な控除について解説していきます。
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用できる控除です。控除を受けるには、年間の医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えていることが条件となります。
控除額の計算方法は以下の通りです。
- 支払った医療費の合計 - 保険金などで補填された金額 - 10万円(または総所得金額等の5%)
寄附金控除(ふるさと納税含む)
寄附金控除は、特定の団体に寄付をした場合に適用できる控除です。ふるさと納税もこの控除の対象となります。
控除額は、以下の計算式で求められます。
- 寄附金の合計額 - 2,000円
ただし、控除額には一定の上限があり、所得金額に応じて計算方法が異なりますので注意が必要です。
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難、横領などによって生じた損失に対して適用できる控除です。
適用の条件は以下の通りです。
- 災害や盗難、横領などの被害を受けたこと
- 損失額が総所得金額等の10%を超えていること
- 保険金や損害賠償金などで補填されていないこと
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅の取得やリフォームなどで一定の要件を満たした場合に適用できる控除です。控除を受けるには、初年度は必ず確定申告が必要となります。
2年目以降は、年末調整で控除を受けることができますが、初年度の確定申告を忘れずに行うことが大切です。
副業や転職・退職時の確定申告
副業や転職、退職時には年末調整ではなく確定申告が必要となる場合があります。ここでは、そうしたケースにおける確定申告の必要性と注意点について解説します。
副業所得が一定額を超える場合の申告義務
会社員で年末調整を済ませている人でも、副業による所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。この申告義務は、本業の給与所得と副業所得を合算して判定します。
副業所得には、アルバイトやパート、フリーランスの報酬、不動産収入などが含まれます。これらの所得が一定額を超えた場合、確定申告により正しく納税する必要があるのです。
副業所得の申告を怠ると、延滞税や加算税が課される可能性があります。副業を行っている人は、必ず収入を記録し、申告義務の有無を確認しましょう。
転職や退職後に再就職しない場合の確定申告
転職や退職をした年に、年末まで再就職しなかった場合も確定申告が必要です。これは、年末調整が行われないためです。
年の途中で退職し、その年に再就職しなかった人は、退職前の勤務先から受け取った源泉徴収票を基に確定申告を行います。この際、退職所得の扱いにも注意が必要です。
転職や退職後に再就職しない場合は、確定申告の必要性を忘れずに確認しましょう。正しく申告を行わないと、税務上のトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
退職金に関する申告書未提出時の課税と還付
退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金から一律20.42%の税金が差し引かれます。この税率は、本来の税額より高い可能性があります。
申告書を提出していない人は、確定申告を行うことで差額分の還付を受けられます。還付申告は、退職金を受け取った年の翌年から5年以内に行う必要があります。
退職金に関する申告書の提出を忘れた場合でも、確定申告による還付の機会があることを覚えておきましょう。適切な手続きを行えば、納め過ぎた税金を取り戻すことができるのです。
確定申告を効率的に行うためのポイント
確定申告をスムーズに進めるには、事前の準備と計画的な取り組みが欠かせません。ここでは、確定申告を効率的に行うための主なポイントを解説します。
確定申告に必要な書類の準備
確定申告を行う上で、必要書類の準備は最も重要な作業の1つです。源泉徴収票、医療費明細書、寄附金受領証明書など、適用を受ける控除に応じた書類を漏れなく用意しましょう。
必要書類が不足していると、申告作業が滞ってしまう可能性があります。書類の収集は早めに始め、提出期限に余裕を持って申告できるよう心がけましょう。
申告期限を意識したスケジュール管理
確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までです。この期間内に申告を完了させる必要があります。
申告が遅れてしまうと、延滞税や加算税が発生する可能性もあるため、スケジュール管理を徹底することが大切です。早めに申告の準備を始め、余裕を持って提出できるよう計画を立てましょう。
国税庁公式サイトを活用した情報収集
国税庁の公式サイトには、確定申告に関する豊富な情報が掲載されています。申告書の書き方や各種控除の詳細など、申告を進める上で役立つ情報が満載です。
特に、住宅ローン控除や医療費控除など、複雑な計算が必要な控除については、公式サイトの情報を参考にすると良いでしょう。最新の情報を確認し、適切な申告を行うことが重要です。
過去の控除申請漏れは還付申告で対応可能
過去の確定申告で控除の申請漏れがあった場合でも、還付申告を行うことで対応できます。還付申告の期限は、本来の申告期限から5年間と定められています。
申告漏れに気づいた時点で、速やかに還付申告の手続きを進めましょう。適切な還付申告を行うことで、納め過ぎた税金を取り戻すことができます。
まとめ
本記事では、年末調整と確定申告の基本的な違いや、年末調整後に確定申告が必要となるケース、確定申告で受けられる主な控除について解説してきました。年末調整は会社員の多くが経験する手続きですが、副業や転職・退職時には確定申告が必要となる場合があります。
確定申告を効率的に行うには、必要書類の準備や期限を意識したスケジュール管理が欠かせません。国税庁の公式サイトを活用して情報収集を行い、過去の控除申請漏れは還付申告で対応しましょう。正しい申告を行うことで、税務リスクを回避し、適切に納税義務を果たすことができます。
最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン
急な受注や支払いが重なって、早急な資金調達が必要になったときに便利なのがビジネスローンです。
HTファイナンスでは、スピードと柔軟性を重視した独自の審査体制を整え、より早く経営者の皆様へ資金をご提供できるよう努めています。
必要書類もシンプルなので、準備に時間をかけることなくお申し込みいただけます。
また、オンラインやお電話でのやり取りを中心に契約まで進められるので、来店の手間を軽減できるのもポイントです。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずは一度HTファイナンスの借入枠診断をお試しください。