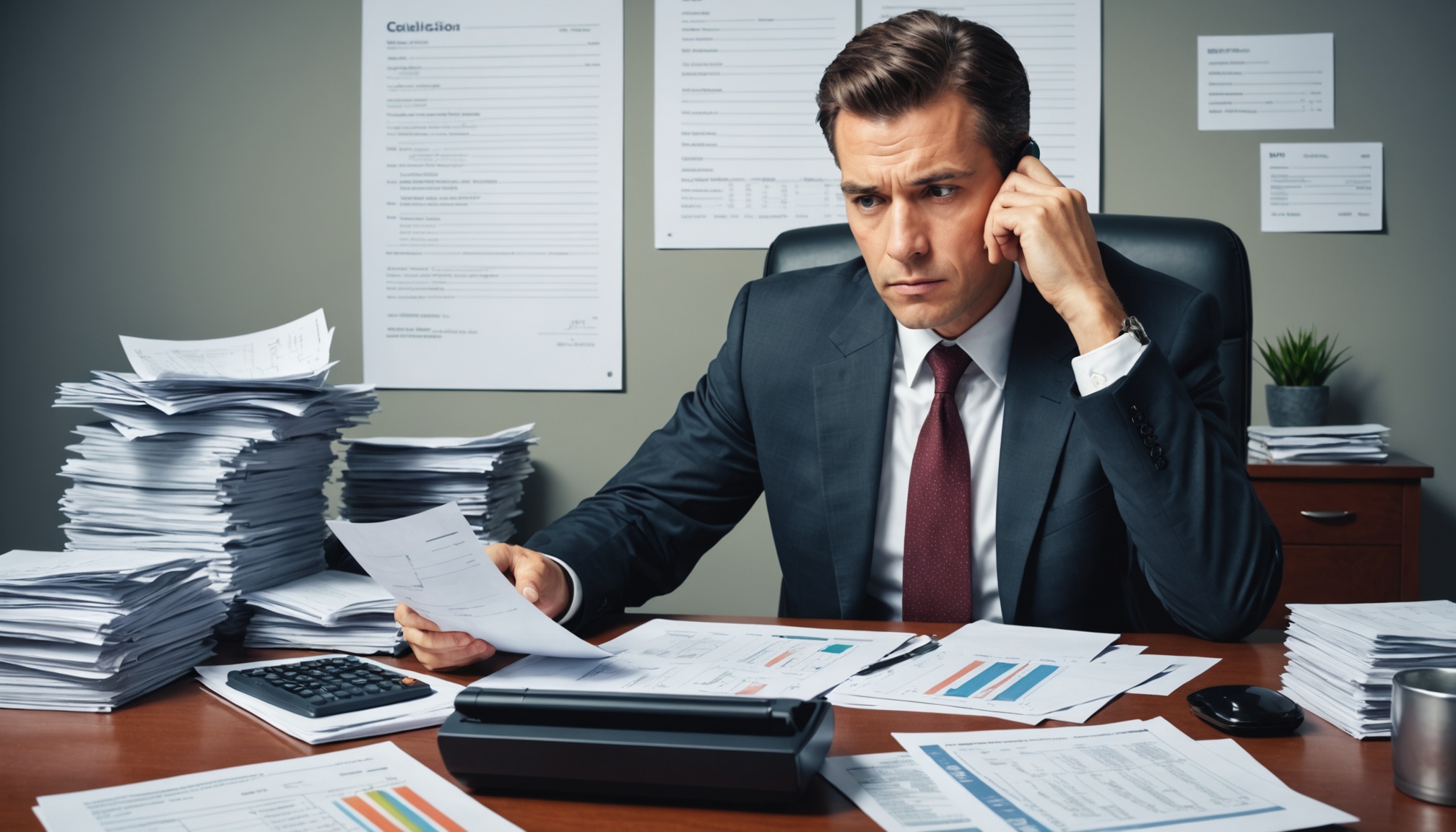2025.04.14
ファクタリングで二重譲渡は犯罪!バレる理由やバレた場合の罰則を解説
資金繰りに困った際の選択肢として注目されているファクタリングですが、その利用には十分な注意が必要です。特に、問題となるのが「二重譲渡」です。
ファクタリングにおける「二重譲渡」とは、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する行為で、刑法上の犯罪に該当します。一時的な資金調達のために二重譲渡を行うと、詐欺罪や横領罪で刑事責任を問われるだけでなく、企業の信用が低下することにより経営破綻につながる可能性もあります。
本記事では、ファクタリングにおける二重譲渡の危険性、発覚する理由、罰則について詳しく解説し、適切な債権管理の重要性をお伝えします。
ファクタリングにおける二重譲渡とは
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡して資金を調達する仕組みですが、同じ債権を複数社に譲渡する「二重譲渡」は、厳しく罰せられます。これは、詐欺や横領など刑法上の罪にあたる行為であり、企業の信用失墜や経営破綻を招きます。
ファクタリングの仕組み
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権を第三者(ファクタリング会社)に売却して、即時に資金を調達する金融サービスです。通常、売掛金の支払期日を待たずに現金化できるため、資金繰りの改善に役立つことが特徴となっています。
ファクタリングの取引では、企業(売主)は売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、その対価として債権額から手数料を差し引いた金額を受け取ります。その後、支払期日が来ると、債務者(売掛先)はファクタリング会社に支払いを行います。
ファクタリング取引における重要なポイントは、売掛債権の所有権が企業からファクタリング会社に完全に移転する点です。つまり、一度譲渡した債権は、もはや企業のものではなくなります。
二重譲渡とは
二重譲渡とは、既に一つのファクタリング会社などに譲渡済みの売掛債権を、別のファクタリング会社などにも譲渡する行為を指します。簡単にいえば、同じ売掛債権を複数の会社に売ることです。
例えば、A社がB社に対して100万円の売掛債権をもっているとします。A社はこの債権をファクタリング会社Xに譲渡し、90万円を受け取りました。しかし、さらに資金が必要になったA社が、同じB社向けの100万円の債権をファクタリング会社Yにも譲渡し、また資金を得るというケースが二重譲渡に当たります。
売掛債権は目にみえない無形資産であるため、物理的な移動がなく二重譲渡が発生しやすいものです。しかし、この行為をしてしまうと、単なる契約違反ではなく、法律違反として厳しく罰せられてしまいます。
なぜ二重譲渡が発生するのか
二重譲渡が発生する背景には、いくつかの原因があります。最も多いのは、資金繰りの悪化による緊急的な資金需要です。一度ファクタリングを利用しても、さらに資金が必要になった場合、安易に同じ債権を再度譲渡してしまうケースがあります。
また、社内の債権管理体制が不十分で、どの債権がすでに譲渡されているかの把握ができていないことも二重譲渡をしてしまう原因となります。特に、複数の部署や担当者がファクタリング取引に関わる場合、情報共有の不足から、意図せず二重譲渡が起こることもあります。
これらは、意図的に行われる場合も少なくありません。「支払期日までに何とかなる」という安易な考えや、「バレなければ問題ない」という認識により、二重譲渡に踏み切ってしまうのです。
ファクタリングの二重譲渡の法律上の規定
ファクタリングにおける二重譲渡が判明した場合、刑法の詐欺罪、横領罪・業務上横領罪が適用され、民事上の責任も負うことになります。
詐欺罪(刑法246条)の適用
ファクタリングにおける二重譲渡は、まず詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性が高いものです。詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる行為を罰する規定です。
二重譲渡の場合、既に譲渡した売掛債権を自分のものであるかのように偽って別のファクタリング会社に譲渡し、金銭を受け取ります。この行為は明らかに「人を欺く」行為に当たり、詐欺罪の構成要件を満たします。
詐欺罪は、10年以下の懲役が科される(実刑)重い犯罪です。企業の代表者や実行した担当者個人が、刑事責任を問われることになります。
横領罪・業務上横領罪(刑法252・253条)の適用
二重譲渡は、横領罪または業務上横領罪にも該当します。横領罪(刑法252条)は、自己の占有する他人の物を不法に領得する行為を罰するものです。業務上横領罪(刑法253条)は、業務上占有する他人の物を横領した場合の規定です。
ファクタリング契約により、売掛債権を譲渡した時点で、その債権の所有権はファクタリング会社に移転します。にもかかわらず、同じ債権を別のファクタリング会社に譲渡して対価を得ることは、既に他人の物となった債権を不法に処分する行為であり、横領罪の要件を満たします。
特に、企業の経営者や債権管理担当者が行った場合は、業務上横領罪として、10年以下の懲役という重い刑罰の対象となります。
民事上の責任を負う
刑事責任に加えて、二重譲渡を行った企業は、民事上の責任も負います。まず、契約違反による債務不履行責任を負い、ファクタリング会社から損害賠償を請求されることになります。
損害賠償の範囲は、通常以下のものが含まれます:
- 譲渡を受けた債権の全額
- 取引にかかった諸費用(調査費用、弁護士費用など)
- 遅延損害金
- その他ファクタリング会社が被った損害
これらの賠償金は企業の財務に大きな打撃を与え、場合によっては企業の存続自体を危うくします。民事訴訟による損害賠償責任は経営に大きく影響が及ぶため、決して軽視できません。
ファクタリングの二重譲渡が発覚する理由
ファクタリングの二重譲渡は、隠し通そうとしてもいつか必ず発覚するものです。どのような経緯で発覚するのか、具体的にみていきましょう。
債権譲渡登記による発覚
ファクタリング取引では、多くの場合、債権譲渡の事実を法務局に登記します。これは「債権譲渡登記」と呼ばれるもので、誰が債権の所有者であるかを公示する制度です。
ファクタリング会社は新たな取引を行う前に、必ずこの債権譲渡登記を確認します。そのため、既に譲渡済みの債権であれば、この調査段階で二重譲渡の事実が判明します。
支払期日での発覚
仮に、最初の段階で気付かれずに二重譲渡が行われたとしても、売掛金の支払期日が来れば必ずその事実が発覚します。なぜなら、債務者(売掛先の企業)は、同じ債権に対して二重に支払うことはできないからです。
例えば、A社の債権が、ファクタリング会社XとYの両方に譲渡されたとします。支払期日になると、XとY両方から債務者に対して支払請求が行われます。債務者は混乱し、どちらに支払うべきか判断できないため、ファクタリング会社同士で確認が行われ、二重譲渡の事実が明らかになります。
この時点で、譲渡を行った企業の不正行為が発覚し、法的措置が取られることになります。
内部告発や監査による発覚
企業内部からの告発や監査によって、二重譲渡が発覚するケースも少なくありません。特に、以下のような状況で発覚することがあります。
- 経理担当者や財務部門の従業員による内部告発
- 監査法人による定期監査での発見
- 経営者の交代時の引継ぎ調査
- 取引先からの問い合わせによる発覚
企業規模が大きいほど関係者も多く、隠し通すことは難しくなります。
ファクタリング会社間の情報共有
ファクタリング業界では、不正取引防止のために会社間で情報共有が行われることがあります。特に大手ファクタリング会社では、過去に問題のあった企業のブラックリストを共有していることもあります。
また、同じ債権に関して、複数のファクタリング会社から問い合わせがあった場合、ファクタリング会社間で連絡を取り合い、二重譲渡の可能性について確認することがあります。
このような業界内のネットワークによっても、二重譲渡の事実は発覚しやすくなっています。いずれにせよ、「バレない」と考えるのは非常に危険な発想です。
ファクタリングで二重譲渡をした場合の具体的な罰則
二重譲渡が発覚した場合、どのような罰則が科されるのか、具体的にみていきましょう。
刑事罰の詳細と量刑
二重譲渡に適用される主な刑事罰は以下の通りです:
| 罪名 | 法的根拠 | 量刑 |
|---|---|---|
| 詐欺罪 | 刑法246条 | 10年以下の懲役 |
| 横領罪 | 刑法252条 | 5年以下の懲役 |
| 業務上横領罪 | 刑法253条 | 10年以下の懲役 |
実際の量刑は、二重譲渡の金額、回数、計画性、被害回復の有無などによって変わります。特に、高額な案件や複数回の二重譲渡を行った場合は、実刑判決となる可能性が高まります。
これらの刑事罰は個人に科されるものであり、会社の代表者や実行した担当者が刑事責任を問われることになります。重大な経済犯罪として厳しく処罰されるため、決して軽く考えてはいけません。
損害賠償請求の規模と影響
刑事罰と並行して、民事上の損害賠償請求も行われます。その規模は非常に大きくなる可能性があります。
具体的な損害賠償額の例:
- 譲渡代金全額(例:1,000万円の債権なら1,000万円)
- 遅延損害金(年率14.6%程度が一般的)
- 調査費用、弁護士費用(数十万円~数百万円)
- 信用毀損による損害(算定が困難なケースも)
これらの賠償金に加えて、訴訟費用も負担することになります。仮に1,000万円の債権を二重譲渡した場合、損害賠償総額は軽く1,500万円を超える可能性があります。
さらに、この損害賠償は企業だけでなく、実行した役員個人にも請求されることがあります。法人格を否定する「法人格否認の法理」や役員の「第三者に対する責任」(会社法429条)に基づき、個人資産からの支払いを命じられる可能性もあるのです。
信用情報への影響
二重譲渡は、企業の信用情報に深刻な影響を与えます。具体的には、以下のような影響が考えられます。
- 金融機関からの融資停止
- 取引先からの信用取引(掛け取引)の停止
- 新規取引先の開拓困難
- 取引条件の悪化(前払い要求など)
特に金融機関は、二重譲渡を行った企業を「高リスク先」と判断し、既存の融資の引き上げや、新規融資の拒否を行うことが一般的です。信用情報機関への登録により長期的な信用毀損が生じるため、事業継続に深刻な影響を及ぼします。
ファクタリングの二重譲渡を行った企業の実例と末路
実際に二重譲渡を行った企業は、どのような末路をたどるのでしょうか。具体的な事例をみていきましょう。
企業の信用低下による経営破綻
刑事罰だけでなく、二重譲渡は企業の存続自体を脅かします。以下に、二重譲渡をしてしまった企業が辿るであろう流れを示します:
- 二重譲渡の発覚
- ファクタリング会社からの一括返済要求
- 金融機関からの既存融資の引き上げ
- 取引先からの取引停止
- キャッシュフローの急激な悪化
- 資金ショートによる支払い不能
- 破産手続きの開始
特に中小企業の場合、一度信用を失うと立て直しが非常に困難です。一回の信用の喪失が大きな経営危機を招くことを理解しておく必要があります。
再起の難しさと関係者への影響
二重譲渡を行った企業の再起は、非常に困難です。考えられる影響として、以下のような点があります。
- 代表者の前科による信用低下
- 金融機関からの与信停止(数年~10年程度継続)
- 取引先の喪失と新規開拓の困難
- 業界内での風評被害
また、企業の破綻は、従業員や取引先にも大きな影響を及ぼします。従業員は突然の失業に直面し、取引先は売掛金が回収できなくなるリスクがあります。さらに、連帯保証人となっている役員の個人資産も差し押さえられる可能性があります。
このように、二重譲渡の影響は当事者だけでなく、多くの関係者に広がることを認識しておくべきです。
ファクタリングにおける二重譲渡の防止
二重譲渡を防ぐためには、どのような対策を講じるべきでしょうか。具体的な防止策をみていきましょう。
債権の管理体制の構築
二重譲渡を防ぐ最も基本的な対策は、社内の債権管理体制を整備することです。具体的には、以下のような方法が効果的です:
- 債権管理台帳の作成:すべての売掛債権を一元管理し、譲渡状況を記録する
- 権限の分散:債権譲渡の決定と実行に複数人の承認を必要とする
- 定期的な監査:内部監査や外部監査により債権管理状況を確認する
- マニュアルの整備:債権譲渡に関する明確な社内ルールを文書化する
特に重要なのは、どの債権がすでに譲渡されているかを一目で確認できるシステムを構築することです。体系的な債権管理システムが二重譲渡防止の鍵となります。
債権譲渡登記の活用
債権譲渡登記は、二重譲渡を防ぐ有効な手段です。法務局に債権譲渡の事実を登記することで、第三者に対抗できる効力が生まれます。
以下の点に注意して債権譲渡登記を活用しましょう:
- ファクタリング取引後は速やかに登記を行う
- 新たなファクタリング取引前には必ず登記を確認する
- 登記事項証明書を保管し、社内で共有する
- 登記費用は保険と考え、必ず予算に組み込む
多くのファクタリング会社は、債権譲渡登記を標準的なプロセスとして実施しており、コスト削減のために省略する場合もあります。しかし、安全性を考えれば必ず登記すべきです。
信頼できるファクタリング会社の選定
二重譲渡のリスクを減らすためには、信頼できるファクタリング会社を選ぶことも重要です。以下のような点に注目して選定しましょう。
- 金融庁や財務局に登録されている正規の事業者
- 設立年数が長く、実績が豊富な会社
- 債権譲渡登記を標準プロセスとしている会社
- 契約内容を明確に説明してくれる会社
- 業界団体に所属している会社
優良なファクタリング会社は、二重譲渡防止のための確認プロセスを丁寧に行います。適切な審査と手続きを行うファクタリング会社を選ぶことで、二重譲渡してしまうリスクを減らすことができます。
企業倫理とコンプライアンスの強化
最終的に、二重譲渡を防ぐ最も重要な要素は、企業倫理とコンプライアンス意識です。
- 経営層によるコンプライアンス方針の明確化
- 定期的な法令順守研修の実施
- 内部通報制度の整備
- 違反時の罰則を含む行動規範の策定
短期的な資金調達のために法令違反を犯すことは、長期的にみれば企業に必ず不利益をもたらします。企業内に、コンプライアンスを優先する考え方を浸透させることが重要です。
まとめ
本記事では、ファクタリングにおける二重譲渡について、その危険性から防止策まで幅広く解説してきました。二重譲渡は一時的な資金調達のようにみえても、詐欺罪や横領罪などの犯罪行為として厳しく罰せられ、企業の信用低下や経営破綻に直結する極めて深刻な問題です。
債権の管理体制の構築、債権譲渡登記の活用、信頼できるファクタリング会社の選定によって、二重譲渡してしまうことを防ぐことができます。
企業を持続的に成長させるためには、短期的な資金繰りにとらわれて法令違反のリスクを冒すべきではありません。債権管理を徹底し、計画的に資金調達を行うことで、健全な経営を続けましょう。
また、HTファイナンスでは、ファクタリングからの乗り換えも得意としておりますので、是非一度ご相談お待ちしております。
最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン
急な受注や支払いが重なって、早急な資金調達が必要になったときに便利なのがビジネスローンです。
HTファイナンスでは、二期目以降の法人様を対象に、スピードと柔軟性を重視した独自の審査体制を整え、より早く経営者の皆様へ資金をご提供できるよう努めています。
必要書類もシンプルなので、準備に時間をかけることなくお申し込みいただけます。
また、オンラインやお電話でのやり取りを中心に契約まで進められるので、来店の手間を軽減できるのもポイントです。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずは一度HTファイナンスの借入枠診断をお試しください。