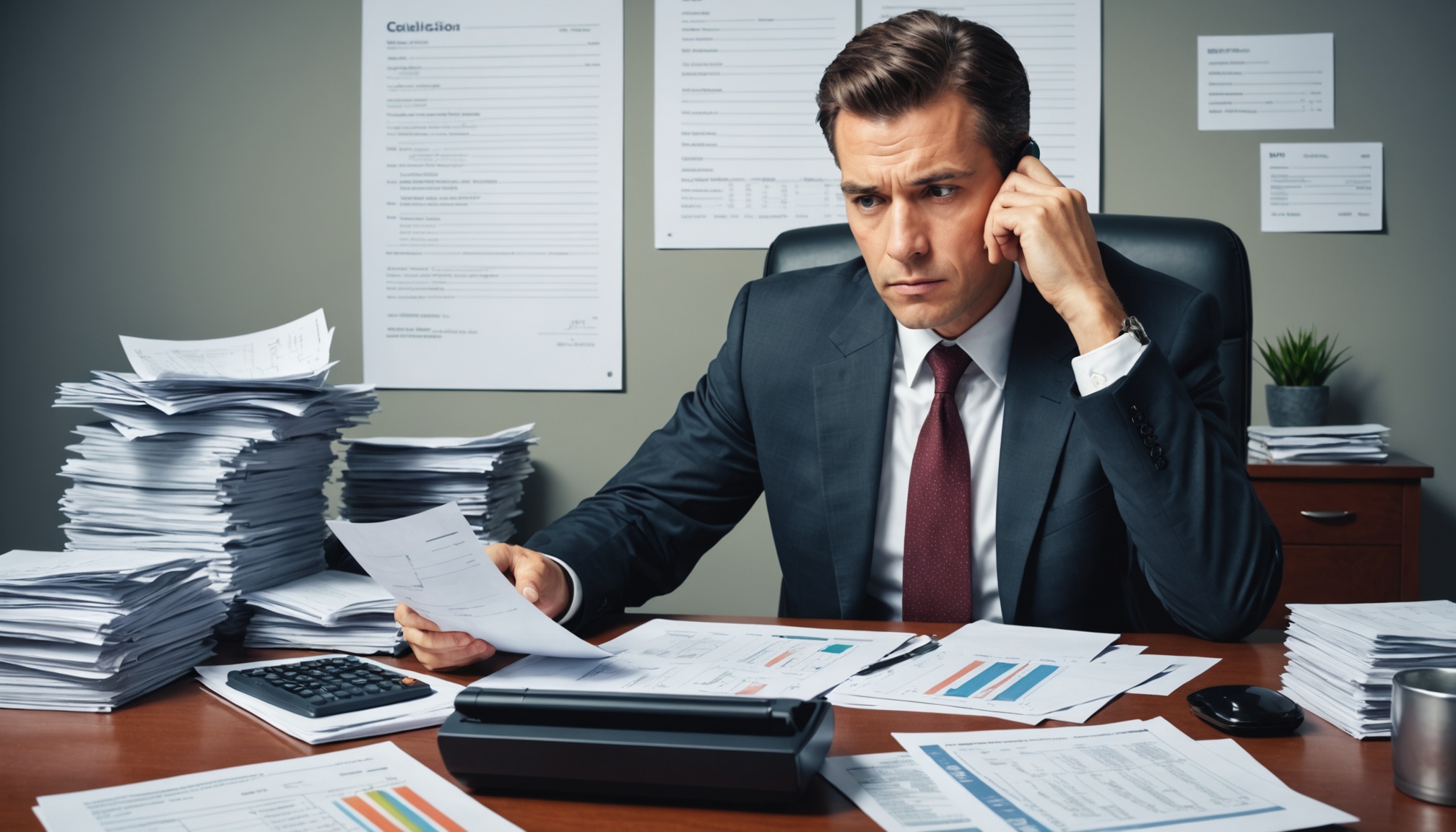2025.04.22
ファクタリングで刑事告訴される!?違法行為になる場合とその回避方法を解説
ファクタリングは、売掛金を即座に現金化できる便利な資金調達手段として、多くの経営者や個人事業主に利用されています。しかし、利用を誤ったり、不正な利用をしてしまうと、刑事告訴につながる可能性があることはあまり知られていません。
特に、架空請求や二重譲渡といった違法行為は、詐欺罪や文書偽造罪に該当し、最悪の場合は実刑に処される可能性もあります。ファクタリング自体は合法的な資金調達手段ですが、正しい知識がないまま利用すると、知らないうちに違法行為を犯してしまうリスクがあります。
本記事では、ファクタリング利用で刑事告訴されてしまうケース、そして違法行為を回避するための具体的な方法を詳しく解説します。適切な知識を身につけて、安全にファクタリングを活用することを心がけましょう。
ファクタリングと刑事告訴
ファクタリングは本来、企業の資金繰りを改善するための合法的な金融手法です。しかし、誤った使い方や悪意ある利用によって、刑事責任を問われるケースが存在します。
まず押さえておくべき点として、ファクタリング自体は金融庁の管轄外であり、貸金業とは異なる金融サービスです。債権の譲渡・売買という民法上の契約行為として成立しています。
しかし、この特性を悪用した不正行為をしてしまうと、刑法上の罪に問われる可能性があります。特に、中小企業経営者が資金繰りに困った末に、安易な選択をして刑事告訴されるケースが後を絶ちません。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(未回収の債権)を、ファクタリング会社に売却して即座に資金化する金融サービスです。通常、売掛金の額面から一定の手数料(割引料)を差し引いた金額が支払われます。
一般的なファクタリングの流れは、まず企業がファクタリング会社に売掛金の買取を申し込み、審査を経て買取額を決定します。契約締結後、ファクタリング会社が企業に代金を支払い、後日ファクタリング会社が売掛金の債務者(第三債務者=取引先)から直接回収するという仕組みです。
正規のファクタリング取引は完全に合法であり、多くの企業が資金繰り改善のために活用しています。しかし、この仕組みを悪用した場合には、詐欺や文書偽造といった犯罪行為になってしまいます。
ファクタリング利用で刑事告訴されるケース
ファクタリングに関連して刑事告訴されるケースには、いくつかのパターンがあります。これらを知り、意図せず違法行為に巻き込まれるリスクを回避するようにしましょう。
架空債権の売却による詐欺
最も典型的なファクタリング詐欺は、実際には存在しない架空の売掛金をファクタリング会社に売却するケースです。これは、明らかな詐欺行為に該当します。
例えば、実在しない取引先との取引を装った、偽の請求書や契約書を作成し、あたかも正当な売掛金があるかのようにファクタリング会社に提示するケースがあります。このような行為は、詐欺罪と私文書偽造・同行使罪の両方に問われる可能性があります。
架空債権の売却は、ファクタリング会社を欺いて金銭を騙し取る行為であり、刑法246条の詐欺罪に該当します。詐欺罪は、10年以下の懲役刑という重い罰則が定められています。
二重譲渡による詐欺行為
同一の売掛債権を、複数のファクタリング会社に二重、三重と譲渡するケースも刑事告訴の対象となります。これは、二重譲渡と呼ばれる行為です。
例えば、A社への500万円の売掛金をX社に譲渡した後、同じ債権をY社にも譲渡するといった行為です。二重譲渡は、民法上は無効ではありませんが(債権譲渡の対抗要件の問題)、故意に行った場合は詐欺罪に該当します。
この行為はファクタリング会社に重大な損害を与える違法行為であり、発覚した場合には刑事告訴される可能性が非常に高いといえます。
請求書の改ざんによる詐欺
実際の取引に基づく請求書の金額や日付を改ざんして、ファクタリングを利用するケースも刑事告訴の対象となります。例えば、本来100万円の売掛金を500万円に改ざんする、まだ取引が成立していないのに既に完了したかのように日付を操作するなどの行為です。
この場合、私文書偽造罪(刑法159条)と詐欺罪の両方に問われる可能性があります。特に組織的に行われた場合は、罪状が重くなる傾向があります。
請求書の改ざんは、文書の信頼性を損なう重大な犯罪として扱われ、金融取引における信用を根本から覆す行為とみなされます。
債務者への通知義務の違反
ファクタリングにおいて、債権譲渡を行った場合は、原則として第三債務者(取引先)に通知する必要があります。この通知を故意に怠り、自ら債権回収を行って資金を着服するようなケースも、詐欺罪や横領罪に問われる可能性があります。
特に2社間ファクタリング(償還請求権付きファクタリング)では、第三債務者への通知が行われないケースが多いため、注意が必要です。しかし、契約上の合意なく債権を回収して着服する行為は、明らかに違法です。
契約内容に反する債権回収行為は、ファクタリング会社との信頼関係を損なうだけでなく、法的責任を問われる原因となります。
ファクタリングの詐欺による刑事罰
ファクタリングによる詐欺に関連する刑事罰には、いくつかの種類があります。違法行為の内容や程度によって、適用される罪状や量刑は変わります。
詐欺罪の成立要件と量刑
詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて錯誤に陥れ、その錯誤に基づいて財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする罪です。ファクタリング詐欺では、架空債権の売却や二重譲渡などがこれに該当します。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。実刑判決となった場合、その刑期は詐欺の金額や手口の悪質さ、被害者の数などによって変わりますが、数年の実刑判決となるケースも少なくありません。
詐欺行為の金額が大きいほど刑罰も重くなる傾向があり、特に組織的に行われた場合や反復継続して行われた場合は、より厳しい判決が下される可能性が高まります。
文書偽造罪が適用されるケース
ファクタリングによる詐欺では、架空請求書の作成や既存の請求書の改ざんなどが行われることがあります。これらの行為は、私文書偽造罪(刑法159条)に該当します。
私文書偽造罪の法定刑は、偽造・変造が5年以下の懲役、その行使が同じく5年以下の懲役となっています。また、公文書を偽造した場合はさらに罪が重くなり、公文書偽造罪(刑法155条)として、1年以上10年以下の懲役が科されます。
請求書や契約書といった取引文書は、ビジネスにおける信用の基礎となるものです。文書の正しさを損なう行為は厳しく罰せられるべきとの考えから、裁判所も厳格な判断を下す傾向にあります。
横領罪が適用されるケース
ファクタリング契約後、既に譲渡した債権を自ら回収して着服するようなケースでは、横領罪(刑法252条)が適用される可能性があります。横領罪は、自己の占有する他人の物を横領することで成立します。
横領罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、業務上横領罪(刑法253条)に該当する場合は、10年以下の懲役と重くなります。ファクタリングの契約においてファクタリング会社から債権回収を委託されている場合などは、業務上横領罪が適用される可能性が高いでしょう。
他者の財産を不正に自分のものにする行為は、財産犯の中でも特に背信性が高いとされ、裁判所の判断も厳しくなる傾向があります。
組織的犯罪としての加重処罰
ファクタリング詐欺が組織的に行われた場合、組織的犯罪処罰法が適用される可能性があります。この場合、通常の刑罰よりも重い処罰が科されることになります。
特に、複数人で役割分担して計画的に詐欺を行った場合や、継続して大規模な詐欺を実行した場合などは、組織的詐欺として扱われる可能性が高まります。
詐欺によって得た利益は、犯罪収益として没収・追徴の対象となります。さらに、組織的な犯罪では関与した全員が共犯として処罰される可能性があり、単独犯より厳しい処分となる傾向があります。
ファクタリングを安全に利用するために
ファクタリングを安全に活用するためには、違法行為に及ばないよう未然に対策をとることが不可欠です。以下では、経営者や担当者が実践すべき具体的な行動を紹介します。
債権管理システムの構築
ファクタリング詐欺を防ぐ第一歩は、自社の債権を適切に管理するシステムを構築することです。売掛金の発生から回収までを一元管理し、二重譲渡などをしてしまうリスクを防止します。
具体的には、売掛金台帳を正確に記録・更新し、どの債権がファクタリングに出されているかを明確に把握できるようにします。また、ファクタリング利用の記録を残し、社内で情報共有することも重要です。
透明性のある債権管理体制の構築により、意図せぬ二重譲渡や不正行為を防ぐことができます。
信頼できるファクタリング会社の選定
ファクタリングを利用する際は、信頼できる正規の業者を選ぶことが重要です。悪質な業者の中には、違法行為を誘導したり、不適切な契約を結んだりするケースもあります。
信頼できる業者を見分けるためには、事業実績や会社の透明性、契約内容の明確さなどを確認しましょう。また、極端に高い手数料や、不自然な契約条件を提示する業者は避けるべきです。
特に重要なのは、契約内容をしっかり確認して理解することです。不明点があれば質問し、納得できるまで説明を求めましょう。必要に応じて、弁護士などの専門家に契約書のチェックを依頼することも有効です。
社内コンプライアンス体制の強化
ファクタリング詐欺を防ぐためには、社内のコンプライアンス体制を強化することが不可欠です。特に、財務・経理部門におけるチェック体制の確立が重要です。
具体的な対策としては、ファクタリング契約の締結に複数人の承認を必要とする仕組みの導入、定期的な内部監査の実施、従業員への法令遵守の教育などが挙げられます。
相互チェックの仕組みを取り入れることで、個人の判断ミスや不正行為を防止できます。特にファクタリングのような資金調達については、決裁権限が明確な管理体制を構築することが大切です。
専門家への相談
ファクタリングを利用する際は、弁護士や税理士などの専門家に相談することも有効な予防策です。特に、大きな金額や複雑な取引の場合は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
また、定期的に顧問弁護士などによる法務チェックを受けることで、意図せずに違法行為を行ってしまうリスクがないかを確認することができます。法律や規制は変更されることもあるため、最新の情報を得ることも重要です。
専門家の客観的な視点を取り入れることで、自社だけでは気づきにくい問題点を発見できる可能性が高まります。コストがかかるという側面はありますが、刑事告訴されてしまうリスクを考えれば、必要な投資といえるでしょう。
ファクタリングの利用で刑事告訴された場合の対応
万が一、ファクタリングに関連して刑事告訴された場合、冷静かつ適切に対応することが重要です。初期対応を誤ると、状況がさらに悪化してしまう可能性があります。
弁護士への速やかな相談
刑事告訴されたり、捜査機関から事情聴取を求められたりした場合、最初にすべきことは弁護士への相談です。刑事事件に強い弁護士を選び、できるだけ早く相談することが重要です。
弁護士は法律の専門知識をもっているだけでなく、刑事手続きにおける適切な対応方法も熟知しています。また、捜査機関とのやり取りを仲介し、あなたの権利を守る役割も果たします。
弁護士への相談は権利であり自己防衛です。「弁護士に相談すると疑われる」という考えは誤りで、むしろ専門家の助言を得ることで、正しい対応をとることができます。
取引先や金融機関への対応
刑事告訴されると、その事実が取引先や金融機関に知られる可能性があります。風評被害を最小限に抑えるためにも、状況に応じた適切な対応が必要です。
まず、事実関係を整理し、弁護士と相談したうえで、重要な取引先には適切なタイミングで状況を説明することも検討しましょう。
また、風評被害に備えた資金繰り対策も重要です。金融機関からの与信が停止されてしまう場合もあるため、代替の資金調達手段を検討しておくことをおすすめします。
証拠保全と事実関係の整理
刑事告訴された場合、関連する書類や電子データなどの証拠を保全し、事実関係を整理することが重要です。特に、自社の正当性を証明するための証拠は、積極的に確保しましょう。
具体的には、ファクタリング契約書、関連する請求書や納品書、メールやチャットなどのやり取り、会議の議事録など、取引の経緯を示す資料をすべて保存します。データは、複数のバックアップを取ることをおすすめします。
事実関係を時系列で整理することも有効です。いつ、誰が、どのような判断や行動をしたのかを明確にすることで、弁護士との相談や捜査への対応がスムーズになります。
捜査への誠実な協力
刑事告訴を受けた場合、基本的には捜査に協力する姿勢を示すように心がけましょう。ただし、自己に不利益な供述を強制されることはないため、弁護士のアドバイスを受けながら対応することが大切です。
取調べの際には、事実と異なる供述や曖昧な返答は避け、明確に答えられないことは「分からない」と正直に答えるべきです。焦って虚偽の供述をすると、後で矛盾が発覚し、さらに状況が悪化する可能性があります。
真摯かつ誠実な対応を心がけることで、捜査機関に対しても誠意を示すことができます。無実である場合は特に、事実に基づいた冷静な対応が重要です。
ファクタリングを合法的に利用するためのポイント
ファクタリングは、正しく利用すれば、企業の資金繰りを改善する有効な手段です。以下では、違法行為のリスクを避けつつ、安全にファクタリングを活用するためのポイントを解説します。
適正な債権のみをファクタリングに出す
ファクタリングを利用する際の基本は、実在する正当な債権のみを対象とすることです。架空の債権や内容を誇張した債権をファクタリングに出すことは、詐欺罪に該当する可能性があります。
具体的には、確実に納品・検収が完了している取引、請求書が発行済みの取引、取引先との間でトラブルや未解決の問題がない取引などが、ファクタリングに適した債権といえます。
売掛債権の実在性を確認し、回収できる可能性を見積もることが、安全なファクタリング利用の第一歩です。自社内でもチェックリストを作成するなどして、適切な債権を選ぶ仕組みを構築しましょう。
書類内容の保持
ファクタリングの契約を結ぶ際は、契約内容を確認し、すべての取引記録を適切に保管することが重要です。後々のトラブルを防ぐためにも、契約書や関連書類は、少なくとも債権の回収期間が終了するまで保管しましょう。
特に重要な書類としては、ファクタリング契約書、譲渡対象となる売掛金の請求書、納品書、契約書のコピー、債権譲渡通知書(債務者への通知)などが挙げられます。
取引の全プロセスを文書化して保存することで、後日問題が生じた際の証拠となるだけでなく、社内での引き継ぎや監査の際にも役立ちます。
適切な債権譲渡通知の実施
ファクタリングでは、債権譲渡の事実を債務者(取引先)に通知することが原則となります。これにより、債権譲渡の法的効力が確保され、二重譲渡などのリスクを防止できます。
債権譲渡通知は書面で行うのが一般的で、内容証明郵便を利用するケースも多くあります。通知の際は、譲渡する債権の内容、譲渡先、譲渡日などを明記します。
ただし、2社間ファクタリングでは、債務者への通知を行わないケースもあります。その場合でも、契約内容を明確にして当事者間の認識を一致させることが大切です。
代替手段の検討
ファクタリングは便利な資金調達手段ですが、手数料が高いケースも多く、常に最適な選択肢とは限りません。状況に応じて、銀行融資や補助金・助成金の活用、資本政策の見直しなど、他の資金調達手段も検討しましょう。
特に、常にファクタリングに頼り続ける状況は、財務体質の根本的な改善が必要なサインかもしれません。資金繰り表の作成や定期的な財務分析を行い、長期的な視点で資金計画を立てることが大切です。
複数の資金調達手段を理解して活用することで、状況に応じた最適な選択が可能になります。ファクタリングは、あくまで選択肢の一つとして活用することをおすすめします。
まとめ
ファクタリングは、企業の資金繰りを改善する有効な手段ですが、誤った使い方や不正利用は刑事告訴のリスクをもたらします。架空債権の売却や二重譲渡といった行為は詐欺罪や文書偽造罪に該当し、厳しい処罰の対象となります。
違法行為を回避するためには、適切な債権管理システムの構築、信頼できるファクタリング会社の選定、社内コンプライアンス体制の強化が重要です。万が一問題が発生した場合は、速やかに弁護士に相談し、誠実に対応するようにしましょう。自社の資金繰りを守りながらも、法令にしっかり従った健全な経営を心がけましょう。
最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン
ファクタリングは法的リスクが心配になるという方は、ビジネスローンも選択肢の一つとして検討してもよいでしょう。安全かつスピーディーな資金調達なら、HTファイナンスのビジネスローンがおすすめです。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。