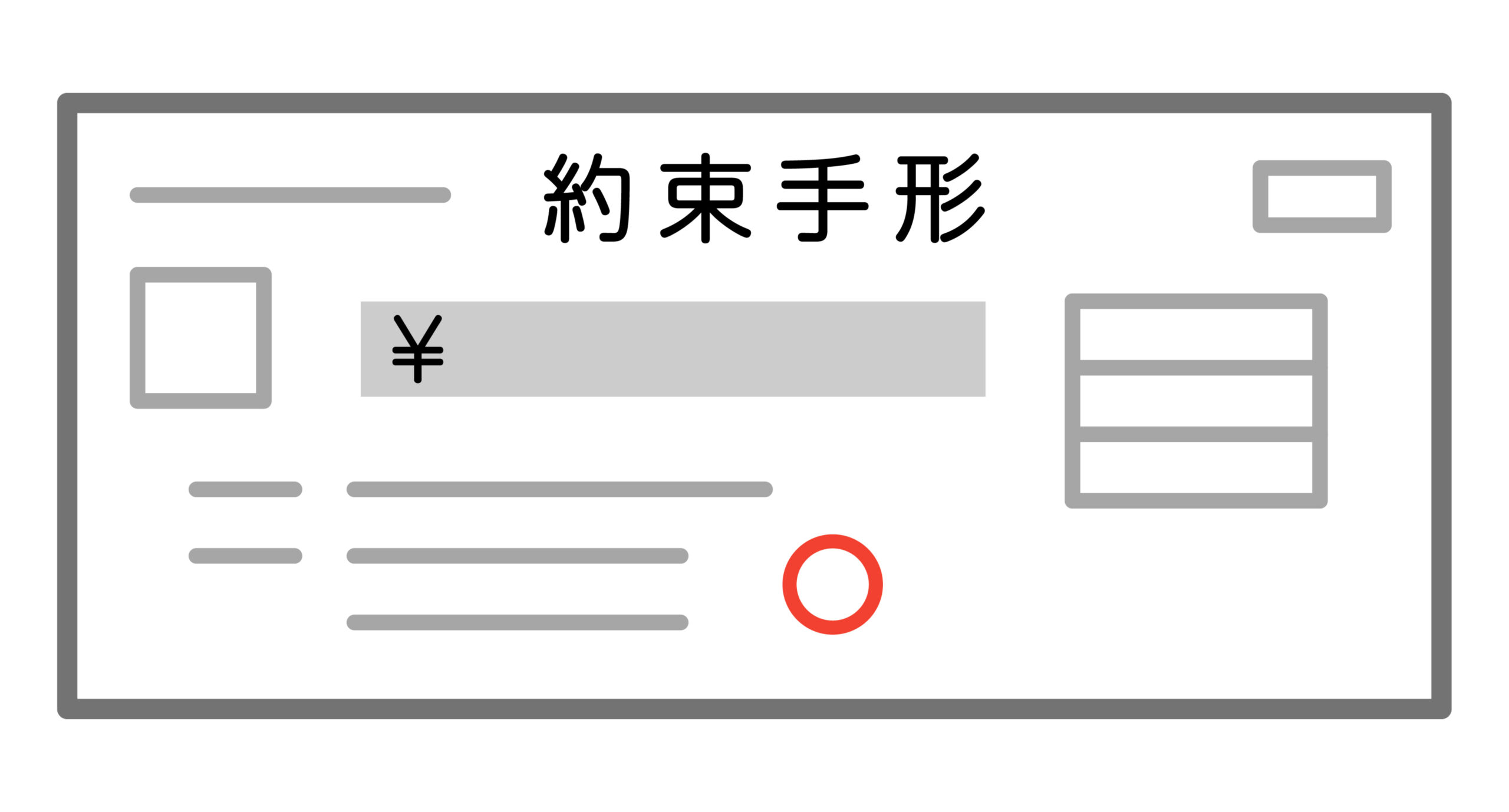2025.04.17
起業が失敗してしまう原因は?避けるべき落とし穴と成功へのステップを紹介
多くの経営者や起業家は、「自分のビジネスを成功させたい」という強い思いを胸に事業を立ち上げます。しかし、熱意をもって始めた事業でも、必ずしも計画通りに進展するとは限りません。実際、統計によれば、新規事業の約7割が10年以内に廃業を余儀なくされています。
本記事では、起業が失敗してしまう主な原因と、それを避けるための具体的な対策を解説します。資金管理の不足や業績不振、経営陣のトラブルなど、失敗する原因を事前に理解することで、同じ失敗を避けることができるでしょう。また、起業を成功に導くために必要なポイントや、困ったときの資金調達方法についても紹介します。
起業が失敗する7つの原因
起業が失敗する原因は多岐にわたりますが、特に重要な7つの要因について詳しくみていきましょう。
1.資金管理の不足
起業失敗の最も一般的な原因の一つが、資金管理の不足です。初期投資だけを考え、運転資金の確保や長期的なキャッシュフロー管理を怠ってしまう起業家は、この失敗に陥りやすいものです。
事業を軌道に乗せるまでには予想以上の時間がかかることが多く、その間の資金繰りが計画通りに進まないと、たちまち資金ショートに陥ります。特に、売上が計画より下回った場合や、予期せぬ出費が発生した場合には、すぐに経営危機に直面することになります。
2.市場調査の不足
多くの起業家は、自分のビジネスアイデアに強い思い入れがあるため、市場の現実を冷静に分析できないことがあります。その結果、需要予測が甘くなり、売上が計画を大幅に下回ることになります。
また、競合調査が不十分だと、市場の飽和状態や競合他社の強みを見誤り、差別化戦略が不足したまま市場に参入してしまいます。さらに、顧客ニーズの把握が不足していると、製品やサービスが市場に受け入れられない可能性も高まります。
3.経営メンバー間のトラブル
共同創業者や主要メンバー間での意見の相違や役割分担の不明確さは、初期段階で事業成長の大きな妨げとなります。特に友人や知人と起業する場合、ビジネス上の厳しい決断が必要になったときに、人間関係が悪化することも少なくありません。
また、利益配分や株式保有比率についての取り決めが曖昧だと、事業が軌道に乗った後で、個人的な利益が原因でのトラブルに発展する可能性があります。経営理念や将来のビジョンの不一致も、長期的には大きな問題となります。
4.過大投資
起業初期は特に「身の丈に合った経営」が重要ですが、多くの起業家は成長への期待から過大な投資を行ってしまいます。高額なオフィス賃料、必要以上の人員採用、過剰な設備投資、原材料の過剰仕入などが典型的な例です。
また、事業が軌道に乗り始めたばかりの段階で急激な拡大を目指すと、管理体制が追いつかず、品質の低下や顧客対応の悪化を招くことがあります。さらに、個人的な支出と事業支出の区別が曖昧になると、知らず知らずのうちに会社の資金が流出していくこともあります。
5.社会情勢・市場変化への対応不足
ビジネス環境は常に変化しており、特にテクノロジーの進化や消費者行動の変化は加速度的に進んでいます。こうした変化に対応できない企業は、次第に市場での競争力を失っていきます。
多くの起業家は自社の製品やサービスに固執するあまり、市場の変化に気づかなかったり、気づいても対応が遅れたりすることがあります。また、新たな競合の参入や代替品の出現といった外部環境の変化を軽視することも、失敗の原因となります。
6.ビジョン・目的の不明確さ
明確な長期ビジョンや事業目的がない企業は、日々の業務に追われるうちに方向性を見失い、一貫性のない経営判断を下すことになります。その結果、リソースが分散し、どの分野でも中途半端な成果しか出せない状況に陥りがちです。
また、ビジョンが不明確だと、従業員のモチベーション維持も難しくなります。特に優秀な人材ほど、会社の方向性や自分の貢献がみえないと、離職する傾向があります。顧客からの信頼獲得も、一貫したビジョンがないと困難です。
7.人材の採用・育成力不足
起業初期は、限られた資金の中で人材を確保する必要があり、多くの場合、経営者の知人や友人を採用したり、予算の都合で経験の浅い人材を雇ったりすることになります。しかし、事業の成長に伴い、より専門的なスキルや経験をもった人材が必要となります。
また、採用した人材を育成する仕組みや時間がなく、せっかく採用した人材が十分に力を発揮できないケースも少なくありません。特に成長フェーズでは、組織体制の構築や人材育成が追いつかず、サービスの質が低下することや、社内混乱を招いてしまうことがあります。
起業を成功に導くための5つの重要ポイント
起業が失敗する原因を理解したうえで、それを踏まえた成功するための具体的なポイントを押さえるとよいでしょう。
綿密な計画の作成
成功する起業家は、感覚や熱意だけでなく、綿密な事業計画と資金計画に基づいて行動します。これは単なる書類作成ではなく、ビジネスの実現可能性を検証し、リスクを予測するための重要なプロセスです。
事業計画では、市場規模や競合状況、顧客ニーズ、差別化戦略などを詳細に分析します。また、資金計画では、初期投資だけでなく、黒字化までの運転資金や予期せぬ出費に対する予備費も含めて計画します。これらの計画は固定的なものではなく、市場の反応や状況変化に応じて柔軟に見直すようにしましょう。
その際、現実的な数字に基づいた計画を立てることが大切です。特に、売上予測は楽観的になりがちですが、最悪のケースを含む複数のシナリオを想定し、それぞれにどう対応するかを考えておくことが重要です。また、計画の妥当性については、可能な限り先輩起業家、専門家などの第三者の意見を取り入れることをおすすめします。
小規模・低リスクからのスタート
起業の成功率を高めるアプローチとして、「リーンスタートアップ」や「MVP(最小限の実行可能な製品)」の考え方が注目されています。これは、最小限の投資(製品の市場投入)で市場の反応を確認しながら、段階的に事業を拡大していく方法です。
例えば、大規模な店舗を構える前にポップアップストアで市場の反応をみたり、フルスペックの製品開発前に簡易版で顧客ニーズを確認したりする方法があります。この方法なら、万が一市場の反応が思わしくなくても、大きな損失を出す前に方向転換が可能です。
最小限のリソースで検証と学習を繰り返すアプローチは、非常に効果的です。特に固定費(人件費、賃料など)は慎重に抑え、成果がみえてから段階的に投資を増やしていくことで、リスクを最小化できます。また、本業をしながらの副業起業や、パートタイムでの起業から始めるのも、このアプローチの一種といえます。
専門家や人的ネットワークの活用
起業家一人で全ての専門知識をもつことは、不可能です。そのため、成功する起業家は、自分の不得意分野や専門外の領域については、積極的に外部の専門家を活用します。税理士や弁護士、マーケティング専門家など、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、それぞれの分野での初歩的なミスを避けることができます。
また、同業他社や関連業界の起業家とのネットワークも非常に重要です。先輩起業家からのアドバイスや業界動向の情報、時には取引先の紹介なども得られます。さらに、起業家同士の交流は精神的なサポートにもなります。
信頼できるアドバイザーを早期に確保するようにしましょう。特に、財務・法務関係は素人判断が危険なため、創業時から専門家に相談することが推奨されます。また、起業家コミュニティや業界団体への参加、SNSを活用した人脈形成など、積極的にネットワーキングを行うことも大切です。
顧客からのフィードバックの重視
成功する事業の多くは、当初の計画通りに進むことはほとんどありません。市場に出してみて初めて気づく課題や顧客ニーズがあり、それに応じて製品やサービス、ビジネスモデルを調整していくことが重要です。
特に創業初期は、顧客からのフィードバックを積極的に集め、それに基づいて迅速に改善を行うサイクルが成功の鍵となります。初期の顧客は単なる収益源ではなく、ビジネスを改善するための貴重な情報源と捉えることが大切です。
顧客の声に真摯に耳を傾け、すぐに対応する姿勢をもちましょう。定期的な顧客アンケートやインタビュー、SNSでの意見収集など、さまざまな方法で顧客の声を集め、それを事業改善に活かすプロセスを確立することが大切です。また、当初の想定と現実が違うとわかった場合は、柔軟に方向転換する勇気も必要です。
綿密な資金繰り管理
事業の継続には、適切な資金繰り管理が不可欠です。どんなに優れたビジネスモデルでも、資金が枯渇すれば事業継続は不可能になります。成功する起業家は、常に先を見据えた資金計画を立て、必要に応じて適切なタイミングで資金調達を行います。
資金調達の方法には、自己資金、融資(銀行、日本政策金融公庫など)、出資(ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家)、クラウドファンディングなど、さまざまな選択肢があります。事業段階や目的によって最適な調達方法は異なるため、それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが重要です。
必ず、資金繰りの見通しを常に更新し把握する習慣をつけましょう。少なくとも3〜6ヶ月先までの資金繰り予測をもち、資金不足が予想される場合は早めに対策の手を打つことが大切です。また、急な資金需要に備えて、ファクタリングや売掛金担保融資など、緊急時の資金調達手段についても事前に情報収集しておくことをおすすめします。
資金繰り困ったときの資金調達方法
起業する過程でしばしば直面するのが、資金繰りの問題です。緊急時にも冷静に対応できるよう、さまざまな資金調達方法について知っておきましょう。
ファクタリング
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(まだ支払いを受けていない請求書)を、ファクタリング会社に売却して即時に資金化する方法です。通常、売掛金の支払いを受けるまでには30〜60日かかりますが、ファクタリングを利用することで、即日〜数日で資金化が可能になります。
ファクタリングの大きなメリットは、借入ではなく資産の売却になるため、返済義務が生じない点です。また、審査基準も融資より緩やかで、創業間もない企業や信用力が低い企業でも利用しやすいという特徴があります。一方で、売掛金額から手数料(一般的に5〜20%程度)が差し引かれるため、調達コストが比較的高くなります。
ファクタリングは、短期的な資金ショートを防ぐ手段として有用な手段です。特に、大型案件の入金前や季節的な資金需要がある場合など、一時的な資金不足を解消するのに有効です。ファクタリング会社を選ぶ際は、手数料率だけでなく、スピード、対応の柔軟性、信頼性なども比較検討することをおすすめします。
政府系金融機関の創業融資
日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関は、創業者向けの特別融資制度を設けています。これらの融資は、民間銀行に比べて金利が低く、審査基準も創業者に配慮したものになっているため、起業する際の資金の調達先としても適しています。
政府系金融機関の創業融資を受ける際は、創業前から情報収集と準備を始めることが重要です。特に、事業計画書の作成は融資審査の重要なポイントになるため、専門家のアドバイスを受けながら丁寧に準備することをおすすめします。また、自治体によっては創業融資への利子補給制度や保証料補助制度もあるため、地元の創業支援窓口にも尋ねてみましょう。
補助金・助成金
創業時や事業拡大時には、さまざまな補助金・助成金制度を活用することができます。これらは返済不要の資金として、事業の立ち上げや成長に大きく貢献します。代表的なものとしては、「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」「創業補助金」などがあります。
補助金・助成金の大きなメリットは返済不要な点ですが、一方で申請のハードルが高い、採択率が低い、資金交付までに時間がかかるなどのデメリットもあります。また、多くの場合、補助対象経費の一部(1/2〜2/3程度)のみが補助されるため、自己資金も必要になります。
事業計画に合った補助金を戦略的に選択することが大切です。補助金の情報は「J-Net21」や「ミラサポ」などの公的サイトで収集できます。申請には事業計画書の作成など相応の準備が必要なため、締切に余裕をもって取り組むことをおすすめします。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて、不特定多数の人から資金を集める方法です。単なる資金調達手段としてだけでなく、製品やサービスの市場検証、認知度向上、ファンづくりなど多方面にわたるメリットがあります。
クラウドファンディングには、大きく分けて「購入型」「寄付型」「投資型」の3種類があり、特に創業期には、製品やサービスと引き換えに資金を集める「購入型」が活用されることが多くあります。成功すれば資金調達が可能なだけでなく、事業の社会的評価も得ることができます。
魅力的なストーリーと適切なリターン設計を行うことが、成功の鍵です。単なる資金調達ではなく、支援者と共に事業を創り上げるという姿勢で、定期的な情報発信と魅力的なプロジェクト設計を心がけましょう。
銀行融資
創業期でも、事業計画の内容次第では、銀行融資を受けられる可能性があります。特に信用保証協会の保証付き融資は、創業者にとって有力な選択肢となります。信用保証協会は、中小企業の資金調達をサポートする公的機関で、同協会が保証人となることで銀行からの融資が受けやすくなります。
特に、「創業関連保証」や「創業等関連保証」は、創業前や創業後間もない企業向けの制度で、一定条件を満たせば比較的有利な条件で融資を受けられます。ただし、信用保証協会を利用する場合も審査があり、事業計画の実現可能性や返済能力が問われます。また、保証料(融資額の約0.5〜2.2%)が必要になる点も注意しましょう。
銀行融資を検討している場合は、メインバンクとなる銀行との関係構築を早期に始めることが重要です。融資を受けるためだけでなく、事業全般の相談役として銀行と良好な関係を築いておくと、さまざまな場面でサポートを得られます。また、地域によっては自治体が行う創業融資の利子補給制度や保証料補助制度もあるため、地元の創業支援窓口で情報収集することもおすすめします。
まとめ
起業は、多くのリスクを伴う挑戦です。この記事では、起業が失敗する主な原因として、資金管理の不足、業績不振、経営メンバー間のトラブル、放漫経営、社会情勢への対応不足、ビジョンの不明確さ、人材の採用・育成力不足という7つの要因を挙げ、解説しました。
起業を成功させるためのポイントとして、綿密な計画作成、スモールビジネスのような小規模・低リスクからのスタート、人的ネットワークの構築、顧客のフィードバックの重視、そして適切な資金繰り管理といった点が挙げられます。また、万が一の場合に備えて、ファクタリングや政府系金融機関の融資など、さまざまな資金調達手段についても理解しておくことが重要です。
起業は決して容易な道ではありませんが、失敗の原因と成功のポイントを理解し、着実に準備を進めることで、成功への確率を高めることができます。
最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン
起業を成功させるためには、資金繰りを安定させることが重要です。しかし、急な資金ニーズや一時的な運転資金不足に陥るケースも珍しくありません。そのような場合は、迅速な資金調達が経営の命運を分けることもあります。
HTファイナンスでは、二期目以降の法人様を対象に、スピードと柔軟性を重視した独自の審査体制を整え、より早く経営者の皆様へ資金をご提供できるよう努めています。必要書類もシンプルにまとめていますので、準備に時間をかけることなくお申し込みいただけます。また、オンラインやお電話でのやり取りを中心に契約まで進められるケースもあり、来店の手間を軽減できるのもポイントです。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずは一度HTファイナンスまでお問い合わせください。