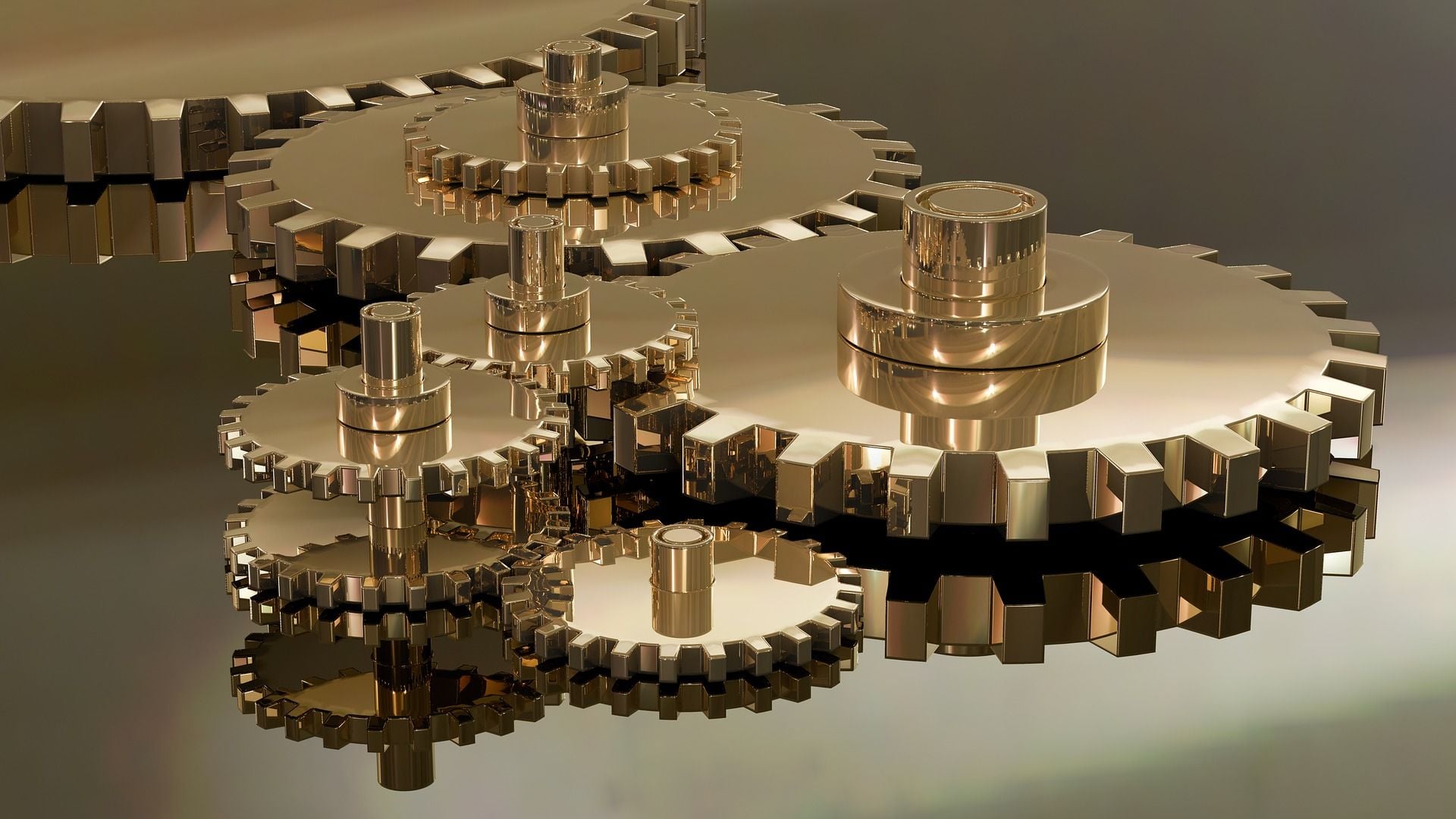2025.04.25
顧問税理士の費用相場は?依頼時にかかる費用の目安を解説
経営者や個人事業主の方は、税務処理を適切に行うために、顧問税理士の活用を検討されることが多いのではないでしょうか。その際には、「顧問税理士にどれくらいの費用がかかるのか」「自社の規模に適した相場はいくらなのか」といった疑問をもつでしょう
顧問税理士の費用は、企業規模や業務内容によって大きく異なります。個人事業主であれば月額1万円程度から、法人企業では2万円以上が一般的な相場となっています。ただし地域や税理士の経験、提供サービスの範囲によっても変動します。
この記事では、年商規模別の月額顧問料の相場から、決算申告や記帳代行にかかる追加費用、費用を抑えるコツまで詳しく解説します。自社に最適な税理士選びに役立つ情報をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
顧問税理士とは
顧問税理士とは、継続的に税務や会計に関するアドバイスを提供し、確定申告や税務調査対応などをサポートする専門家です。単発の依頼とは異なり、月額の顧問料を支払って長期的に契約する形態が一般的です。
顧問税理士の主な業務内容には、確定申告書の作成、帳簿の記帳代行、税務相談、税務調査への対応、経営アドバイスなどがあります。企業の規模や要望に応じて、サービス内容はカスタマイズされることが多いでしょう。
税理士と顧問契約を結ぶことで、定期的な税務サポートを受けられるのが大きなメリットです。特に、税務に関する専門知識が不足している経営者や個人事業主にとっては、税務リスクを軽減し、経営に集中できる環境を整えることができます。
また、金融機関からの融資を受ける際や、会社の成長フェーズにおいて資金調達が必要になったときにも、顧問税理士のアドバイスや財務書類の整備は大きな助けとなります。税務だけでなく、経営全般のアドバイザーとしての役割も期待できます。
顧問税理士に依頼する際の費用の業務別相場
顧問税理士に依頼する主な業務としては、月々の顧問業務の他に、決算申告業務や記帳代行などがあります。これらは、基本顧問料とは別に費用が発生することが多いため、あらかじめ把握しておきましょう。
決算申告業務にかかる費用
決算申告業務は、事業年度終了後に行う確定申告のための業務です。基本顧問料とは別に、年に一度発生する費用として計算されることが一般的です。
| 事業形態 | 決算申告費用の相場 |
|---|---|
| 個人事業主(青色申告) | 10,000円~50,000円 |
| 法人(小規模) | 50,000円~100,000円 |
| 法人(中規模) | 100,000円~150,000円 |
| 法人(大規模) | 150,000円~200,000円以上 |
決算申告業務には、決算書の作成、各種申告書の作成・提出、税額計算などが含まれます。特に法人の場合は、法人税、消費税、事業税、住民税など複数の税金に関する申告が必要になるため、個人事業主よりも高額になる傾向があります。
決算期前に顧問税理士と打ち合わせを行うことで、スムーズに決算作業を進めることができるため、単に申告書作成だけでなく、税務戦略的な視点からのアドバイスも含めた費用と考えるとよいでしょう。
また、決算申告費用は月額顧問料に含まれている場合もあります。契約前に「決算料」が別途必要かどうか、必ず確認することをおすすめします。
記帳代行サービスの費用相場
自社で経理処理を行わず、税理士事務所に記帳代行を依頼する場合、追加費用が発生します。記帳代行とは、日々の取引を仕訳し、帳簿をつける作業を税理士事務所が代行するサービスです。
| 月間仕訳数 | 記帳代行費用の相場(月額) |
|---|---|
| 50件未満 | 10,000円~20,000円 |
| 50~100件 | 20,000円~30,000円 |
| 100~200件 | 30,000円~40,000円 |
| 200件以上 | 40,000円~(要相談) |
記帳代行の費用は、主に月々の取引量(仕訳数)によって決まります。電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトを使用する場合と、従来の紙媒体での処理を行う場合でも費用が異なることがあります。
クラウド会計ソフトの活用で記帳代行費用を削減できる可能性があります。近年は、クラウド会計ソフトと連携したサービスを提供する税理士事務所も増えており、効率化によって費用を抑えられるケースもあります。
記帳代行を依頼する場合は、月々の取引量に応じた料金体系になっているか、追加料金が発生する条件は何かなど、細かい点も確認しておくとよいでしょう。
税務調査対応や特殊業務の費用
税務調査対応や事業承継、M&A対応などの特殊業務については、通常の顧問契約とは別に費用が発生することがほとんどです。
| 特殊業務の種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 税務調査対応 | 5万円~20万円/回 |
| 事業承継支援 | 30万円~100万円 |
| 会社設立支援 | 10万円~30万円 |
| 資金調達支援 | 調達額の1~3%程度 |
| 相続税申告 | 基礎控除後の課税財産の1~3%程度 |
税務調査対応については、調査の規模や日数によって費用が変わります。通常は半日~数日の立ち会いに対して、1日あたり数万円の費用がかかることが多いでしょう。
特殊事情の相談や複雑な税務には追加料金がかかることを理解しておきましょう。例えば、グループ法人の再編や国際税務に関する相談、複雑な組織再編などは、専門的なノウハウが必要となるため、通常の顧問料では対応できないケースが多いものです。
特殊業務を依頼する際は、事前に見積もりを取るようにしましょう。また、複数の税理士事務所から見積もりを取ることで、適正な価格かどうかの判断材料にもなります。
顧問税理士の契約タイプ別の費用相場
顧問税理士との契約には、主に「顧問契約」と「スポット契約」の2種類があります。
顧問契約の費用相場
顧問契約は、毎月一定の顧問料を支払い、継続的に税務面のサポートを受ける契約形態です。月額制の顧問料が基本となりますが、サービス内容によってはオプション料金が発生することもあります。
| 契約内容 | 費用体系 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 基本プラン | 月額1万円~3万円 | ・月次税務相談(電話/メール) ・簡易な経営相談 ・確定申告のアドバイス |
| スタンダードプラン | 月額3万円~5万円 | ・基本プランの内容 ・月次訪問(1回) ・決算申告書作成 ・経営アドバイス |
| プレミアムプラン | 月額5万円~10万円 | ・スタンダードプランの内容 ・月次訪問(複数回) ・記帳代行 ・節税対策 ・財務分析 |
顧問契約の大きなメリットは、安定したサポートを継続的に受けられることです。定期的な相談により、税務面のリスクを早期に発見できる点や、急な相談にも対応してもらいやすい点が挙げられます。
複数のプランから自社に適したサービス内容を選択することで、費用対効果を高められるでしょう。また、長期的な信頼関係を構築することで、より踏み込んだ経営のアドバイスを得られる可能性もあります。
なお、多くの税理士事務所では、顧問契約を締結する際に初期費用(契約料)が発生することがあります。これは、通常1~3ヶ月分の顧問料に相当する金額が目安となるため、予算に含めておくとよいでしょう。
スポット契約の費用相場とメリット
スポット契約は、確定申告や決算書作成など、必要なときだけ依頼する契約形態です。毎月の顧問料は発生しませんが、1回あたりの費用は顧問契約よりも高めに設定されることが一般的です。
| 依頼内容 | 個人事業主の費用相場 | 法人の費用相場 |
|---|---|---|
| 確定申告・決算書作成 | 10万円~15万円 | 15万円~20万円 |
| 税務相談(1時間) | 5千円~1万円 | 1万円~2万円 |
| 記帳指導(1回) | 1万円~2万円 | 2万円~3万円 |
| 会社設立支援 | – | 10万円~30万円 |
スポット契約のメリットは、必要なときだけ税理士に依頼できるため、年間トータルでの支出を抑えられる可能性がある点です。特に、創業間もない個人事業主や、安定した経営状態にある小規模事業者にとっては、コスト面で有利な選択肢となりえます。
年1回の確定申告だけ依頼するなら、スポット契約の方が経済的な場合もあることを覚えておきましょう。例えば、月商30万円程度の個人事業主が、毎月2万円の顧問料を支払うと年間24万円になりますが、確定申告だけをスポットで依頼すれば10万円程度で済むことも多くあります。
ただし、スポット契約では日常的な税務相談ができない点や、緊急時の対応が難しい点などのデメリットもあります。また、長期的な税務戦略の立案や継続的なフォローは期待しにくいため、事業の成長段階や複雑さに応じて、適切な契約形態を選ぶことが重要です。
顧問税理士の費用の変わる要因
顧問税理士の費用は、さまざまな要因によって変動します。
事業規模と売上
事業規模や売上高は、顧問料を決定する最も基本的な要素です。一般的に年商が大きくなるほど、税務処理も複雑になるため、顧問料も比例して高くなる傾向があります。
| 影響要因 | 費用への影響 |
|---|---|
| 年商の増加 | 顧問料が段階的に上昇 |
| 取引先数の増加 | 仕訳量増加による追加費用発生 |
| 事業所数の増加 | 複数事業所対応による料金上乗せ |
| 海外取引の有無 | 国際税務対応による割増 |
例えば、年商1億円の企業が2億円に成長した場合、取引量や経理処理の複雑さが増すため、顧問料が1万円程度上がることも珍しくありません。また、複数の事業を展開している場合や、海外取引がある場合も、追加料金が発生することが多いでしょう。
事業拡大を予定している場合は、顧問料の変動条件を事前に確認しておくことが大切です。将来的な費用の増加を見越した計画が立てられるだけでなく、成長に合わせた適切なサポート体制を整えることができます。
従業員数
従業員数の多さも、顧問料に影響を与える重要な要因の一つです。従業員が増えると、源泉所得税の納付や年末調整、社会保険関連の手続きなど、人事労務に関連する税務面の業務も増加します。
| 従業員数 | 基本顧問料への上乗せ目安 |
|---|---|
| 5名未満 | 基本料金のまま |
| 5~10名 | 5,000円~10,000円程度 |
| 11~30名 | 10,000円~20,000円程度 |
| 31名以上 | 20,000円~(要相談) |
また、月間の仕訳数(取引量)も顧問料に大きく影響します。特に、記帳代行を依頼している場合は、仕訳数に応じて段階的に費用が上がることが一般的です。
人材採用計画がある場合は、従業員増加に伴う顧問料の変動も考慮に入れるべきでしょう。特に、短期間で従業員数が大幅に増える予定がある場合は、税理士と事前に相談し、料金体系について確認しておくことをおすすめします。
業種や取引内容の専門性
事業の業種や取引内容の複雑さによっても、顧問料は変動します。一般的に、標準的な業種(小売業、サービス業など)に比べ、専門性の高い業種や特殊な税務処理が必要な業種では、顧問料が高くなる傾向があります。
| 業種・取引特性 | 顧問料への影響 |
|---|---|
| 建設業(工事進行基準など) | 基本料金の1.1~1.3倍 |
| 不動産業(賃貸・売買) | 基本料金の1.1~1.3倍 |
| 医療法人・社会福祉法人 | 基本料金の1.2~1.5倍 |
| 輸出入取引がある企業 | 基本料金の1.1~1.3倍 |
| 複数税率対応(飲食・小売など) | 基本料金の1.1~1.2倍 |
例えば、消費税の軽減税率対象となる飲食業や小売業では、複数税率への対応が必要なため、通常よりも顧問料が高くなることがあります。また、建設業では工事進行基準の適用や、現場ごとの原価管理が必要なため、税務処理が複雑になりやすいです。
業種特有の税務知識をもつ専門性の高い税理士を選ぶことで、リスク低減につながることを意識しましょう。業界特有の税務処理や節税対策に精通している税理士を選ぶことで、長期的にはコスト以上のメリットを得られることもあります。
顧問税理士の費用を抑えるための効果的な方法
顧問税理士の費用を抑えつつ、必要なサポートを受けるためのポイントを解説します。コスト削減と業務効率化を両立させる方法を理解しておきましょう。
自社で対応できる業務の範囲を広げる
税理士に依頼する業務範囲を見直し、自社で対応できる部分は内製化することで、顧問料を抑えることができます。特に記帳代行は、自社で行うことでかなりのコスト削減が可能です。
| 自社対応可能な業務 | 削減できる費用の目安 |
|---|---|
| 日常的な記帳業務 | 月額1万円~3万円 |
| 経費精算・管理 | 月額5千円~1万円 |
| 請求書・領収書の整理 | 月額5千円~1万円 |
| 給与計算・年末調整 | 月額1万円~2万円 |
クラウド会計ソフトを導入することで、経理業務の効率化とコスト削減を同時に実現できます。クラウド会計ソフトは、初心者でも比較的扱いやすく、銀行口座やクレジットカードとの連携機能により、自動的に仕訳を作成することもできます。
クラウド会計ソフトの活用と基本的な経理知識の習得で、大幅なコスト削減ができる可能性があります。例えば、月間の記帳代行費用が2万円かかっていた場合、クラウド会計ソフト(月額数千円程度)を導入して自社対応することで、年間20万円近くの削減効果が見込めます。
ただし、バランスを考えることが大切です。基本的な入力作業は自社で行い、チェックや申告書作成は税理士に依頼するといった役割分担も効果的でしょう。
オンラインサービスの活用
訪問頻度を減らし、オンラインやリモートでのやり取りを中心にすることで、顧問料を抑えることができます。最近では、完全オンライン対応の税理士事務所も増えてきており、地域に縛られず、全国から選ぶことも可能になっています。
| コミュニケーション方法 | コスト削減効果 |
|---|---|
| 訪問中心(月1回以上) | 基本料金 |
| 訪問(四半期に1回)+オンライン | 基本料金の0.8~0.9倍 |
| 完全オンライン対応 | 基本料金の0.7~0.8倍 |
Zoom、Teams、Google Meetなどのビデオ会議ツールを活用すれば、対面での相談と変わらないクオリティで、コミュニケーションをとることができます。また、クラウドストレージを使った資料共有や、チャットツールでの日常的なやり取りも効率的です。
デジタルツールを活用して効率的なコミュニケーション体制を構築することで、コスト削減と利便性向上の両立が可能です。特に、地方在住の経営者や、多忙で事務所訪問の時間が取りにくい方にとっては、オンライン対応の税理士は大きなメリットとなるでしょう。
ただし、完全オンライン対応の場合は、緊急時の対応力や、きめ細かなサポートが得られるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。また、税務調査などの際には対面での立ち会いが必要になることもあるため、その点も考慮して選ぶとよいでしょう。
複数の税理士事務所から見積もりを取る
複数の税理士事務所から見積もりを取り、比較検討することも効果的な方法です。同じ条件でも、税理士事務所によって料金体系は大きく異なることがあるため、比較することで適正な価格を見極めることができます。
見積もりを依頼する際は、以下の情報を明確に伝えることで、より正確な見積もりを取ることができます。
- 事業形態(個人/法人)と年商規模
- 従業員数
- 月間の取引量(仕訳数の目安)
- 依頼したい業務内容(記帳代行の有無など)
- 希望する訪問頻度やコミュニケーション方法
最低でも3社以上から見積もりを取ることで、料金の適正さを判断できるようになります。ただし、単に価格の安さだけで判断するのではなく、提供されるサービス内容や専門性、相性なども含めて総合的に検討することが大切です。
また、見積もり依頼の際には、「追加料金が発生する条件」や「契約後に料金が変動する可能性」についても確認しておくとよいでしょう。後になって、予想外の費用が発生するリスクを避けることができます。
まとめ
顧問税理士の費用相場は、事業形態や規模、依頼する業務内容によって大きく異なります。個人事業主であれば月額1万円~3万円程度、法人企業では2万円~5万円程度が一般的な相場となっていますが、地域や専門性によっても変動します。
費用を抑えるためには、自社で対応できる業務の範囲を広げる、オンラインでのコミュニケーションを活用する、複数の税理士事務所から見積もりを取るなどの方法が効果的です。ただし単に費用の安さだけで選ぶのではなく、専門性やコミュニケーションの取りやすさ、追加料金の明確さなども総合的に判断することが大切です。
自社のニーズに合った顧問税理士を見つけるためには、現在の課題や将来の展望を整理し、それに適した専門性やサポート体制をもつ税理士を探すことをおすすめします。まずは、複数の税理士との初回相談を通じて、相性のよい税理士を見つけることから始めてみてください。
最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン
税理士選びと同様に重要なのが、事業資金の調達方法です。顧問税理士に依頼する費用も含め、事業運営には安定した資金繰りが欠かせません。急な資金需要や設備投資、事業拡大のための現金が必要な場合は、スピーディーな審査が特徴のビジネスローンも検討されてはいかがでしょうか。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。