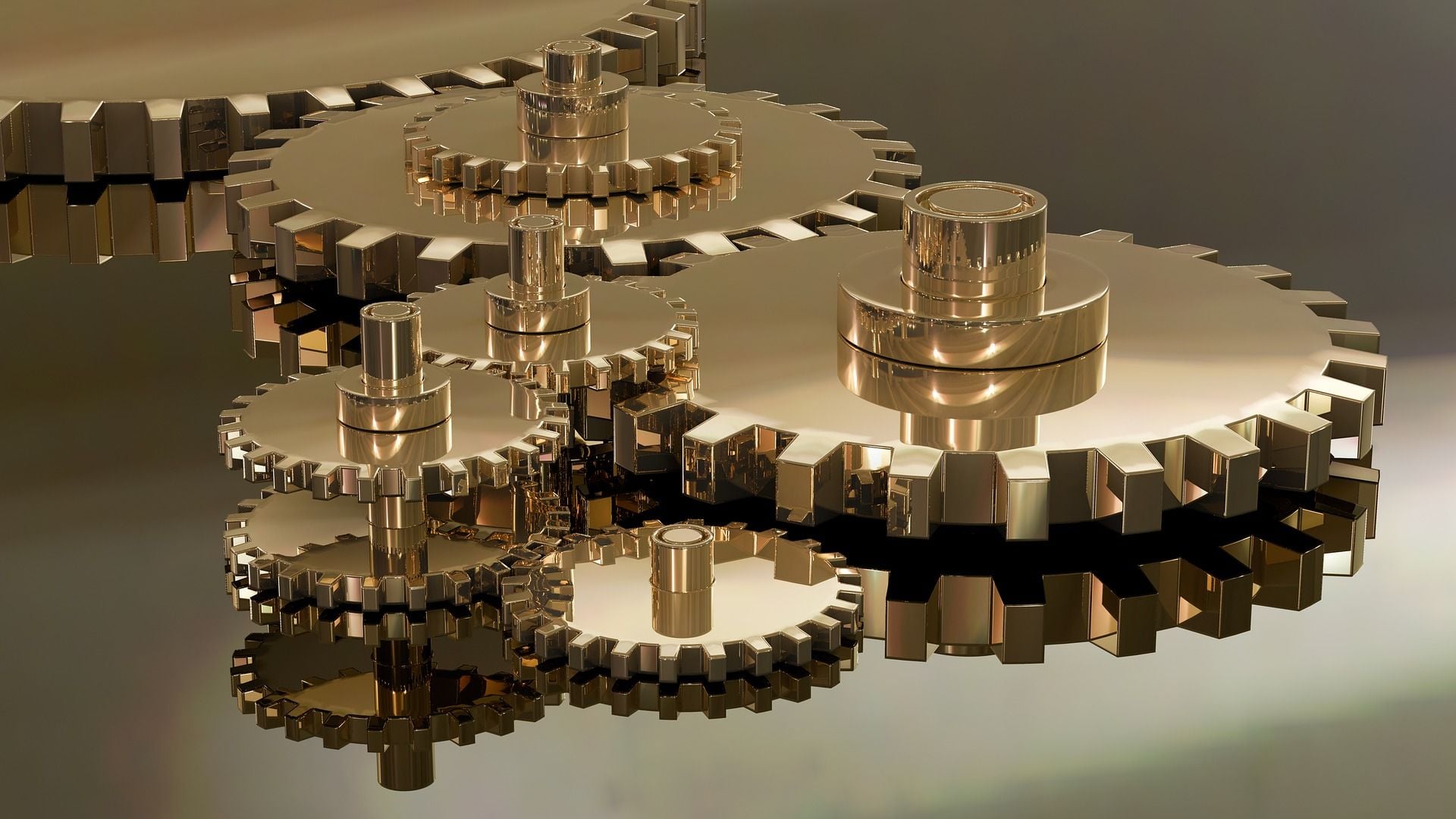2025.04.25
M&Aで使える補助金は?事業承継・引継ぎ補助金を分かりやすく解説!
M&Aや事業承継を検討されている中小企業のオーナーの方々にとって、資金面が課題になることはよくあります。M&Aには専門家への相談費用や設備投資など、さまざまな費用が必要となりますが、「事業承継・引継ぎ補助金」という国の支援制度を活用することで、これらの費用負担を軽減できる可能性があります。
本記事では、M&Aで活用できる事業承継・引継ぎ補助金の概要や支援内容、申請方法などを詳しく解説します。最大2000万円の補助が受けられる制度もあり、採択率は約60%と比較的高いことが特徴です。M&Aや事業承継を成功させるためのコスト削減方法の一つとして、ぜひ参考にしてください。
事業承継・引継ぎ補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業や個人事業主がM&Aや事業承継を円滑に進めるために国が用意した支援制度です。
この補助金は、後継者不在に悩む中小企業の事業存続と、それによる地域経済や雇用の維持を目的としています。M&Aにおけるさまざまな場面で活用でき、専門家への相談費用から設備投資まで幅広い支援が受けられるのが特徴です。
事業承継・引継ぎ補助金は、複数の支援類型に分かれており、M&Aの各段階に応じて適切な支援を受けることができます。特に、買い手側は最大2000万円の補助を受けられる場合もあるため、M&Aを検討する企業にとって大きな資金的メリットとなります。
補助金の目的
経営者の高齢化が進む中、後継者不在による廃業が社会問題となっています。中小企業庁の調査によれば、今後10年の間に約245万人の中小企業経営者が70歳を超え、そのうち約半数が後継者未定という状況です。
こうした背景から、国は事業承継・引継ぎ補助金を通じて、第三者への事業承継(M&A)を積極的に支援しています。この制度は、単なる資金援助ではなく、日本経済を支えている中小企業の存続を図る重要な政策の一つです。
事業承継・引継ぎ補助金は、年々拡充されており、2025年度にはPMI推進枠(M&A後の統合支援=Post Merger Integration)が新設されるなど、M&Aの各段階に対応した支援体制が整えられています。
対象となる企業
事業承継・引継ぎ補助金の対象となるのは、原則として中小企業基本法で定義される中小企業者および個人事業主です。具体的な規模要件は業種によって異なりますが、一般的には、以下の条件を満たす企業が対象となります。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
また、申請には以下のような条件もあります。
- 日本国内に本社を有すること
- 風俗営業等の業種でないこと
- 申請時に事業を営んでいること
- 暴力団等の反社会的勢力でないこと
特に重要なのは、補助金申請の前に実施したM&A関連費用は対象外となるため、補助金の申請タイミングを適切に計画しておく必要があります。
M&Aに使える補助金の種類
事業承継・引継ぎ補助金は、M&Aのプロセスに応じて、いくつかの支援類型に分かれています。
事業承継促進枠
事業承継促進枠は、M&Aや事業承継後に新たな取り組みを行う際の費用を支援する制度です。主に設備投資や販路開拓、人材育成などの費用が対象となります。
支援内容は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 設備投資、システム費用、人件費、販路開拓費、広告宣伝費など |
| 補助金額 | 通常枠:最大600万円 上乗せ枠:最大800万円(賃上げ計画の場合) |
| 補助率 | 中小企業:1/2(一部の条件で2/3) 小規模事業者:2/3 |
事業承継促進枠の最大の特徴は、M&A後の新たな事業展開に必要な幅広い費用をカバーできる点です。ただし、申請にあたっては認定支援機関(税理士、公認会計士、金融機関など)の確認を受けた、経営革新計画の策定が必要となります。
この支援類型は、M&A後の事業成長に向けた投資を検討している企業に特におすすめです。事業拡大のための設備投資や新規採用なども補助対象となるため、M&A後の成長戦略と合わせて活用を検討するとよいでしょう。
専門家活用枠
専門家活用枠は、M&Aの検討から成約までに必要となる専門家への依頼の費用を補助する制度です。仲介手数料やデューデリジェンス(財務調査)費用など、M&A成立に向けたさまざまな専門家経費が対象となります。
| 区分 | 補助上限額 | 補助率 | 主な対象費用 |
|---|---|---|---|
| 買い手側 | 通常:最大800万円 特例:最大2000万円 |
2/3 | 仲介手数料、FA費用、DD費用、株価算定費用など |
| 売り手側 | 最大800万円 | 1/2~2/3 | 仲介手数料、FA費用、DD費用、株価算定費用など |
専門家活用枠の最大の魅力は、買い手側が特例を適用すると最大2000万円の補助金が受けられる点です。
M&Aには多額の専門家費用がかかるため、この補助金を活用することで、特に初めてM&Aに取り組む中小企業の資金的な負担を大きく軽減できます。専門家を十分に活用することで、M&Aのリスクを最小化しながら、最適な条件での成約を目指せるでしょう。
PMI推進枠
PMI(Post Merger Integration)推進枠は、2025年度から新設される支援類型で、M&A後の企業統合プロセスを支援する制度です。M&A成立後の統合作業は、成功の鍵となる重要な過程であるため、この支援類型は非常に重要です。
| 区分 | 補助上限額 | 補助率 | 対象費用 |
|---|---|---|---|
| 専門家費用 | 最大150万円 | 1/2 | PMIコンサルティング費用、統合支援費用など |
| 設備投資費用 | 通常:最大800万円 賃上げ:最大1000万円 |
1/2~2/3 | システム統合費用、設備投資費用など |
PMI推進枠の大きな特徴は、M&A後の統合プロセスに特化した支援を受けられる点です。M&A後に、システム統合や事業運営の効率化を図る際に、大きな資金的サポートを受けることができます。
申請にあたっては、具体的なPMI計画書の提出が必要となります。M&A後に発生するシナジー効果を最大化するための計画を、明確にすることが重要です。また、賃上げ計画を含める場合は、補助上限額が200万円アップするため、従業員の処遇改善も検討する価値があります。
廃業・再チャレンジ枠
廃業・再チャレンジ枠は、事業承継の選択肢として廃業を選んだ場合や、M&A後に一部事業を廃止する場合の費用を支援する制度です。この支援類型は、スムーズな事業整理を促進するために設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大150万円 |
| 補助率 | 中小企業:1/2 小規模事業者:2/3 |
| 対象費用 | 廃業登記費用、在庫処分費用、原状回復費用、店舗撤去費用など |
廃業・再チャレンジ枠の重要な点は、廃業にともなう様々な費用負担を軽減できることです。特に店舗の原状回復の費用や在庫処分の費用などは、予想以上にかかることが多いため、この補助金は大きな助けとなります。
申請にあたっては、認定支援機関の確認を受けた廃業計画の策定が必要です。また、単なる廃業ではなく、新たなチャレンジや残された従業員の雇用確保などの観点も重視されるため、廃業後の計画も含めて検討することが大切です。
M&Aに使える補助金の申請手順
事業承継・引継ぎ補助金を利用するためには、申請手順に従って申し込む必要があります。
申請前の準備
補助金申請の前には、いくつかの重要な準備が必要です。まずは公募要領を確認し、自社が申請要件を満たしているかを確認しましょう。
申請に必要な主な準備は、以下の通りです。
- gBizIDプライムアカウントの取得(電子申請に必須)
- 事業計画書の作成(事業承継促進枠、廃業・再チャレンジ枠の場合は認定支援機関の確認が必要)
- 見積書などの費用の根拠となる資料の準備
- 直近の決算書や確定申告書の用意
- 会社の履歴事項全部証明書(法人の場合)
特に重要なのは、gBizIDプライムの取得は2週間程度かかるため、余裕をもって準備することです。また、認定支援機関への相談も早めに行うことで、より充実した内容の事業計画書の作成が可能になります。
専門家活用枠の場合は、M&A専門家との契約内容や見積書、専門家の実績を示す資料なども必要となります。これらの資料は申請の評価に大きく影響するため、丁寧に準備しましょう。
申請から採択、補助金受給まで
補助金の申請から受給までの基本的な流れは、以下の通りです。
- 公募要領の確認と申請要件の確認
- 認定支援機関への相談(事業承継促進枠・廃業・再チャレンジ枠の場合)
- gBizIDプライムアカウントの取得
- 電子申請システム「jGrants」での申請
- 審査・採択結果の通知
- 交付決定後に事業実施
- 実績報告書の提出
- 補助金額の確定・入金
申請から採択までは、通常1~2ヶ月程度かかります。補助対象となる事業は、必ず交付決定後に開始することが原則です。交付決定前に発生した費用は、補助対象外となるため注意が必要です。
実績報告書の提出は、事業完了後30日以内、もしくは補助事業終了日のいずれか早い日までに行う必要があります。実績報告書には、発注書、納品書、請求書、支払証明など多くの証憑書類の添付が求められるため、事業実施中から書類を整理しておくことが重要です。
グループ企業申請の特例
事業承継・引継ぎ補助金では、グループ企業が共同で申請できる特例があります。この制度は、グループ内の複数の企業が連携してM&Aを進める際に利用すると効果的です。
グループ企業申請の主なポイントは、以下の通りです。
- 親会社1社と子会社最大4社まで、計5社までの連名申請が可能
- それぞれの会社が補助対象要件を満たす必要がある
- 親会社が代表して申請を行う
- グループ全体での補助上限額は通常と同じ(合算されない)
グループ企業申請を活用するメリットは、複数企業が連携したM&A戦略を実行できる点です。例えば、親会社がM&Aの中心となり、各子会社がそれぞれの事業領域で、統合後の事業強化を図るといったアプローチが可能になります。
ただし、グループ企業申請の場合も補助上限額は通常と同じであり、企業数に応じて増額されるわけではありません。グループ内での補助金の配分については、事前に十分な検討が必要です。
事業承継・引継ぎ補助金を申請する際に知っておくべきポイント
事業承継・引継ぎ補助金を最大限に活用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
採択率を高めるためのポイント
事業承継・引継ぎ補助金の採択率は、約60%と比較的高いものの、確実に採択されるわけではありません。ただし、採択率を高めるためのポイントがいくつかあります。
採択率を高める主なポイントは、以下の通りです。
- 中小企業会計要領や中小企業会計基準に準拠した財務諸表の整備
- 経営力向上計画や事業継続力強化計画などの認定取得
- 具体的かつ実現可能な事業計画の策定
- 賃上げ計画の策定(加点要素となる)
- 事業承継後の明確な成長戦略の提示
- 地域経済や雇用への貢献度を明確に示す
特に、経営力向上計画などの認定取得は審査で有利になるため、申請前に準備しておくことをおすすめします。また、専門家活用枠の場合は、選定する専門家の実績や専門性も重要な評価ポイントとなります。
申請書の記載内容も重要です。抽象的な表現ではなく、具体的な数値目標や実施スケジュール、投資計画などを明確に示すことで、審査員に事業の実現する可能性や事業のもつ影響を理解してもらいやすくなります。
申請時の失敗例
事業承継・引継ぎ補助金の申請において、よくある失敗例とその対策をご紹介します。これらを避けることで、スムーズな申請と採択確率の向上につながります。
| よくある失敗例 | 対策 |
|---|---|
| 補助対象外の費用を計上 | 公募要領で対象経費を事前に確認し、不明点は事務局に問い合わせる |
| 申請書の記載不備・証憑不足 | チェックリストを作成し、提出前に複数人でチェックする |
| 事業計画の具体性不足 | 数値目標や実施スケジュールを明確に記載する |
| 交付決定前に事業開始 | 交付決定通知を受けるまで発注や契約を行わない |
| 申請期限ギリギリの提出 | 余裕を持ったスケジュールで準備を進める |
最も多い失敗は、補助対象外の費用を計上してしまうことです。例えば、汎用性の高い備品や消耗品、用途が明確でない外注費などは補助対象外となる場合が多いため、事前に対象経費を確認することが重要です。
また、申請期限直前の駆け込み申請も避けるべきです。システムの混雑や予期せぬトラブルで申請できないリスクがあります。最低でも、締切の1週間前には申請を完了させるようにしましょう。
併用できる税制優遇措置
事業承継・引継ぎ補助金と併用できる税制優遇措置もあります。これらを組み合わせることで、M&Aにかかるコストをさらに抑えることができます。
主な税制優遇措置は、以下の通りです。
| 制度名 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 事業承継税制 | 非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除 | 最大で相続税・贈与税の100%が猶予される |
| 経営資源集約化税制 | M&Aに伴う設備投資等の即時償却または税額控除 | 投資額の10%の税額控除または即時償却が可能 |
| 登録免許税・不動産取得税の軽減 | M&Aに伴う不動産取得にかかる税金の軽減 | 通常税率の1/2~1/6に軽減される |
特に、経営資源集約化税制はM&A後の投資に大きなメリットがあります。この制度は、経営力向上計画の認定を受けたうえで、M&A後に行う設備投資などについて税制優遇を受けられるものです。
これらの税制優遇措置は適用要件が複雑なため、税理士などの専門家に相談しながら活用を検討することがおすすめです。補助金と税制優遇を組み合わせることで、M&Aにかかる総コストを大幅に削減することが可能になります。
M&A補助金に関するよくある質問
事業承継・引継ぎ補助金について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q:個人事業主でも申請できますか?
A:はい、個人事業主も申請可能です。ただし、事業実態があり、青色申告を行っていることが条件となります。廃業・再チャレンジ枠や、事業承継促進枠は個人事業主の方も多く活用しています。
Q:創業間もない企業でも申請できますか?
A:基本的には申請可能ですが、一部の支援類型では、一定期間の事業実績が求められる場合があります。特に専門家活用枠では、買い手企業として申請する場合、事業の安定性が審査されるため、ある程度の事業実績があることが望ましいです。
Q:どのような業種が対象外となりますか?
A:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める「性風俗関連特殊営業」、公序良俗に反する事業、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業などは対象外となります。また、宗教法人、学校法人、医療法人なども対象外です。
既に進行中のM&A案件でも申請可能かについては、契約締結前であれば申請可能な場合があります。ただし、補助金の交付決定前に発生した費用は対象外となるため、タイミングには注意が必要です。
Q:申請から交付決定までどれくらい時間がかかりますか?
A:通常、申請から交付決定までは1~2ヶ月程度かかります。ただし、申請時期や申請件数によって変動することがあります。特に公募締切直前は申請が集中するため、余裕をもって申請することをおすすめします。
Q:一度不採択になった場合、再申請は可能ですか?
A:可能です。不採択の理由を確認し、計画内容を改善したうえで、次回の公募で再申請することができます。不採択理由は、問い合わせることで教えてもらえる場合がありますので、事務局に確認することをおすすめします。
Q:複数の支援類型に同時に申請することはできますか?
A:基本的には可能ですが、同一の経費を複数の支援類型で申請することはできません。例えば、専門家活用枠とPMI推進枠のように、M&Aの異なる段階に対応する支援類型であれば同時に申請できる場合があります。ただし、具体的なケースについては事務局に確認することをおすすめします。
Q:補助金で購入した設備などの処分制限はありますか?
A:はい、補助金で取得した財産には、一定期間の処分制限があります。取得価格が50万円以上の機械装置等は、原則として法定耐用年数の間、無断で売却や廃棄などの処分はできません。処分する場合は事前に承認を受け、場合によっては補助金の一部返還が必要になることがあります。
Q:事業計画通りに実施できなかった場合はどうなりますか?
A:事業計画と大きく異なる実施内容となった場合、補助金の減額や返還を求められる可能性があります。やむを得ない事情で計画を変更する場合は、事前に事務局に相談し、計画変更の手続きを行うことが重要です。
Q:補助金の事業が完了した後の書類保存期間はどれくらいですか?
A:補助事業に関する書類は、事業完了後5年間保存する義務があります。保存が必要な書類には、見積書、発注書、請求書、支払証明書類、納品書、成果物などが含まれます。これらは、後日の検査で提示を求められる場合があります。
まとめ
事業承継・引継ぎ補助金は、M&Aや事業承継に取り組む中小企業・個人事業主にとって、非常に有用な支援制度です。事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠など、M&Aの各段階に応じた支援類型が用意されており、最大2000万円の補助金が受けられる可能性があります。
補助金を活用するためには、事前準備が重要です。gBizIDの取得や認定支援機関への相談、具体的な事業計画の策定など、余裕をもって準備を進めましょう。また、税制優遇措置と組み合わせることで、M&Aにかかる総コストをさらに軽減できます。M&Aを検討している方は、ぜひ事業承継・引継ぎ補助金の活用を検討してみてください。
最短即日融資!HTファイナンスヒューマントラストのビジネスローン
M&Aや事業承継を検討する際、補助金だけでは資金が足りない場合や、補助金が支給されるまでのつなぎ資金が必要な場合も多いでしょう。そのようなときには、HTファイナンスのビジネスローンがお役に立ちます。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。