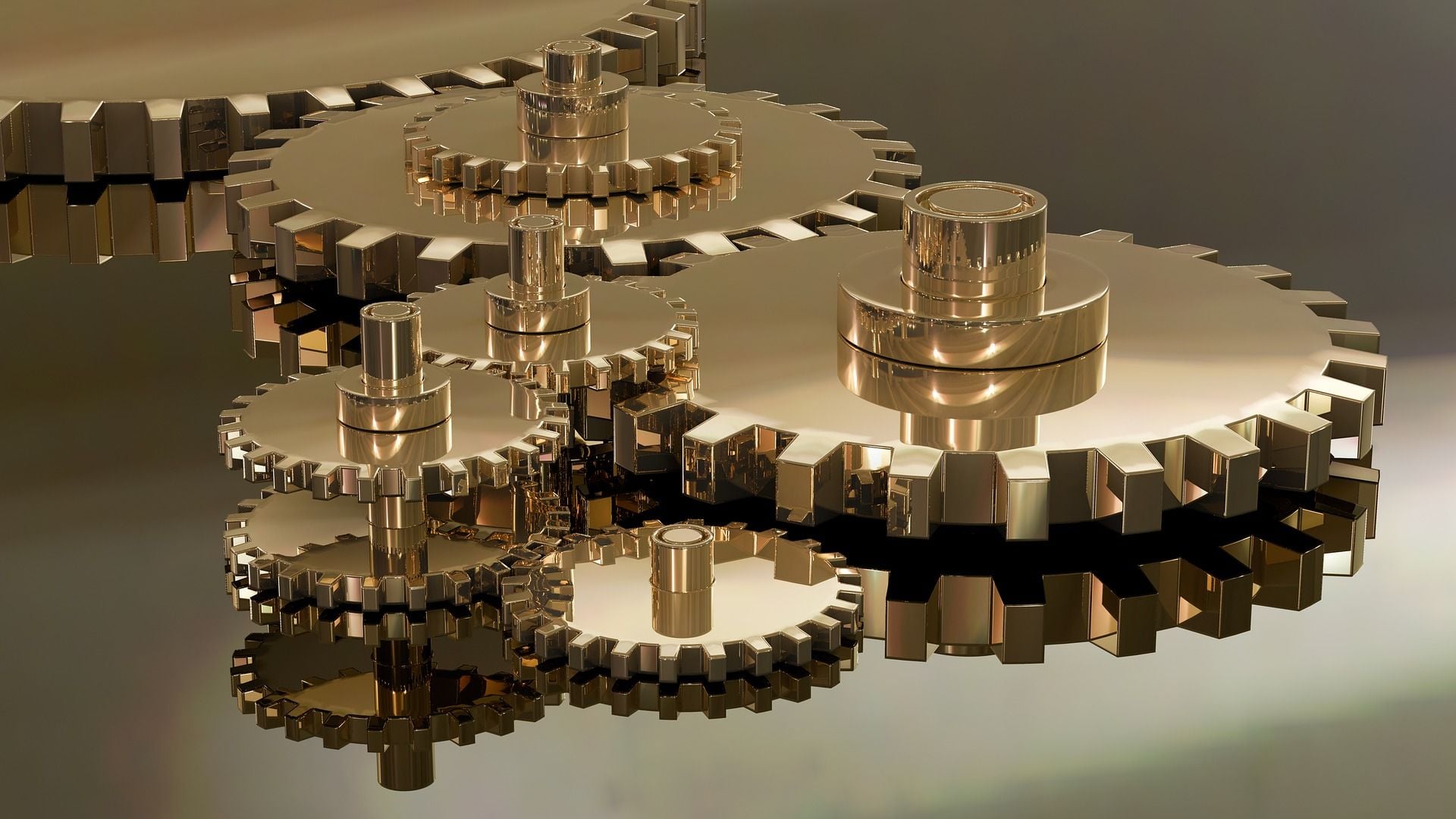2025.04.25
法人の借入限度額はいくら?適切な金額の計算方法も解説
「これからの事業拡大に向けて融資を検討しているけれど、いったいどのくらいの金額なら借入可能なのだろう」と悩んでいませんか?法人が資金調達を行う際、その調達額の上限は金融機関が設定しますが、この限度額がどのように決まるのか、自社ではいくらまで借入可能なのかを把握しなければなりません。
本記事では、法人の借入限度額について、業種別の目安、具体的な計算方法まで詳しく解説します。さらに、借入限度額を増やすための実践的なポイントもお伝えします。
借入限度額とは
借入限度額とは、金融機関が企業に対して融資可能と判断する最大金額のことです。これは、企業の返済能力や信用力に基づいて設定されます。
この限度額は「与信枠」とも呼ばれ、企業が金融機関から借り入れられる上限を示しています。金融機関は企業の財務状況や事業内容から判断し、返済可能と考えられる範囲内で限度額を設定します。
適切な借入限度額を把握することは、資金調達計画を立てるうえで非常に重要です。自社の借入可能額を正確に理解していれば、無理のない返済計画を立てられるだけでなく、金融機関との交渉においても現実的な要求ができるようになります。
借入限度額を決める4つのポイント
金融機関が企業の借入限度額を決定する際は、主に以下の4つのポイントを重視します。それぞれの要素がどのように影響するのかみていきましょう。
返済能力(収益力)
借入限度額を決めるうえで最も重要な要素は、企業の返済能力、つまり収益力です。安定した売上と利益を継続的に出せる企業ほど、高い借入限度額が設定されます。
金融機関は、過去3〜5年の財務諸表を分析し、特に経常利益の推移に注目します。利益率が高く、安定した成長を示している企業は、返済能力が高いと判断されます。
また、キャッシュフローの状況も重要視されます。売上が好調でも、現金の流れが悪い企業は返済リスクが高いと判断され、借入限度額が低く設定されることがあります。
安定したキャッシュフローを示せることが、高い借入限度額を得るための基本条件となります。
現在の借入状況(借入依存度)
既存の借入残高も、借入限度額に大きく影響します。すでに多額の借入がある企業は、追加の融資に対する限度額が低く設定される傾向があります。
金融機関は、「借入依存度」という指標を重視します。これは、総資本に占める借入金の割合で、この数値が高いほど財務面のリスクが高いと判断されます。一般的に、借入依存度が30%を超えると警戒されることが多くなります。
また、月々の返済額と売上高の比率も大切です。月々の返済額が売上高の15%を超えると、返済負担が重いと判断される傾向にあります。
既存借入の返済状況も審査で確認されます。過去に返済遅延があると、新規の借入限度額は大幅に制限されることがあります。
業種の特性(月商倍率)
借入限度額は、業種によっても大きく異なります。これは、業種ごとに資金回転率や必要な設備投資額が異なるためです。
製造業は設備投資額が大きいため、比較的高い借入限度額が設定されることがあります。一方、サービス業は人件費比率が高く設備投資が少ないため、限度額が低めに設定される傾向があります。
金融機関は、「月商倍率」という考え方を用いることがあります。これは、月平均売上高の何倍まで融資できるかを示す指標です。例えば、小売業では月商の3〜4倍、製造業では4〜6倍といった具合に、業種ごとの目安があります。
業界平均と比較した財務状況も審査で重視されます。同業他社と比べて収益性や安全性が高ければ、より高い借入限度額が設定される可能性があります。
自己資金の金額(特に創業時)
特に創業融資や事業拡大時には、経営者が投入する自己資金の額が借入限度額に大きく影響します。自己資金が多いほど、経営者の事業への本気度が高いと評価されます。
一般的に、創業融資では総事業費の3分の1程度の自己資金があることが望ましいとされています。例えば、3,000万円の事業を始める場合、1,000万円の自己資金があれば、残りの2,000万円を融資で調達できる可能性が高まります。
自己資本比率も重要な指標としてみられます。これは、総資本に占める自己資本の割合で、この数値が高いほど財務的に安定していると判断され、借入限度額も高く設定される傾向があります。
経営者自身の信用力も無視できません。個人の信用情報や過去の経営実績、保有資産なども審査の対象となります。
借入限度額の具体的な計算方法
借入限度額を具体的に計算する方法は、いくつかあります。ここでは代表的な3つの計算方法を解説しますが、自社の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
月商倍率方式による計算
月商倍率方式は、最もシンプルな計算方法で、特に運転資金の借入限度額を算出する際によく用いられます。計算式は以下の通りです。
借入限度額=平均月商×(1〜6ヶ月)
例えば、月の平均売上が500万円の企業の場合、業種によって異なりますが、一般的には500万円×3ヶ月=1,500万円程度が借入限度額の目安となります。
業種ごとの一般的な月商倍率は、以下のようになっています。
| 業種 | 一般的な月商倍率 | 借入限度額の目安 |
|---|---|---|
| 小売業 | 1〜3ヶ月 | 低め〜中程度 |
| サービス業 | 2〜4ヶ月 | 中程度 |
| 卸売業 | 3〜5ヶ月 | 中程度〜高め |
| 製造業 | 4〜6ヶ月 | 高め |
過去6ヶ月〜1年の平均月商を用いることで、より安定した数値に基づいた計算ができます。ただし、季節変動が大きい業種では、その影響を考慮する必要があります。
収益面による計算
収益面からの計算方法は、企業の利益に基づいて借入限度額を算出します。この方法は、中長期的な借入や設備投資のための資金調達に適しています。計算式は以下の通りです。
借入限度額=経常利益(3年平均)×50%×(5〜7年)
例えば、過去3年間の平均経常利益が1,000万円の企業の場合、1,000万円×50%×6年=3,000万円が借入限度額の目安となります。
この計算方法のポイントは、年間返済可能額を経常利益の50%程度と設定している点です。これは、事業を継続していくことを考慮したもので、利益の全てを返済に充てるのではなく、一部を内部留保や配当に回すことを想定しています。
返済期間の設定も重要です。一般的に運転資金は5年程度、設備資金は7年程度が目安となりますが、設備の耐用年数や資金の用途によって、適切な期間は変わります。
簡易キャッシュフロー方式による計算
簡易キャッシュフロー方式は、企業の実質的な資金生成力に基づいて借入限度額を算出する方法です。計算式は以下の通りです。
借入限度額=(税引後利益+減価償却費)×5〜10年
例えば、税引後利益が700万円、減価償却費が300万円の企業の場合、(700万円+300万円)×7年=7,000万円が借入限度額の目安となります。
この方法の特徴は、実際のキャッシュフローを基準にしている点です。減価償却費は、実際には現金支出を伴わないため、これを利益に加算することで、実質的な資金生成力を測ります。
業種や事業内容に応じた適切な倍率選択が重要です。設備投資が多い製造業では7〜10年、比較的軽装備のサービス業では5〜7年程度が一般的です。
業種別・目的別の一般的な借入限度額目安
借入限度額は、業種や資金使途によって大きく異なります。ここでは、一般的な目安を紹介しますので、自社の状況を判断する参考にしてください。
創業融資における借入限度額
創業時の融資は、実績がない中での判断となるため、慎重に審査されます。特に、日本政策金融公庫の創業融資の目安に注目します。
創業融資の平均的な借入額は700〜900万円程度ですが、事業計画の内容や創業者の経験、自己資金の額によって大きく変動します。特に無担保・無保証人での融資では、上限が設けられていることが多くあります。
法人設立時の借入限度額は、一般的に次のような要素で決まります。
- 創業者の自己資金(総事業費の1/3程度が望ましい)
- 創業者の業界経験と実績
- 事業計画の実現可能性と市場性
- 担保・保証人の有無
創業計画を綿密に作成することが、高い借入限度額を得るためのポイントです。特に、売上予測と必要経費の積算の根拠を明確にすることが大切です。
運転資金における借入限度額
運転資金は、企業の日常的な事業活動を支えるための資金で、仕入れや人件費、家賃などの支払いに充てられます。
目安として、月商の約3ヶ月分が運転資金の借入限度額とされることが多いですが、業種によって異なります。在庫を多く抱える小売業や製造業では3〜4ヶ月分、サービス業では2〜3ヶ月分が一般的です。
運転資金の必要額は、以下の式でも計算できます。
必要運転資金=売上債権+棚卸資産-仕入債務
この計算式は、資金繰りのサイクルを考慮したもので、現在の財務状況から必要な運転資金を算出します。売上債権(売掛金など)と在庫が多く、仕入債務(買掛金など)が少ないほど、必要な運転資金は増えます。
資金繰り表の作成と分析を行うことで、より精度良く運転資金の必要額を把握できます。特に、季節変動がある業種では、月別の資金繰り予測が非常に重要です。
設備資金における借入限度額
設備資金は、工場や店舗の建設、機械設備の購入など、長期的な事業基盤を整えるための資金です。
一般的に、簡易キャッシュフロー(税引後利益+減価償却費)の7〜10倍程度が設備資金の借入限度額の目安となります。ただし、設備の種類や業種によって変動します。
設備資金の借入では、導入する設備自体が担保となることが多いため、担保価値も重要な要素です。一般的に、設備価格の70〜80%程度が融資上限となることがあります。
また、設備投資による収益改善効果も審査のポイントです。新規設備導入によって利益率が向上する見込みがあれば、より高い限度額での融資が可能になることがあります。
設備投資の投資対効果を具体的な数字で示すことが、高い借入限度額を獲得するコツです。導入後の生産性向上や、経費削減効果を明確に説明できると有利です。
借入限度額を増やすための実践的な方法
借入限度額を増やすには、金融機関からの信頼を高め、返済能力をアピールすることが重要です。
自己資金を増やす
自己資金は、経営者の事業への本気度の現れる指標です。自己資金を増やすことで、金融機関からの信頼を得やすくなります。
具体的な方法としては、役員報酬を一時的に抑えて、その分を資本金や資本準備金として会社に入れる方法があります。これにより自己資本比率が向上し、財務基盤を強化することにつながります。
また、不要な資産を売却して現金化し、それを自己資金として投入する方法も効果的です。具体的には、遊休不動産や使用頻度の低い設備などを見直すことが考えられます。
利益の内部留保を増やすことも、長期的な視点では重要です。配当を抑え、利益を会社に蓄積することで、徐々に自己資本も大きくなります。
明確な事業計画書を作成する
金融機関は、貸し出したお金が確実に返済されるかを最も重視します。その判断材料として見られる事業計画書を、説得力のあるように仕上げることは非常に重要です。
事業計画書には、市場分析、競合状況、売上予測、経費計画、資金繰り表など具体的な数字を盛り込みましょう。特に、売上予測は根拠を明確にし、過大な見積もりは避けるべきです。
借入金の使途と、それによって得られる効果を明確に示すことも重要です。例えば「この設備投資により生産効率が30%向上し、年間500万円のコスト削減につながる」といった、具体的な効果を示すことができると説得力が増します。
返済計画の実現可能性を、具体的に示すことも大切です。過去の実績を踏まえた無理のない計画を立て、最悪のケースでも返済できる余裕をもたせましょう。
業績好調時に申し込む
融資の申込みタイミングも、借入限度額に影響します。業績が好調な時期に申し込むことで、より有利な条件で融資を受けられる可能性が高まります。
直近の決算が好調であれば、その勢いを活かして融資を申し込みましょう。特に前年比で増収増益を達成した直後は、金融機関の評価も高まりやすいものです。
季節的な変動がある業種では、資金繰りに余裕がある時期に申し込むことも重要です。切羽詰まった状況での申込みは、審査で不利に働くことがあります。
将来の成長性をアピールする行動も効果的でしょう。新規取引先の獲得や新商品の開発など、今後の業績向上につながる具体的な要素があれば、積極的に伝えましょう。
借入残高を減らす
既存の借入残高が多いと、新たな融資の限度額は低く設定される傾向があります。計画的に借入残高を減らすことで、新たな借入の余地をつくることができます。
高金利の借入から優先的に返済することで、全体の金利負担を減らし、収益性を高めることができます。これにより、金融機関からの評価も改善します。
借入金の一本化(おまとめ)も、検討してよいでしょう。複数の借入を一本化することで管理が容易になり、全体の返済負担も軽減できる可能性があります。
返済実績を着実に積み上げることも重要です。期日通りの返済を続けることで信用力が高まり、将来的により有利な条件での借入が可能になります。
目的に合わせた融資形態の選び方
借入目的や返済計画に合わせて、適切な融資形態を選ぶことも重要です。
証書貸付と当座貸越
証書貸付と当座貸越は、代表的な融資形態の2つです。それぞれに特徴があり、資金用途や返済計画に合わせて選択する必要があります。
証書貸付は、融資契約時に一括で借入を行い、決められた返済計画に従って返済していく方式です。主な特徴は、以下の通りです。
- 一括で借入を行い、毎月定額を返済する
- 金利は固定金利が多く、返済計画が立てやすい
- 設備投資など、使途が明確な資金に適している
- 一度返済した分は再度借りられない
一方、当座貸越は、あらかじめ設定された限度額の範囲内で、必要に応じて借入と返済を繰り返せる方式です。主な特徴は、以下の通りです。
- 必要なときに必要な金額だけ借入可能
- 使った分だけ金利が発生する
- 返済も自由に行える(限度額内で再借入も可能)
- 季節変動がある業種や、短期の資金不足に対応するのに適している
資金需要のパターンを分析し、最適な融資形態を選ぶことで、金利負担を抑えつつ必要な資金を確保できます。
用途に合わせた融資制度の活用
資金の用途に応じて、さまざまな公的融資制度や民間の融資商品があります。これらを上手く活用することで、より有利な条件での借入が可能になることがあります。
公的融資制度としては、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資などがあります。これらは、民間金融機関に比べて金利が低く、長期の返済期間が設定できる場合が多くあります。
| 資金用途 | おすすめの融資制度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 創業資金 | 日本政策金融公庫の新創業融資制度 | 無担保・無保証人で最大3,000万円 |
| 運転資金 | 信用保証協会のセーフティネット保証 | 一般保証とは別枠で保証を受けられる |
| 設備投資 | 設備資金貸付制度(各金融機関) | 設備の耐用年数に合わせた長期返済が可能 |
| 事業拡大 | 中小企業経営力強化資金 | 経営改善計画実施に必要な資金を支援 |
また、資金用途に特化した、民間の融資商品も増えています。例えば、IT投資向けの融資商品や、環境配慮型設備導入のための低金利融資などがあります。
複数の融資制度を組み合わせることも有効です。例えば、設備資金は公的融資、運転資金は民間銀行からの融資というように、用途に応じて最適な資金調達先を選ぶことができます。
まとめ
借入限度額は、企業の返済能力や業種特性、現在の借入状況などによって決まります。自社の状況に合った計算方法を用いて、適切な借入限度額を把握し、無理のない資金調達計画を立てることが大切です。
借入限度額を増やすためには、自己資金の増強、明確な事業計画の作成、業績好調時の申込み、借入残高の管理が効果的です。また、資金用途や返済計画に合わせた融資形態や制度を選択することで、より効率的に資金調達することが可能になります。
最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン
事業資金の借入を検討する際は、金利や返済条件だけでなく、審査にかかる時間や手続きの簡便さも考慮する必要があります。特に、資金需要が急な場合は、迅速な審査と柔軟な対応が可能なサービスを選ぶことがポイントとなるでしょう。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。