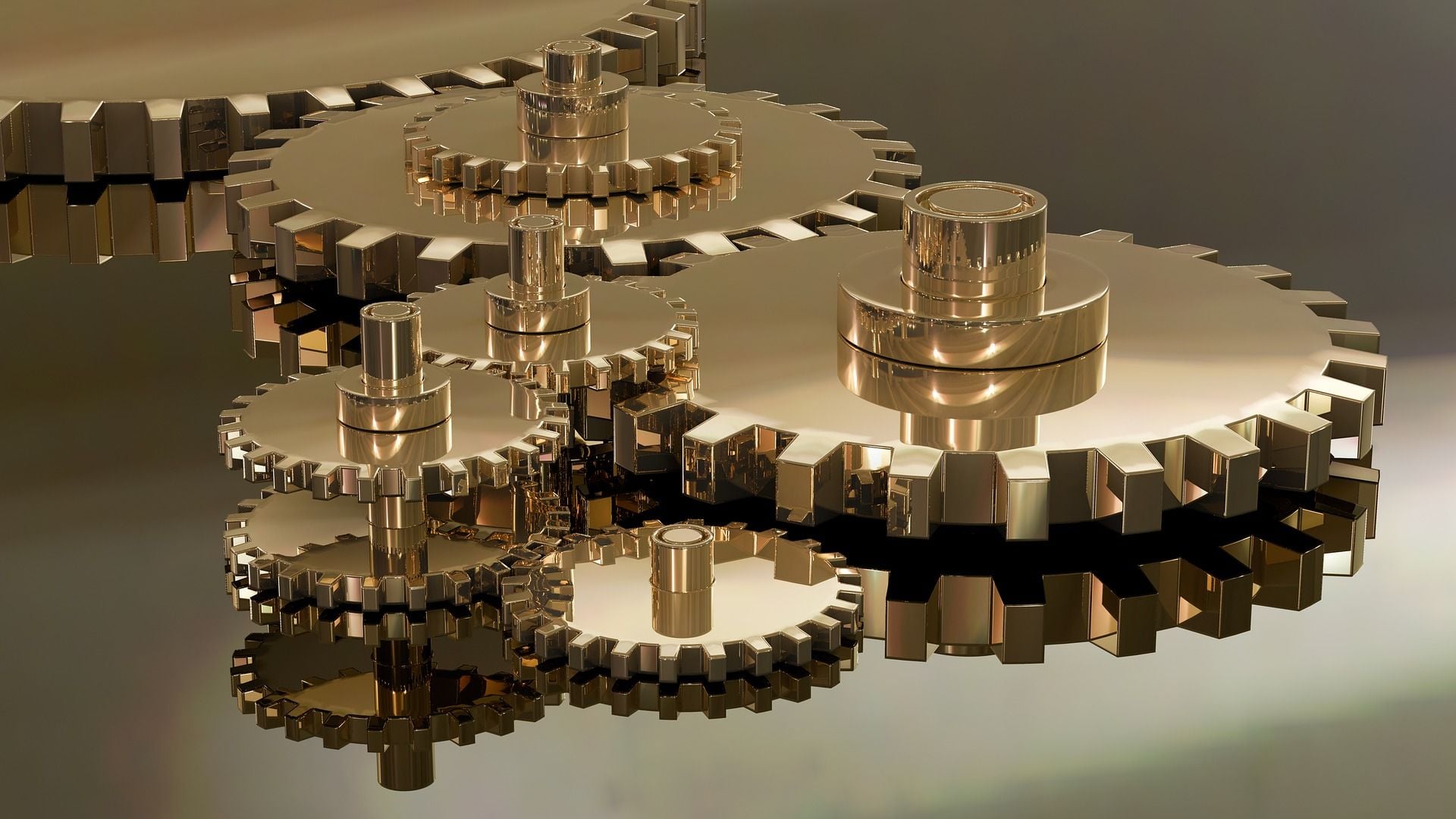2025.01.31
「事業性評価」とは?ローカルベンチマークを活用した中小企業の成長戦略

「事業性評価」とローカルベンチマーク
ローカルベンチマークの概要
前回のコラムに続いて、「事業性評価」の実務について説明します。
2016年に経済産業省が公開したローカルベンチマークは、無料で利用できる効率的なシステムです。実際の「事業性評価」について、金融機関や中小企業の双方が戸惑いを抱く中、このシステムは行政が提案した広範な活用が可能な仕組みとして注目されています。
「事業性評価」における財務情報と非財務情報
ローカルベンチマークでは、財務情報と非財務情報の両方を評価対象とします。財務情報は主に数値的な指標を用いた客観的評価で、非財務情報はビジネスの流れや組織体制を可視化する役割を担います。これにより、中小企業の強みや改善点を明確に把握できます。
財務情報の6つの指標
売上増加率と営業利益率
財務情報には6つの主要指標があります。
売上増加率は、「直近売上高÷前期売上高-1」で計算します。売上の伸びは重要なアピールポイントですが、利益率を犠牲にして売上至上主義に陥る場合、評価は下がります。会社の戦略が利益率重視であれば、売上増加率だけでビジネスモデルを判断するのは不適切です。
営業利益率は、「営業利益÷直近売上高」で算出されます。「事業性評価」においては、この指標が特に重視されます。本業の収益力を示す営業利益こそ、企業の価値を測る重要な基準とされています。
労働生産性とEBITDA有利子負債率
労働生産性は、「営業利益÷従業員数」で求めます。この指標は、会社の利益を従業員一人当たりの生産性として評価します。従来の「付加価値÷従業員数」ではなく、営業利益を重視している点が特徴です。
EBITDA有利子負債率は、「(借入金-現預金)÷(営業利益+減価償却)」で計算します。EBITDA(税金・利息・減価償却前利益)は、会社の収益力を示す指標で、財務の健全性を評価する際に用いられます。特に、本業を基準にした指標として重要です。
非財務情報の重要性
商流・業務フローの理解と事業俯瞰図の作成
非財務情報には、会社内外の業務プロセスを把握するための「商流」と「業務フロー」が含まれます。
業務フローでは、業務を遂行する順序やプロセスを図表化し、改善点や差別化ポイントを明確化します。作成には、実際の業務担当者との協力が必要です。
商流把握のためには、「事業俯瞰図」が役立ちます。この図は、仕入先からエンドユーザーまでのビジネスモデル全体を可視化します。同業他社との違いを明確にし、差別化ポイントを強調することで事業の強みを示せます。
経営者・事業・環境に関する4つの情報項目
ローカルベンチマークでは、以下の非財務情報も評価対象です:
- 経営者に関する情報:企業理念(ビジョン)、事業実績、後継者の有無など。
- 事業に関する情報:沿革、SWOT分析、ITシステムの活用状況。
- 企業を取り巻く環境:市場動向、競合分析、顧客リピート率など。
- 内部管理体制:組織の管理体制や人材育成計画など。
これらの情報は、財務データでは捉えきれない企業の実力や成長可能性を示す重要な要素です。
まとめ
本記事では、「事業性評価」とローカルベンチマークの概要、財務情報の6つの指標、さらに非財務情報の重要性について解説しました。これらの指標と情報は、中小企業が自社の現状を客観的に把握し、経営課題を明確化するための有用なツールです。
しかし、これらの情報を正しく活用し、実際の経営戦略に落とし込むことは容易ではありません。また、自社の強みや成長性を効果的に金融機関や投資家に伝えるには、専門的な知識と適切なアプローチが求められます。
そんな中小企業様の頼れるパートナーが、HTファイナンスです。HTファイナンスは、豊富な知見と30年以上の実績を活かし、事業性評価をはじめとする経営支援を通じて、企業の成長をサポートいたします。
資金調達や経営改善に関するご相談は、ぜひHTファイナンスまでお気軽にお問い合わせください。